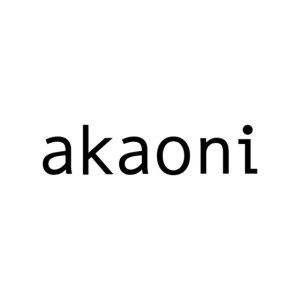ハイエンドなホテルを思わせる空間デザインやホスピタリティで、新しい医療施設のあり方を提示している鶯谷健診センター。2010年のリニューアルでは「健康診断サービスのトータルデザイン」が評価されグッドデザイン賞を受賞するなど、予防医学が重視される未来を見据え、健診センターの新たな価値を生み出してきた。
その空間づくりに、10年にわたり携わってきたのが株式会社丹青社だ。医療施設になぜ、デザインが必要とされたのか。また、これからのホスピタリティ空間に求められるものとは? 鶯谷健診センターの中條克幸さんと、株式会社丹青社の三石俊治さんにお話をうかがった。
デザインとサービスを徹底した「病院らしくない」空間
鶯谷健診センターは、人間ドック、生活習慣病健診など、予防医療を総合的に提供する都内屈指の大規模健診施設。2010年からリニューアルを続け、男女別のフロア構成、アテンダントによる案内など、「サービス業」に徹した運営に舵を切った。なかでも注目を集めたのが、上質さにこだわったシックな空間デザインだ。
中條克幸さん(以下、中條):たとえば、5階の男性専用の人間ドックフロアのロビーは、ウォールナットの無垢板を多用した木目調のインテリアで、アロマの香りが漂い、ジャジーなBGMが流れるくつろいだ雰囲気にしています。採血スペースでは、包み込まれるような座り心地の良いカッシーナのソファが検査のストレスを和らげてくれます。

中條克幸 医療法人社団せいおう会 鶯谷健診センター 副理事長

5F男性専用の人間ドックフロア。壁などには無垢の木素材を使用しており、施工から10年以上経過しているがデザインも古びず、居心地のよい深みや味わいがある
バリウムを飲む方など誰もが利用するトイレは、壁のタイルのパターンからデザインを起こすなど、どこよりもこだわりました。2017年に新設したVIPルームはソファやデスク、有機ELテレビなどを備えたスイートルームスタイルで、診察室もセットになっているためすべての検査を個室内で受けられます。

男性専用の人間ドックフロアのトイレ。タイルひとつひとつのデザインにこだわり、ホテルのような風合いを感じる
三石俊治さん(以下、三石):僕は2017年のリニューアルのときから関わらせていただいているのですが、初めて訪れたときはハイエンドなホテルにも引けを取らないクオリティに驚きました。

三石俊治 丹青社 コマーシャルスペース事業部 第2営業統括部 営業1部 部長
中條:リニューアル当初は、よくお客さまが帰ってしまったんですよ。今までの健診センターのイメージと大きく異なるので、エレベーターが開いてここに入ると「間違えた」と思うらしくて(笑)。でも次第に口コミで評判が広まり、2年目くらいからは予約でいっぱいになりました。
病院をはじめとした医療施設のほとんどが、壁も床も全体的に真っ白で無機質なイメージがあると思います。しかし、健診センターは健康な人がいらっしゃる場所で、体調が悪いときに訪れる病院とは求められるものも違う。そこでリニューアルにあたっては、「病院らしくない」空間にしようと思ったんです。

3F女性専用の人間ドックフロア。全体的に明るく、長時間の滞在でも居心地の良い空間を目指した。点在する植物は生花を使用
設計にあたっては、人が移動する「導線」にも工夫が凝らされた。たとえば4階にMRIやCTの検査室を配置することで、3階の女性専用フロア、5階の男性専用フロアの双方からアクセスしやすくなっている。また受診者の移動には、アテンダントシステムが採用された。
中條:当センターでは大手航空会社グループによる接遇研修を受けたスタッフがお客さまをアテンドし、次に検査をする場所までご案内しています。ですから、館内に案内板はいりません。「検査室」「診察室」といったサインも、扉や壁に小さく入れるだけにしています。大きな案内板があると、途端に医療施設らしさが出てしまうため、それを無くすためにたどり着いた、アテンダントシステムなんです。

スタッフによる誘導があるため、検査室のサインは必要最小限で運用可能
三石:ホスピタリティとデザインが密接に結びついているんですよね。
中條:そういうわけです。わかりやすい例として、レントゲン室があります。多くの医療施設のレントゲン室は技師のいる操作室が撮影室の奥にありますが、そうすると技師は外に出られず、マイクでお客さまを呼び込むことになります。しかしそれでは、アテンダントシステムの利点が活かせません。そこで、操作室と撮影室を反対に配置しました。これだと技師が自らお客さまを呼び込むことができるし、操作室をお客さまが通るので、室内をいつもきれいにしておこうという気持ちも生まれるんです。
三石:ここでは医療器具が雑然と並ぶような光景も目にしませんし、医療施設でよく見るような注意喚起やお知らせといったポスターがまったく貼られてないことも特徴ですよね。あと、僕も打ち合わせなどで何度も訪れていますが、ハイレベルな空間を日頃から維持されていることにも驚かされます。
中條:そのために、デザインレベルをこれだけ上げているというのもありますよ。たとえば家庭でも、塵ひとつ落ちていないスタイリッシュな部屋にいたら、散らかしにくいじゃないですか。ポスターに関しては禁止にし、アートワークをあちこちに置いています。つまり、ただきれいな空間をつくるだけではなくて、綺麗な空間が維持されるようにデザインしているんです。
健診衣やデザートまで、妥協しないトータルブランディング
中條:これまでプロデューサーの仕事をしてきた経験から、「人間ドック」に「デザイン」を掛け合わせた健診センターにしてはどうかと考えていました。しかし、当初、都内にそのような健診センターは例がなく、私自身も従来のいわゆる“病院”のような施設のイメージを払拭できずにいました。
そんな時、当時新宿の高層複合ビルに入っていた飲食店の空間デザインがすごくいいなと思ったんですね。そこは中華料理店なのに、中華料理店らしくない空間で、「健診センターも“らしくない”空間にすればいいんだ!」と思いつきました。
三石:その頃のリニューアルからさらに時が経ち、私が前任者から引き継いでお付き合いを続けさせていただいたのは、2017年のリニューアルプロジェクトからです。3階の女性専用人間ドックフロアの新設、5階の男性専用人間ドックフロアの一部改修、またVIPルームの新設などを行いました。しかし、プロジェクトマネージャーという立場として、最初は「どうしたらいいんだろう」という戸惑いがあったのが正直な気持ちでした。
というのも、中條さんからのご依頼は、すでにグッドデザイン賞などを受賞して評価されている施設を「もっとホテルのようなホスピタリティ性を高めた空間にしたい」というものだったので。このグレードを超えるものを提案すべく、社内でも中條さんの期待に応えられるデザイナーを再検討し、現在クリエイティブディレクターである猪瀬恭志が担当することになりました。中條さんは事業主さまであると同時にデザインにも精通しているので、通常の医療施設を手がける場合とは異なるアプローチが可能なチーム体制で挑みたいと思ったんです。

VIPルーム。すべての検査を個室内で行うことができる特別な設えに
中條:いっぱい闘ったよね。
三石:闘いましたね(笑)。特にプロジェクトの予算、工期をまとめるのはハードルが高かったです。設計への要求レベルを具現化するにあたって、お預かりした予算内でいかに収めるか。また、マテリアルや納まりなどすべてにおいて高いクオリティを徹底するため、スケジュールを考慮しながら納得いただけるまで何度もご提案を繰り返しました。そうやって少しずつ、中條さんの信頼を得られたように思います。
中條:私の要望とデザイナーや制作チームとの間に立って、三石さんは大変だったと思います(苦笑)。でも、それから長い付き合いになったよね。いま思うと、このデザインは丹青社だからできたんだと思います。
一流のデザイナーは自分のデザインを押しつけるのではなく、クライアントのコンセプトや好みをデザインで表現できる人だと思っているんですが、デザイナーの猪瀬さんもまさにそのタイプでした。デザインって、一つひとつの積み重ねなんですよね。先ほどの導線の話もそうだけど、説明されなかったら素通りしてしまうような小さな工夫の積み重ねが、訪れた人に「なんだか心地いいな」と感じさせることができるんだと思います。
鶯谷健診センターの革新性は、デザインやサービスにとどまらない。その根本にあるのは、ビジョンを掲げ、収益をあげるビジネスとして医療施設を再構築するブランディングの視点である。
三石:中條さんのこだわりは、空間だけではありません。企業診療で使われる健診車のグラフィックデザインによるラッピングや、センター内で着用する健診衣のデザイン、また人間ドックが終わったあとに専用ラウンジで提供される「薬膳ご飯」、デザートまで、一貫したブランディングが行われています。

人間ドック終了後に提供される「身体にやさしい薬膳ご飯」。これも中條さんがメニューを検討した
三石:それらひとつひとつが効果的に作用して、受診してみると最初から最後まで居心地よく快適に過ごせるので、年間約28万人という多くのお客さまに選ばれている理由がよく分かります。日本全国の空間づくりをお手伝いしている当社としては、鶯谷健診センターに携わって得た医療施設におけるトータルブランディングの視点を、より多くの医療機関にお伝えしていきたいですね。それが結果として、医療サービスそのものの向上にもつながりますから。
中條:医療機関もこれからは、ホスピタリティの視点・トータルブランディングの視点を持って運営していかないといけないと考えています。特に健診センターというマーケットは、そのフロントラインにいると思う。健診って前日から食事制限があったり、バリウムも飲まなければいけないし、受診する方にとっては本来あまり行きたくないところなんですよね。そこで、そうした負のイメージを払拭し、自分の健康と向き合う時間を、豊かで快適に過ごしていただけたらと考えました。健診センターもこれからは、プラスαの価値でお客さまに選んでもらう時代なんです。
ただ、いくら設備投資にお金をかけても利益をあげられなかったら意味がない。ビジネスの視点も大切に、投資した分を回収できるよう、収益効率をあげる空間設計であることも重要ですね。鶯谷健診センターはデザインにこだわり抜いて予算もかかってしまったんですが(笑)、おかげさまでたくさんお客さまが来てくださっているので、この考えは間違いではなかったのだと思っています。
- 1
- 2
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)











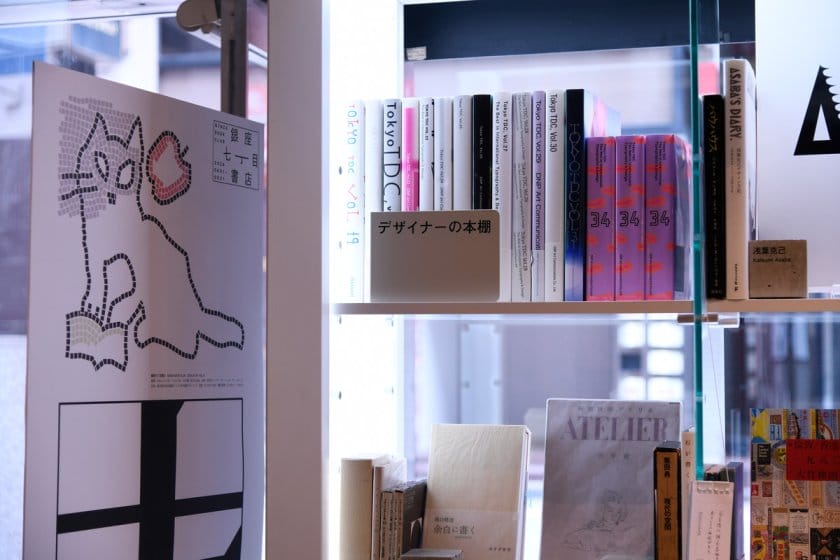
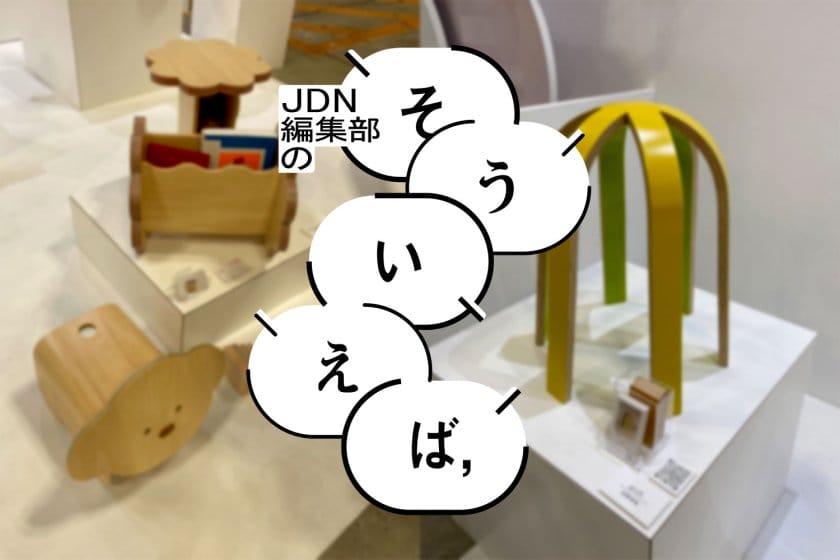

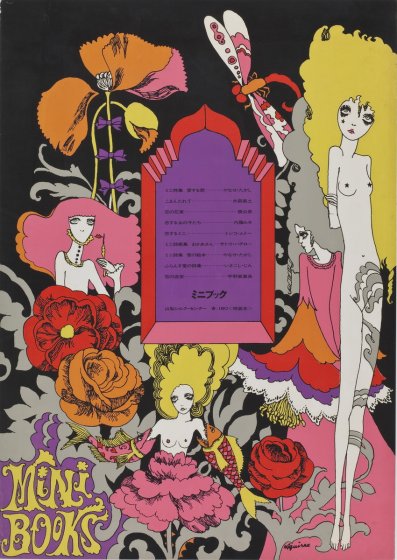
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)