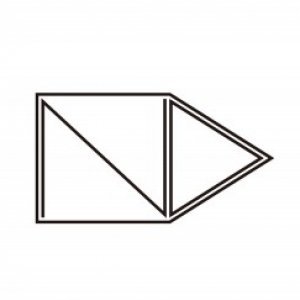幕末維新期の佐賀の歴史を4つのシーンで体感できる「幕末維新記念館」
組織の垣根を超えてプロフェッショナルが集まった新しい形のチームづくり
2017年3月に協議会が立ち上がり、4月に公示、翌月にはプレゼンという過密スケジュールではじまった幕末維新記念館プロジェクト。会期も決定済みで準備期間は1年弱、当初は誰もが「間に合わないのでは……」と思ったという。
鈴木朗裕さん(以下、鈴木):プロジェクトをまとめる立場として、まず考えたのが『歴史に詳しいメンバーを入れなくては』ということでした。そこで、佐賀県出身で社内では歴史オタクとしても有名だったプランナーの東中川に入ってもらい、提案の骨子を考えました。

株式会社丹青社 プロデューサー 鈴木朗裕
1999年丹青社入社。企業の宣伝・販促分野を中心に空間づくりに携わる。2014年にイベントプロデュース室、2017年にクロスメディアインキュベートセンターの立ち上げに参画。場と時のクロスメディア=空間を活用した感動体験づくりを実行中。
博覧会ならではのにぎわい感があるハレの場とする必要があった。また、博物館の展示とは違って、佐賀の幕末史を親しみながら体験できる空間を意識した。「明治維新150周年の歴史を未来に繋ぐためにすべきこと」という命題の元、歴史好きはもちろん幅広い層の心に響く空間づくりを計画していった。業務量や説得力の強化から、デザイナーは二人体制に。博覧会経験者でかつアイデアの発想力と瞬発力のある感覚派の阪田さんと、デザインのプロセス化と説得力に長けた理論派の吉田さんを招聘した。同期入社のデザイナーが組むプロジェクトが少ない中、二人は協業経験を持つ強みもあった。
鈴木:感覚派の阪田と理論派の吉田なのでうまく補完してくれるんですよね。そして若手を支えてくれるのが小林と川南。歴史をエンターテイメントとして見せるには小林の技術力が不可欠ですし、川南は公共施設をおもに手がけていますが商業施設の経験もあり、一級建築士や施工管理士の資格もあるので知識がとにかく豊富。博覧会の特殊性も熟知しているのでお願いしました。
この全員のスケジュールを確保できたのは奇跡に近いと笑う。社内における制度の面では、部門をまたぐことで調整が必要な部分もあったようだが、実際のクリエイティブについてはどう感じたのだろうか。
東中川華子さん(以下、東中川):継続するプロジェクトやチェーン展開のプロジェクトなどは同じメンバーでチームを組む方がスムーズでしょうけど、今回のようにどの事業部にも当てはまらないような、一度きりのプロジェクトでは、事業部横断のチーム構成はよかったと思います。

株式会社丹青社 プランナー 東中川華子
2006年営業職として入社。プランナーに転向後、エンターテインメント・プロモーション施設におけるコンテンツづくりや、商業施設におけるレストルームなどのアメニティの向上まで、幅広い分野の企画を手がける。
小林勇さん(以下、小林):演出システム担当の私はさまざまな部門と関わるので、混成メンバーは慣れています。ただ今回は、以前からよく知るメンバーなので特にやりやすかったです。人となりや仕事ぶりを知っているから。
メンバーは制作の最前線に立ち、さまざまなプロジェクトに関わっている。本件の進行中にも全員が7~8件のプロジェクトを並行して扱う状況にあった。それだけに特別なスケジュール共有やタスク管理を行っているかと思いきや、ツールはGoogle関連ツールなど、ごくごくシンプル。それよりも鈴木さんが意識したのは、メンバーの打ち合わせ時間の確保だ。調整がつきにくい状況を見越し、最初に向こう一年の社内定例会議週1回とお客さまとの定例会議を月2回を組みこんだ。その後、全員で佐賀まで赴くお客さまとの定例会議が頻繁に行われたが、この施策がなければプロジェクトの実現は難しかったに違いない。

株式会社丹青社 テクニカルディレクター 小林勇
1987年丹青TDCに入社、2001年丹青社に転籍。テーマパーク、博覧会、イベントなどの演出システムの設計・施工を担当。映像音響、照明、噴水、特殊効果などを手がけ、特にショー制御が得意。ペットの亀吉(クサガメ)とは22年の付き合い。
クライアントから『仲間』へ
鈴木:お客さまと密にコミュニケーションを取れる環境がつくれたことは、非常に大きな意味がありました。当社が提案した内容に対するお客さまからの要望を元に、さらにアイデアを重ねていく形で企画を進めました。お客さまに信頼していただけたことで先に続く関係がつくれました。
東中川:最初はかなりキツく言われましたよね。このプロジェクトに対するお客さまの想いが非常に強いこともあってか、プロポーザルに通った企画なのに「全然ダメ」と(苦笑)。
鈴木:それをただ受け入れるのではなく、博覧会のプロフェッショナルである我々の知見を加えたデザインや意見をいつも返すようにしていました。そのやりとりの中で出てきたのが「心を震わせたい」と「泣かせたい」というキーワード。何をもって「心震わせ」「泣かせる」のか、企画の肝となるお客さまのご要望を早い段階で汲めたことでより具体的な案を提示でき、最終的にはお客さまとも仲間としてタッグを組めたのだと思います。
会議中の伝え方にもこだわった。例えば、お客さまとの定例会議での映像の台本読みを小林さんに依頼。阪田さんとの掛け合いも含めた講談口調で突然披露し、協議会の事務局である佐賀県側スタッフの度肝を抜いた。
鈴木:県の方に書面と図面でそのまま返すよりは、違う形のほうがいいんじゃないかなと(笑)。驚きながらも皆さん喜んでくれて、台本にも納得してくれました。あれも結束できた一つの瞬間だった気がします。

- 1
- 2
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)











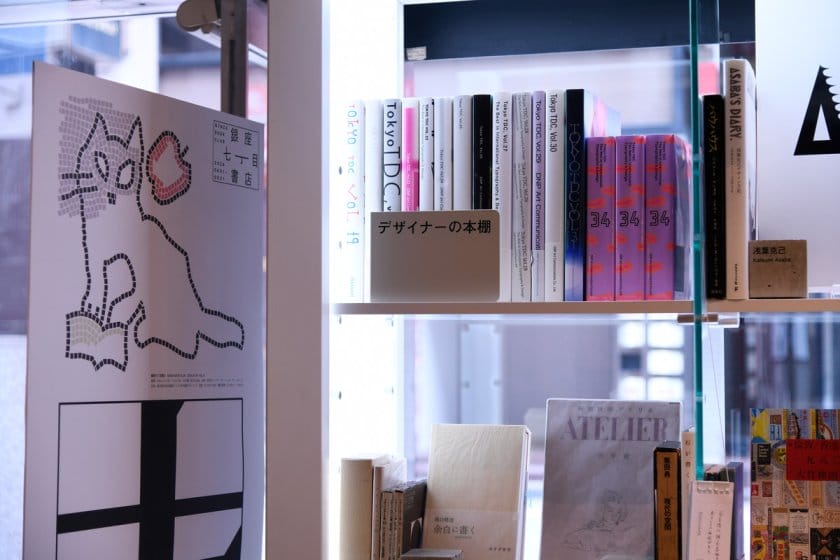
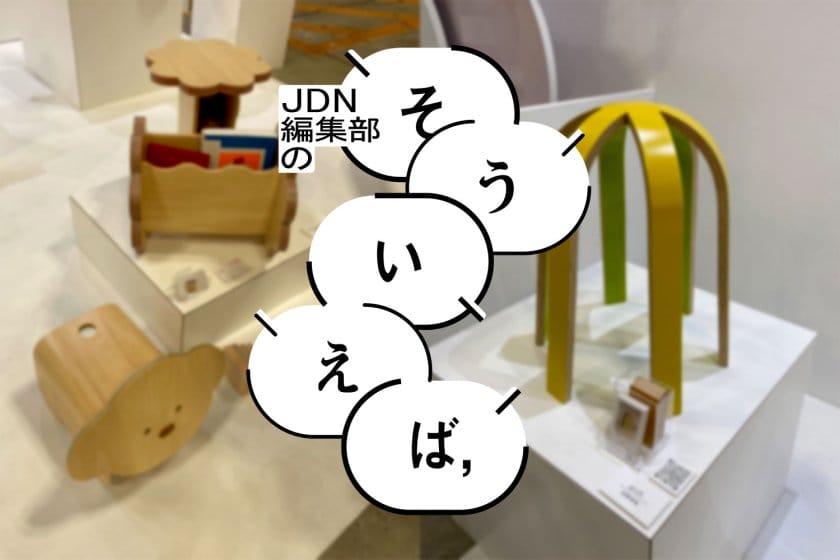

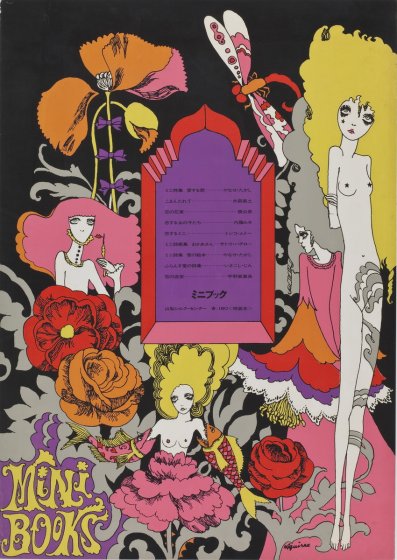
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)