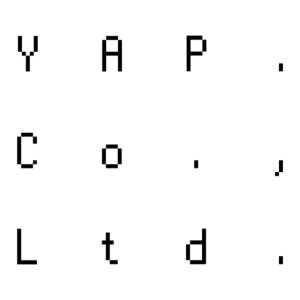空間づくりへの想い、その軸となるデザインセンター
丹青社のWebサイトには、「空間づくりのプロフェッショナルとして『こころを動かす空間』をつくりあげる」と書かれている。一口に空間と言ってもさまざまな意味があるだけに、同社ではどう定義しているかをまずは尋ねてみた。

株式会社丹青社 Webサイト
https://www.tanseisha.co.jp/
德増照彦さん(以下、德増):当社が指す「空間」は、場所や意義で変化するものだけに定義は少し難しいですね。それ自体というよりは、「人と人が交流する空間とはどうあるべきか」を重視するからです。私たちが目指しているのは「人と人が交流する空間」の価値をあげること。技術が進歩し、消費し、学び、働く場でのコミュニケーションが変化するいまだからこそ、私たちの考える空間の最大のエレメントは“人”なんです。人がいて初めて成立し、どんな人がそこにいるかで在り方が変わる。当社のデザイナーたちは、皆その最も大事なものを感じ取ってデザインに反映しています。

株式会社丹青社 取締役常務 デザイン担当/デザインセンター長 德増照彦さん
戸髙久幸さん(以下、戸髙):当社は事業領域を「社会交流空間づくり」と定めています。「人とモノ」「人と情報」そして「人と人」。社会を構成する物事の中心を考えると、当社では「人が関わるさまざまな場をつくる」ことに丹精を込めて、「空間づくり」と呼んできました。
空間をつくる軸になる存在がプランナーやデザイナー、いわゆるクリエイティブ職である。従来、クリエイティブ職は、商業や文化などの分野でわかれている事業部ごとに所属していたが、先日のデザインセンター設立によって約250名の一大デザインチームとなった。会社を創業して70年間でも初の試みだが、これはデザイン職出身であり「デザインの強化」を唱えた会長・青田嘉光さんと制作職出身の社長・高橋貴志さんの思いを具現化したプロジェクトだったという。

組織設立にあたりつくられた「DESIGN CENTER」ロゴ
德増:例えば、小売店舗と博物館のように、商業空間と文化空間は相見えることがないという感覚が社内には長くありました。ですがいまの時代、たこつぼ化した専門家の視点だけでは限界があり、そうした縦割外のハイブリッドな空間が求められるようになってきた。そこでデザイナーを結集させれば文化領域のノウハウがリテールに、リテールの要素が文化施設にと新たなプラスアルファや刺激が、手がける空間に反映できるのではないかと考えたのです。
博物館や美術館併設のカフェやレストランもその一つ。同社には双方のノウハウがあるのだから、もっと融合して、より活かしたい。だからこそ、立案時からプランニングや企画の形でデザイナーが柔軟に提案し、形にできる仕組みを作りたかったという。
德増:ビジネス構造に直接触れる部分だけに、社内の仕組みを変えるためには、非常に高い壁がありました。しかしデザイナーは、当社の大事な財産です。彼らの能力を伸ばすためなら、困難を乗り越えてでも実現させるべきだろうと。新たな提案ができる幅広いジャンルのデザイナーがいることこそが、私たちの一番の強みだからです。
2年を要した「個を徹底的に育成する」ための仕組みづくり
新たな仕組みづくり、その重大な任務を務めたのが戸髙常務だ。期間にして約2年。テクニカルパートナーなどを含め400人もの人材の位置づけを変えるため、明確なコンセプトを掲げ、全社視点で社内構造や制度の見直しまでを見据えて取り組んだ。
戸髙:営業とデザイナーは、職能の違いやそれぞれの想いもあり、場面によっては「もっとこうあるべき」「こうすべき」といった双方の視点で熱い議論になることもあります。ですが、その大元を辿ればすべては『より良い空間づくりのため』そして、『お客さまのため』という強い気持ちによるもの。過去、経営危機に陥った際も、事業部ごとに同じお客さまに向き合った者同士で協力して乗り切ってきました。今回は、その協力を全社で行うための施策です。デザイナー出身である会長・青田の『日本一のデザイン企業にするためにはどうすべきか』という問いを受けて、社長である高橋が掲げた「デザイン力の強化」を実現するため、お客さまに価値あるデザインを提供していく一体感を醸成する形を考えてきました。

株式会社丹青社 取締役常務 経営企画、経営管理、グループ全般担当 戸髙久幸さん
德増:特に苦労したのが新たに配置したマネージャー職の任命です。若手デザイナーの自立と個性確立が最大の課題だけに、知見があり経験値も高いベテランに後進の育成とマネジメントを任せたいと考えました。部門としての収益や、勤怠管理はもちろん、各デザイナーの強い意欲とタイムマネジメントを同時にコントロールできる冷静さも必須です。しかしそうなると、デザインの現場との兼務ではなく、マネージャー業に専念してもらう必要がある。第一線で活躍してきたデザイナーとしての自負がある彼らです。新たな仕事に納得して専念してもらうためにも、その役割の意義や次世代の人材を育成していくことの重要性について説き、何度も話し合いを重ねました。
世界一のデザイナーを育成するプラットフォームの狙いは、「個を徹底的に育成する」こと。だからこそ、その先頭に立つべきマネージャーの任命に時間をかけた。その第一歩を踏み出せたいま、次の課題は個々の長所を活かしたオンリーワンのデザイナーに成長させること。才能のある人材のクリエイティビティ、個性をさらに引き出すため、良質な刺激や影響が受けられる環境が必要だと彼らは考えた。成長を促す刺激という部分で、センターの働く場づくりに明確な工夫も施している。
德増:デザインセンター設立にあたり、すべてのプランナー・デザイナーひとりひとりと面談する機会を設けた際に、若手の約8割が「もっと多くの人とコミュニケーションを取りたい」という希望があったんですね。そこでまずはオフィス内のデザインセンターエリアにもフリーアドレス制を導入し、自然と会話が生まれる空間構造に変えました。その結果、従来プロジェクト内でしか共有されていなかったプリンシパル(丹青社におけるトップクリエイティブディレクター)の生の言葉や分析、指導内容を、デザイナー全員の共有財産にできるようになりました。また、それぞれに得意分野をもつデザイナー同士が互いにコミュニケーションを取り、影響を与え合って成長できる環境になりました。

その他にも、若手デザイナーを中心とした事務局が自主的にトークイベントやワークショップなどのイベントを企画・実行するクリエイティブサロン、ミラノサローネをはじめとした海外のデザイン視察など、デザイナーの経験値を向上させる機会がいくつも用意されているという。また、デザインセンターのプレプロジェクト的な「クリエイティブカンファレンス」も行われてきた。部門や階層の垣根を取り払って人材が集まり、ひとつのプロジェクトやテーマについてコラボレーションするというものだ。
德増:この取り組みはデザインセンター設立に向けた自信となりました。事業部間の枠も比較的早く消えましたし、そのプロジェクトに最適なリーダーを据えることで、リーダーによる最適なチームビルドも可能になったのです。現在はこの手法が日常的に行われるようになりました。

社外デザイナーを招いたトークセミナーも度々行われる
- 1
- 2
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)











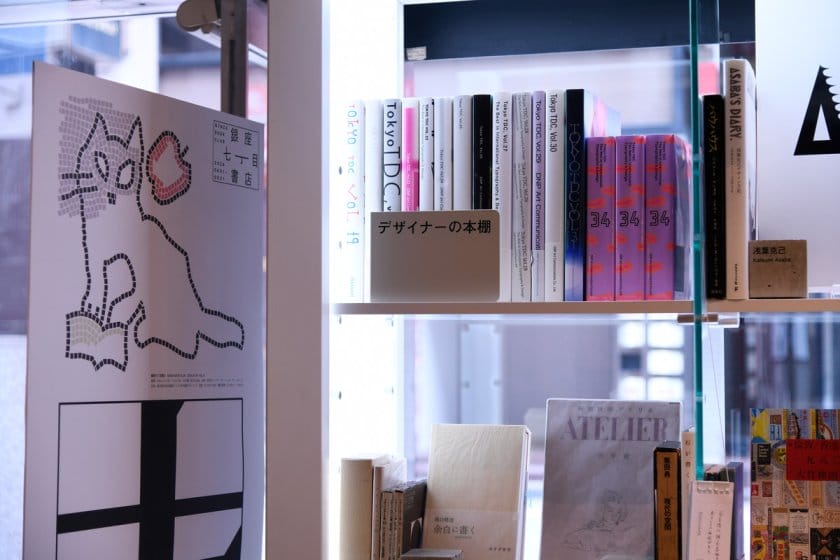
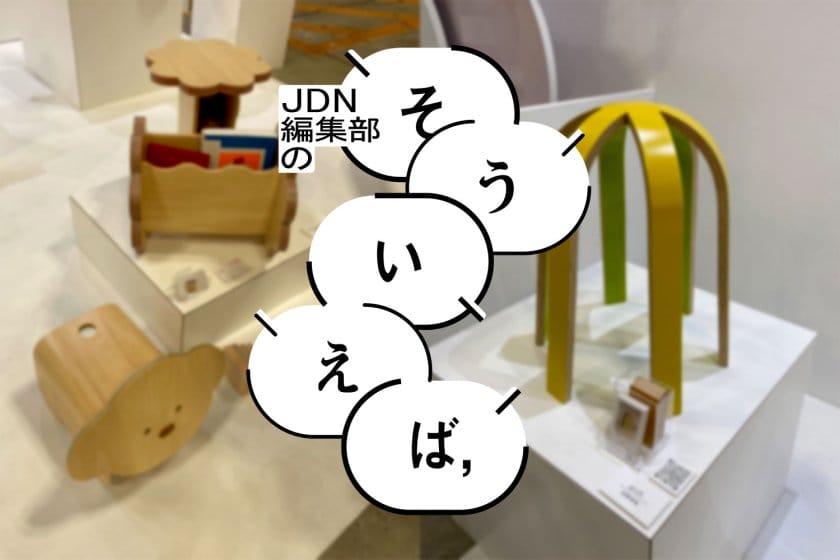

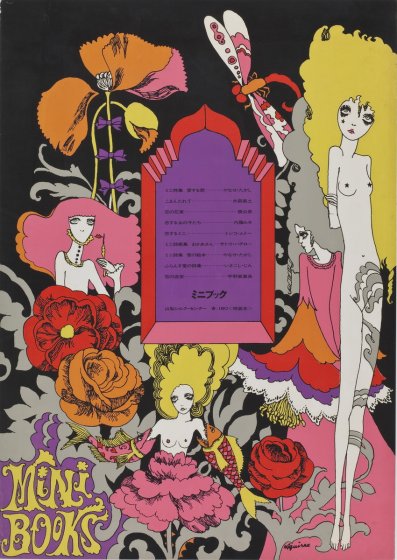
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)