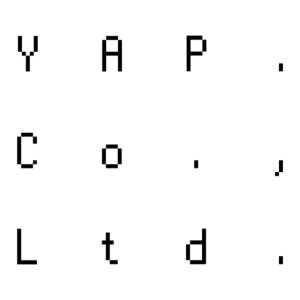編集部の「そういえば、」2020年10月

どうしても言いたいわけではなく、特別伝えたいわけでもない。そんな、余談以上コンテンツ未満な読み物としてお届けする、JDN編集部の「そういえば、」。デザインに関係ある話、あんまりない話、ひっくるめてどうぞ。
デザインの視点から、『TENET』ついて思うこと
そういえば、そろそろそのほとぼりも少し収まりつつあるように思いますが、クリストファー・ノーランの『TENET』について、少し考えたことを書いてみようと思います。
公開されるやいなや、WebメディアやSNS、ラジオ、ポットキャストなど、さまざまなところで取り沙汰されている『TENET』ですが、ぼくも公開日に観に行ってから、世の中を飛び交う毀誉褒貶を読んだり聞いたりしてしばらく過ごしていました。ですが、なんだかもの足りないなぁという気持ちがあるんですね。
というのも、誰もが一貫してこの『TENET』という映画の複雑な構造そのものについて語ることに大半を費やさざるを得なくて、最終的に「わかった/わからない」という話に終着してしまうからなんです。それは、この映画がかつてないほど入り組んだ話になっているので無理もないのですが、ここまで「この映画がどういう構造になっているか」に終始してしまうことって、なかなかないことだよなぁと思います。
「時間が逆行する」という設定によって物語が駆動してく本作ですが、過去から未来へと進んでいく一本の線だけではなく、それが逆行することで折れ曲がり、時間の線が重なっていく。さらにその線が思ってもない方向へまた逆行・順行していくので、一回観ただけではまず理解できない。ぼくも初見時は「なんだかみんなとても大変そう」ぐらいしかわからず(理解力のなさ……)、IMAX映像の迫力とルドヴィグ・ゴランソンのスコア、そして俳優たちの美しい演技に見惚れることしかできませんでした。
おそらくこの映画について語ろうとする人は、何度も繰り返し劇場に足を運んでいると思うんですね。確かに、結末を理解した上でもう一度150分の映像を観ることで、逆行して折れ曲がった時間の線を頭の中でほどき、整理しながら観ることができる。そうすることで、「ああ、このシーンですでにこれから起こることが暗示されてるなぁ」とか「けっこうセリフで説明してくれてるなぁ」とかがわかってくる。ぼくは3回観たんですが、一応なにがどうなっていたかは理解できたと思います、たぶん。
で、さまざまなところで『TENET』について語られているときに、なにがもの足りないなぁとぼくが感じたかというと、時間が逆行する世界を描くこの『TENET』という映画の構造、つまり“『TENET』のデザイン”についてしか、語られていないように思えるからなんです。確かに、複雑な時間軸やプロットの構造、見せ場となる逆行・順行が混じり合うシーンの分析など、精緻に読み解くことがおもしろい映画ではあると思うですが、それらはどれも『TENET』という映画のデザインについてしか語られていなくて。そのことに、なんだかなぁとぼくは感じてしまった。
映画は総合芸術と言われるだけあって、映像や脚本、編集、音楽、照明、衣装、美術、役者の演技など、さまざまなアートフォームが集積することで生まれるものですが、ひとつひとつの要素がもつ美しさとそれらが組み合わされることによって生まれる化学反応、さらに巨額の制作費や膨大な時間とスタッフによって生み出されるという、「映画が映画である」という事実そのものに対してなど、さまざまな視点から楽しみ、味わうことができるものだと思います。なので、『TENET』のように、複雑で難解な映画がつくられたことそのものについて感動し、語られること自体は、まったく間違ってはいないと思います。
ただ、今回『TENET』について考えながら気づいたのは、映画が「なにを描いているのか」ということの方が、個人的には興味があるなぁということでした。つまり、『TENET』という映画のデザインについて語ることに、そこまでは関心が湧かないんですね。なぜなら、それは「どう描いているか=How」の話であって、どういうわけか、ぼくは「なにを描いているか=What」、もしくは「なぜそれを描いているのか=Why」の方に意識が向いてしまうようです。
『TENET』でぼくがもっとも興味を持ったのは、悪役であるアンドレイ・セイターという存在でした。地図から消えた旧ソ連の街で生まれ、妻に異常なまでの執着を持ち、暴力的で非道な男。そして彼がこの映画で達成しようとしていることのおそろしさには、背筋が凍るような思いがしてしまい、スクリーンから目が離せなくなってしまった。3回の鑑賞は、確かに『TENET』がどうデザインされているかを知るためでもあったんですが、ほとんどはこのセイターという男のおそろしさに、怯えながらも惹かれてしまった部分が大きかったです。
逆にいうと、本作できちんと「What」や「Why」について語っているのは、セイターぐらいだと思うんですね。少しうがった見方をすれば、彼の動機そのものが「時間を逆行させる」というこの映画の設定に対して、無理やり大義を設けたに過ぎないとも言えなくはないのですが、彼が口にしたある“後悔”の一言は、いま世界が置かれている状況において、リアリティを持ってしまいかねないおそろしさをもつ言葉だと思うんです。『インターステラー』においても気候変動を描いていたノーラン監督なので、そこに少なからず意味があるように思えてならない。
とはいえ、ぼくはいつも映画の中でなにかひとつの要素を拡大解釈したり、過剰に感情的な反応をしてしまうきらいがあるので、これもまたひとつの誤読なのかもしれません。なので、この文章は『TENET』のデザインについてだけじゃなくて、本作が描こうとした「What」や「Why」について語るのも、案外おもしろいかもですよ、という小さな提案でもあります。ケネス・ブラナーって、やっぱりすごい俳優だなぁ。
(堀合 俊博)
青一色の展覧会
そういえば、先日、銀座のガーディアン・ガーデンで開催されている『The Second Stage at GG #51 田渕正敏展「Choice」』を見に行ってきました。
本展は、若手表現者を応援するガーディアン・ ガーデンの公募展「1_WALL」入選者の中から、各界で活躍する作家のその後の活動を伝えるための展覧会シリーズです。今回は、第11回グラフィック「1_WALL」のファイナリストに選出された、イラストレーターの田渕正敏さんによる展示です。
http://rcc.recruit.co.jp/gg/exhibition/gg_sec_gra_202010/gg_sec_gra_202010.html
田渕さんは、書籍の挿画やパッケージイラスト、CDジャケットなどを中止に手がけるイラストレーターです。ストライプ柄のシャツを拡大し、描写した作品でファイナリストに選出されました。本展では、田渕さんが継続して制作している、青色の色鉛筆や絵具で、日用品を細密に描写するシリーズを中心に展示しています。

会場に展示された作品は、容器に入れられたフルーツや折り畳まれてパッケージされた物干しハンガーなど身近なモチーフばかりですが、田渕さんが描き起こすことでいつもの印象からはまた違った、魅力的な形に映ります

今回の展示は、青色1色で表現されたイラストレーションですが、画材について以下のようにコメントを寄せています。
「使用している画材はおもにニッカー絵具のポスターカラー(スカイブルー)、uniのポスカ(スカイブルー)、ユニボール シグノ エンジェリックカラー(ACブルー)の併用です。これらの画材との出会いが青一色で絵を描き始めるきっかけになっています。この3商品はとても色味が近く、上手く併用すると細い線、グラデーション、広い面のベタ塗りを同じ質感で描くことができます。(中略)ブルーに意味を見出したのではなく、先にこの画材があってそれで何が描けるだろうという考えで始まった作品です」
田渕さんは本展に限らず、さまざまな画材で作品を制作しています。会場に並ぶ作品は、30cmサイズくらいのものから1.5mサイズのものがあったり、白い紙以外にも段ボールや、アクリルなどに支持体を変えていたりと多種多様。画材への興味からはじまったということで「このモチーフだったら、この大きさだったらこんな筆致や表現で描けて面白いな」ということなどからバリエーションが出たのかなと感じました。

ちなみに、田渕さんはグラフィックデザイナーの松田洋和さんと造本ユニット「へきち」としても活動していて、実はJDNの2018年の年賀状を描いていただいたことがありました。年賀状の制作プロセスを入口にしつつ、お二人の活動について取材した記事があるので、よかったらこちらもご覧ください!
https://www.japandesign.ne.jp/interview/newyear2018/
(石田 織座)
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)




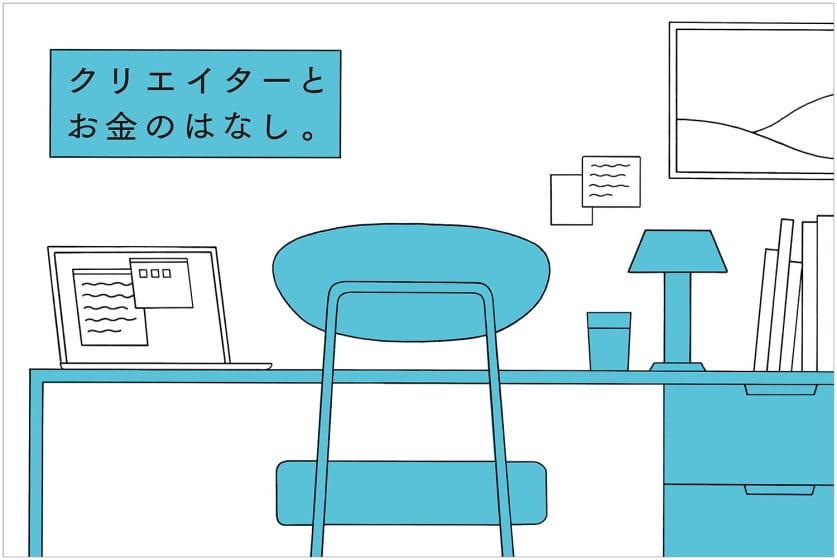







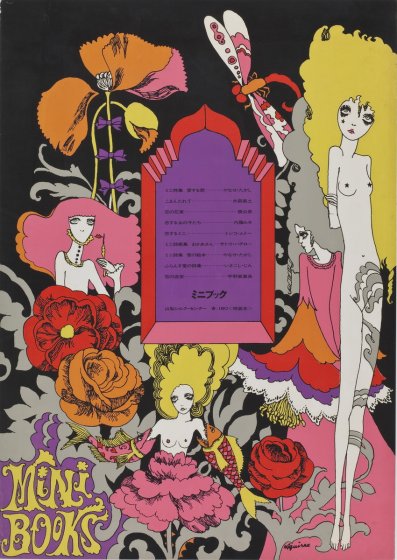
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)