JDN編集部の「そういえば、」2020年9月

ニュースのネタを探したり、取材に向けた打ち合わせ、企画会議など、編集部では日々いろいろな話をしていますが、なんてことない雑談やこれといって落としどころのない話というのが案外盛り上がるし、あとあとなにかの役に立ったりするんじゃないかなあと思うんです。
どうしても言いたいわけではなく、特別伝えたいわけでもない。そんな、余談以上コンテンツ未満な読み物としてお届けする、JDN編集部の「そういえば、」。デザインに関係ある話、あんまりない話、ひっくるめてどうぞ。
「ベゾアール(結石)」シャルロット・デュマ展
そういえば、昨日、銀座メゾンエルメス フォーラムで開催されている展覧会を拝見してきました。
11月29日まで開催されているのは、アムステルダムを拠点に活動する写真家兼アーティストのシャルロット・デュマさんによる展覧会「ベゾアール(結石)」です。現代社会における動物と人の関係性をテーマに、20年にわたり、騎馬隊の馬や救助犬など、人間と密接な関係を築いている動物たちを被写体としたポートレート作品を発表してきたデュマさん。2014年からは日本を訪問し、北海道や長野、宮崎、与那国島など全国8ヶ所を巡り、現存する在来馬を撮影し続けているそうです。
本展は、デュマさんの近年の映像作品3点を中心に、動物と人間の関わり合いを再考するというもの。馬の撮影を通じて発見した原始の風景を紐解くように、馬と関連する品々や史料との対話を試み、生と死について問いかけています。

映像作品のまわりにあるのは、テキスタイルデザイナーのキッタユウコさんによる藍染めの布を使ったインスタレーション。
会場では、映像作品3点と馬を被写体とした写真作品が複数点、馬に関する資料やオブジェが並んでいますが、中でも気になったのは、タイトルにもなっている「ベゾアール(結石)」の実物です。

結石と一緒に展示されているのは、馬の頭蓋骨
ベゾアールは動物の胃や腸の中に形成される凝固物のことで、特に乾燥した不毛な地に生息する草食動物に特有のものだそう。石混じりの土壌を歩き回って草を食むため、小石を飲み込んでしまうことがきっかけとなり、水分の不足で石は体内でどんどん成長していくのだとか。
人間の結石の実物も見たことがありませんでしたが、驚いたのは展示されていた結石のその大きさ。写真ではわかりづらいのですが、15~20cmくらいのサイズで、これが馬の体内に存在していたことが信じられませんでした。結石は古い伝承の中ではお守りや神秘的な想像と結びつくこともあったそうで、石だけど卵のようにも見えたり、ものによっては表面に独特のしわがあったり、あたたかくもありひんやりした感触も想像できるような不思議な佇まいでした。

映像作品をじっくり見るための椅子や、木の什器は建築家の小林恵吾さんと植村遥さんによるもの。
一連の展示を通して感じたのは、生と死の循環などのイメージで、映像作品はぜひ腰を据えてじっくり見てほしいと思います。また、建築家の小林恵吾さんと植村遥さんによる会場構成や、デュマさんと数年来協働を続ける、テキスタイルデザイナーのキッタユウコさんによる藍染めの布を使ったインスタレーションも世界観を増幅させてくれています。気になった方はぜひ実物を見に行ってみてください。
(石田 織座)
『ようこそ映画音響の世界へ』
そういえば、公開中の映画『ようこそ映画音響の世界へ』を観に行きました。
映画の中で使用されているあらゆる音の制作背景に迫るドキュメンタリーなのですが、俳優たちの音声をはじめ、登場人物たちを取り囲む環境音、自動車や飛行機、船などの機械音、SF映画における効果音、そして音楽にいたるまで、わたしたちが意識をしないほど自然と映画の世界に入り込むことをたすける映画音響という仕事の醍醐味を、十二分に感じることができる映画でした。
映画全編を通して、「VOICE」「SOUND EFFECT」「MUSIC」というセクションに分けて映画音響の制作プロセスが順を追って丁寧に映し出されていくのですが、戦争映画におけるマシンガンの音がいくつかのリズムパターンをつくった上でアンサンブルされていることや、『トップガン』の戦闘機の音に動物の鳴き声がミックスされていることなど、つくり手たちの創意工夫の数々には「なるほど…!」と何度も感嘆してまいます。
そういった、映画全体の音をつくるというデザインの視点から観ることができる映画ではありますが、ぼくが印象に残ったのは、そのプロセスにしばしば社会的な意味が込められているところでした。実話をもとにした『アルゴ』における群衆の音声を録音する際に、当時実際にその場所にいた人々を使用していたというエピソードや、『グローリー/明日への行進』のデモシーンにおけるリアリティのある音づくりなど、映画をつくる上での「音」が、ひとつの素材や情報だけに留まらず、それらがどういった歴史的な文脈にあり、文化的な意味が込められ、映画がもつメッセージを感情的に観客に届けるための要素としての役割を果たしているのかを知ることができます。
それは、映画制作に限らず、あらゆるデザインやものづくりの場面でも言えることだと思います。つくられるものやことを構成する要素は、たとえ同じ種類や属性であっても、それぞれがもつ背景や時間的な重みが、微細なレベルにいたるまで異なった意味を持ち、効果を発揮するということ。自分の仕事に関しても、同じ言葉だとしても、そこにどれだけの妥当性や重みを持たせるのかということを、もっと考えなくちゃいけないなと思います。「デザインはおもしろい」というシンプルな言葉に、どうやったら説得力が生まれるのかを、普段から意識しなくちゃなと。
とはいえこの映画、なんといっても『スター・ウォーズ』や『レイダース』、『ゴッドファーザー』、『地獄の黙示録』、『プライベート・ライアン』といったクラシックから『ブラック・パンサー』まで、映画史を彩るさまざまな作品をあらためて劇場の大きなスクリーンとスピーカーで感じることができるので、なんだかふたたび映画に恋に落ちたような気持ちになりました。家でのんびりNetflixを観るのもいいですけど、映画館で映画を観る特別さは、きっとこれからも変わらないのだと思います。
(堀合 俊博)
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)




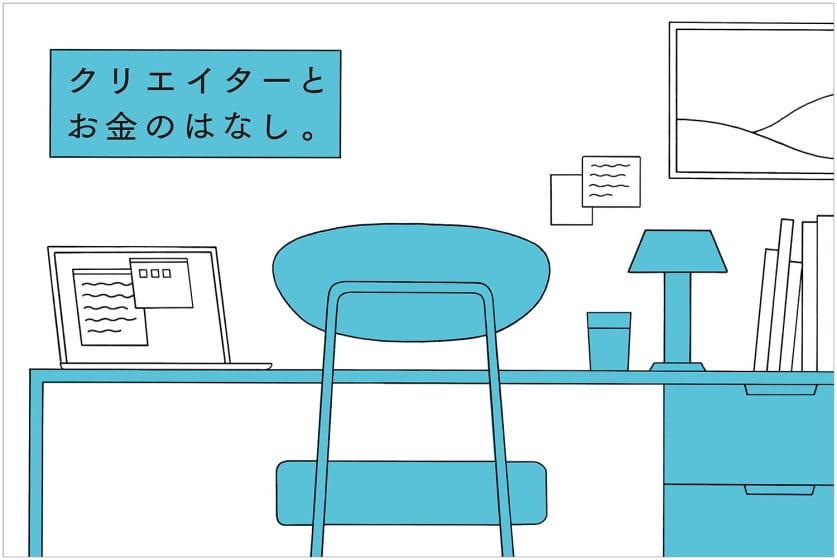







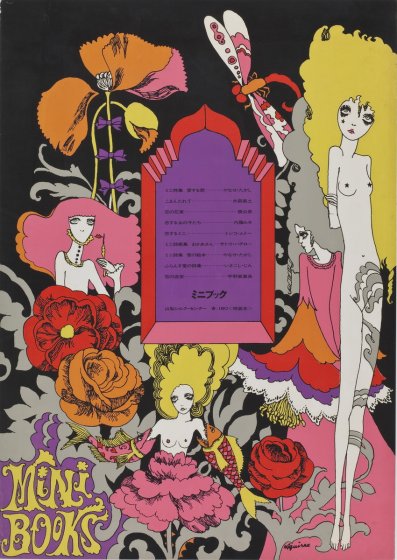
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




