作品をつくることと、他者からの評価としてのアワード
――中村さんは、学生時代などにコンペに応募した経験はありますか?
中村:学生のとき一度だけ参加したことがあります。「お台場を変える都市計画」みたいなお題で、お台場の半分を墓地にする案を3人のグループで出しました。やってみると自分たちの伝える能力のなさがわかって、挫折した記憶が残っています(笑)。
鈴木:僕は、中村さんがいま審査員として参加されている「シヤチハタ・ニュープロダクト・デザイン・コンペティション」の第2回目に応募しました。そのときはペットボトルの蓋を鉛筆削りにした作品で「一席」をいただきました。TMAでも審査員を務めていた原研哉さんと知り合うきっかけになりました。
中村:アートコンペに応募してくるのは、やはりミッドタウンという大舞台で展示したいと思っているひとなのかな?
鈴木:前提として、多くのひとに見てもらいたいと素直に思えるひとが応募すると思います。そういう気持ちのひとは、賞をもらうという喜びも自分の変化に還元しやすいので、審査員としては並走して背中を押せます。その後も予想外のチャンスを得やすいのではないでしょうか。
中村:デザインというものは基本的には他者や社会のために存在するもの、という前提があって、デザインコンペに応募してくるひとは、そこからはみ出た自意識をどう扱うのか、もやもやしているようなひとたちなんじゃないかと思うんです。アートコンペに応募してくるひとは、他者にも評価されたいという欲望とどう向き合うのか、という理由で参加してくるのかな。
鈴木:アートコンペは募集テーマがありませんが、日頃から独自の方法で向き合っている対象やテーマを、東京ミッドタウンという公共の場を媒介にして、個として世に問う機会だと思います。

僕自身を例にすると、自分が感じたことや思ったことを、他者も同じように感じているのだろうか、という「距離」を確認したい欲求が根本にあるんです。鈴木が苗字のひとが日本にたくさんいるので、子どもの頃から自分が特別だという感覚は一切なくて、「人類のうちの1人」という感じなんです。
「自分」というのは、たくさんいるみんなの中の個であって、それは「プライベートな私」だけではないなという感覚がだんだんと芽生えてきた。実はそうした変化が、作家として作品をつくる起点になっています。そこにはアートとデザインの差はない。それをどういうかたちで具現化していくのか、の違いだと思います。
中村:デザインというのは基本的には「設計」という行為を指す言葉だと捉えています。アートとデザインはそもそもレイヤーが違う概念なので、本来は普通に共存するものだと思います。アート作品の中にも「設計」はある。鈴木さんもアート作品をどう伝えるか、最終的なところはデザインされているのを感じます。
鈴木:アーティストは誰に頼まれるでもなく作品をつくりはじめることが多いと思います。社会と接点を持ちつつも外側から関わる存在だと思っています。だからこそアートコンペでは、そのひと自身の指針でつくり続けていくだろうと感じられたアーティストを推すようにしています。
アートマーケットで作品が商品になる作家はある面ではシンプルだと思います。まだ作品の価値を交換する仕組みのないアーティストにとって、アワードの役割は作品を公共の場にさらすことで、作家として生きていくためのヒントや手ごたえを提供することだと思います。メディアに出て活字になった自分の名前を見るだけでも変わることはあります。そうやって一歩ずつ変化を続けていくものなので、受賞して一気に上り詰めた気になってしまったら続かないと思います。
あと、プランニングの段階で審査員から意見が出るので普段の制作とは違って、それに応えるかたちで作品を具現化していくことも新たな挑戦ではないでしょうか。展示空間の制約の中でデザイナーに近い計画性や設計力が求められます。

デザインコンペ1次審査にて
デザインとコミュニケーションの変化と、原研哉と深澤直人の影響
——これからのアワードのあり方について、どのように考えていますか?
中村:コンペの目的が「すごいひとを発掘すること」であるなら、すでにインターネットにその役割を取って代わられていると思うんです。24時間、世界中の人々による「すごいひと選手権」のようなものがTwitter上で行われている中で、いまデザインコンペがどうあるべきかが問われていると思います。
デザインコンペは、正直“テーマ大喜利”みたいな、頭脳戦ばかりになってしまうとつまらないなと思うんです。イケてるプレゼンとセットで審査される慣例があって、そこに沿ってないと勝てないみたいな雰囲気にはどこか息苦しさを感じる……。手仕事によるかたちの美しさであったり、そういったものを評価する場所がなくなってしまうと、デザインコンペがカバーできるのはとても狭い領域になってしまいます。今後はいままでになかったテーマというよりも、造形であったり、もの自体を評価するアワードを見てみたい。

鈴木:たしかに2000年代に入ったくらいから、そういったデザインを伝えるコミュニケーションの仕方が変わってきたように感じます。別の機会にデザインコンペの審査員に関わってきた経験では、海外から届く応募作品は、製品そのものの美しさや機能に特化した提案が多く、生活の中の特別な瞬間を捉えるような詩的なものはあまり出てこないんです。
中村:現在、デザインコンペに応募されているものは、現実にあるスタンダードを踏まえた上で、「こんな俳句を書いてみました」みたいな、ちょっとした発想の転換をアピールするものが多い印象です。それは、たとえば原研哉さんが竹尾の展覧会として企画された「RE DESIGN」などの影響が大きい気がしています。写真のビジュアルや、見せ方の部分で。
鈴木:たしかにそうですよね。僕たちの年代は、深澤直人さんが手掛けられた「WITHOUT THOUGHT」の影響も多く受けてきました。21_21 DESIGN SIGHTが伝えてきたデザインの視点の成果でもあると思います。
――アートコンペについてはいかがですか?
鈴木:アートコンペはプレゼンテーションもしなければならないし、展示場所がしっかりと決まっていたり、レギュレーションが厳しい中で勝ち抜くのは、経験者でも本当に大変なことだなと思います。作品の完成度はもちろん重要視されているんですが、未完成だけどそれでも選んじゃおうと審査員が思ってしまうような、そんな異質なアプローチをする提案が入り込んでくる余地もほしいなと思います。
デザインとアートにとって、お祭りのような場所

鈴木:TMAは応募者も審査員も、それぞれの仕事の専門分野やデザインの思考を忘れて、お祭りのように集える場所ですよね。毎年新たな作品が展示されることで、おのずとひとが集まってくる。TMA自体が新陳代謝するパブリックアートとして機能する、実験的な場でもあるのかなと。
中村:このお題だったらちょっとつくりたいと思うような、なにかをつくりたいひとというのは一定数いて、そういったひとたちになにかしらのきっかけを与えるのがコンペの役割だと思います。ジョギングしたいと思っていてもしないけど、東京マラソンという目標があると出場する、みたいな。
鈴木:あと、TMAはいまの若いつくり手たちが考えていることや感じていることをパブリックアート化させることに成功しているんじゃないかと思います。審査を通して20〜30代の興味をのぞき見ることができる感覚があるというか。まだかたちにすることに追いついていないもの、見えないところでうごめいているクリエイターの存在が垣間見えるところがポイントだと思います。
東京ミッドタウン内にある安田侃さんの彫刻は、やわらかな輪郭でひとと空間を包み込み、自分の感性だけでは気づけないような、光や風、時の流れ、そこに居合わせたひとの存在へと目を向けさせてくれます。そのようないつもそこにあることで特別な瞬間を与えてくれるパブリックアートとともに、TMAは参加性を持つひらかれたパブリックアートとしてかたちを成しているように思います。アワードによって新たに関わりを持った応募者や作品が媒介となって、それまで会うはずのなかったひとが東京ミッドタウンに集まってくる。そこにアワードの可能性を感じています。

TOKYO MIDTOWN AWARD 2019
https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/
文:白坂由里 写真:葛西亜理沙 取材・編集:堀合俊博(JDN)
- 1
- 2
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)













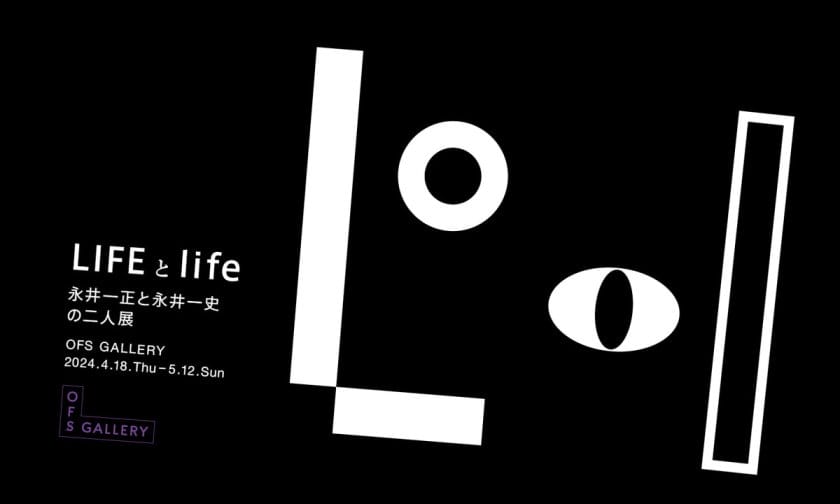

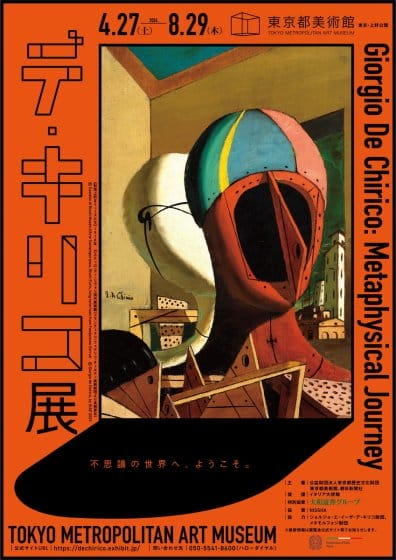
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




