「歌詞をリッチに見せる」その思想の元につくられたデザイン
-歌詞をどれだけリッチに見せるか。そこがリリックスピーカーのデザインのコンセプトとなっていますね。
斉藤:音楽は「作曲」と「作詞」の両面があります。作曲=サウンドの方は、安いスピーカーから高いスピーカー、ヘッドフォンもあって音を楽しむバリエーションに多様性がありますが、作詞=歌詞のバリエーションはあまりないんですよね。データ配信が主流になって、CDの歌詞カード自体も少なくなっている。歌詞カード以外では、ネットで検索して歌詞を読むこともできますが、もっとより一歩踏み込んだ歌詞の付き合い方があるといいなと。
例え話をすると、スピーカーによっては低域が強く出る特性を持ったものなど、製品ごとの個性があります。その一種で、スピーカーの低域が強調されるように、歌詞が前に出るのがこのスピーカーかなと。歌詞が強調されたイコライジングみたいな感じです(笑)。

-今までにない発想の製品ですが、SIXとしての初の自社プロダクトとなるリリックスピ-カーは、どういった形で企画が通ったのですか?
斉藤:SIXは、テクノロジーと表現を中心にしたクライアントのための映像や、インタラクティブなものを制作しています。僕はおもに音楽系のクライアントの映像を担当しているのですが、リリックスピーカーの開発の経緯に関してはシンプルな流れです。SIXでも自社プロダクトをつくろうという話があったので、かなりたくさんの案を出して、その中から社長と取締役が選びました。それと僕がとにかくつくりたい!と言っていたので。
-ほかにも何案か出されたんですか?
斉藤:そうですね、資料に残っているもので200点はありました(笑)。
-そんなに!その中で絞り込まれた一点だったと。実際の開発をはじめたのはいつですか?
斉藤:2013年の年末ですね。まず「歌詞にフォーカスしたスピーカー」というコンセプトは、音楽がデジタル化する時代で必須だと思ったことがスタートポイントです。「言葉が音と同じく空中に浮いている表現にしたい」という発想から、空中に描写する手法を探って。そこは時間をかけて、ホログラムやプロジェクターなどの再生装置のパターンを検討して、一番デザイン的にまとまりがよかった透過スクリーンに落ち着きました。
そこから制作を開始して、2014年に「ビックパレード」(エンタテインメント×テクノロジーをテーマに開催されたカンファレンスイベント)でプロトタイプを公開しました。2015年3月の「SXSW」(毎年3月にテキサス州で開催される、音楽祭・映画祭・インタラクティブフェスティバルなどを組み合わせた大規模イベント)での受賞をきっかけに製品を取り扱いたいという話も受け、生産に向けて準備をはじめました。生産に向けての一番大きいポイントは、デザインを重視したプロダクトなので、大量生産する上での成立の仕方でいろいろ悩むところがありました。悩みながらもなんとか解決していきましたが。
プログラミングで歌詞のモーショングラフィックを自動生成
-実際のプロダクトの制作に関してですが、dot by dot inc.と一緒に制作されたそうですね。
斉藤:最初はaircodeと一緒にアイデアを練ってプロトタイプをつくりました。その後、dot by dot inc.のテクニカルディレクターSaqooshaさんと一緒に仕上げていきました。
-モーショングラフィックは、Saqooshaさんが制作されたのですか?
斉藤:おもにSaqooshaさんとdot by dot inc.のメンバーの方々です。モーショングラフィックの元となるデザインは、takcomさんやALLd.の荻野健一さんなど、メジャーアーティストのライブ演出を手がける方々が担当していて、ある意味リッチなライブ演出をインタラクティブなホームユースのプロダクトで体験できます。歌詞の演出をプログラミングして実装するので、たくさんの方々が参加してます。

-デザイナーから預かったものをSaqooshaさんが動かすという工程ですか?
斉藤:まず、デザイナーに曲に合わせたコンセプトを考えてもらいました。例えば、おとなしい曲では風の流れるようになど演出のパターンをいくつも出します。そこから歌詞の動きを演出するサンプル動画をつくります。ここまでがデザイナーの作業です。そしてそれを参考にしながらプログラマーが実際のプログラムとしてつくります。どんな曲が来ても歌詞を雰囲気に合ったモーショングラフィックスにする仕組みです。モーションデザイナーがひとつの曲に1個ずつ動画をつくるような感覚で、その曲に対してふさわしいモーショングラフィックを自動生成するプログラムを組みました。
-デザイナー以外では、職種的にはどういった方が携わられていたのでしょうか?
斉藤:モーショングラフィックデザイナーがいて、それを実装してくれるプログラマーがディスプレイの表現の部分。文字のデータを得るために、歌詞のデータベースはシンクパワーから。曲の雰囲気を読み取るために、曲の解析をする産業技術総合研究所。それらをつなぎ込むためのサーバーをつくるのは博報堂アイ・スタジオが担当しています。
そのサーバーから来たデータと音の部分と繋げるために、本体のファームウェアを制作したQuicco Sound。元YAMAHAの人たちがつくった浜松の会社で、もともとは楽器をつくってます。そこから実際に音が鳴るスピーカーの部分では、ヨーロッパで活躍していたサウンドエンジニアの大崎博文さんが音響設計。筐体全体のデザインはmonomのプロダクトデザイナー小野直紀くんなど、いろいろな方たちが関わっています。
-かなり大勢の方が参加されているんですね。そんななかで、斉藤さんは全体的なディレクションやコンセプトが揺らがないように調整をされていたのですか?
斉藤:統括自体、僕ひとりでやっているわけではないんですが、皆で連絡を取り合って形になりました(笑)。コンセプトのなかで、たくさんのメンバーに制作を楽しんでもらいつつ、そのセッションがいい感じで盛り上がっていくように調整しました。

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)














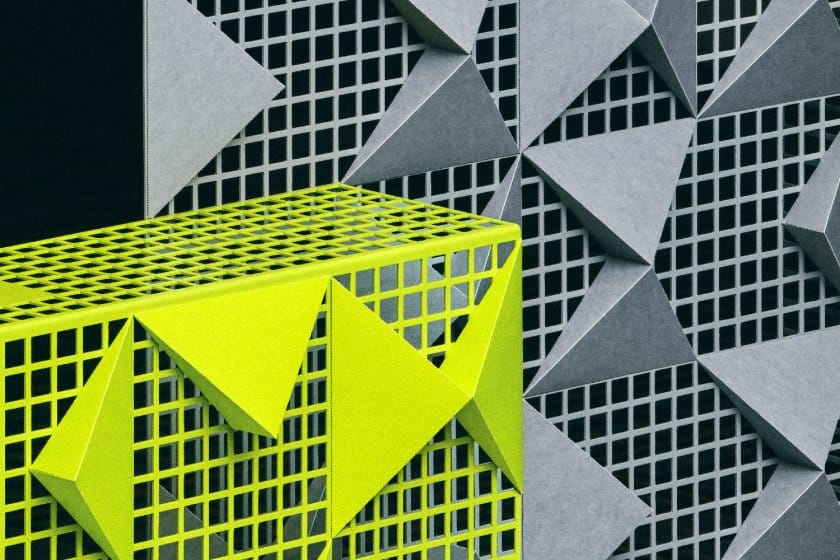

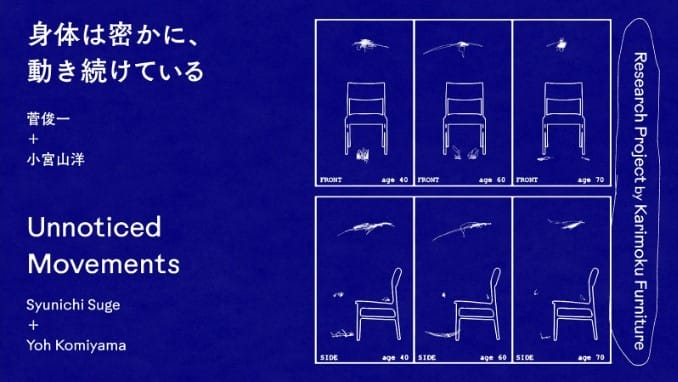
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




