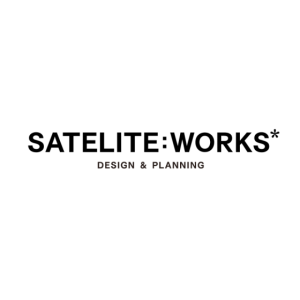“敷居を越える一週間”をテーマにした「Design Week Kyoto ゐゑ(いえ)」は、京都市内のさまざまな工房やオフィスが開放されるイベントです。普段入れない「クリエイティブの現場」でクリエイターと会話したりワークショップに参加することで、あたらしい京都の一面を知ることができます。第一回目となる今回は、2016年2月21日~28日の期間で開催されました。
好きな神社がいくつもあり、京都には毎年訪れているのですが、これまで「ものづくり」という視点で京都を見たことはありませんでした。今回、「京都でデザインウィーク? しかも記念すべき第1回目」ということで、1泊2日で取材に行ってきました!

参加店舗やオフィスは約140組と多く、全部は見切れませんでしたが、2月21日~22日に参加したものにしぼってレポートします。
・オープニングイベント
・NOSIGNER京都オフィス 展示&オープンオフィス
・KYOTO ART HOSTEL kumagusuku
・中村ローソク
・つづれ織工房 おりこと
・修美社
つづれ織工房 おりこと
日時:2016年2月21日、26日
会場:つづれ織工房 おりこと(京都市上京区寺之内通堀川西入東西町377)
つづれ織は、西陣織の中で最も歴史があり、爪で織る芸術品と呼ばれています。特徴は多彩な単色糸を使用することに加え、それだけでは表現できない微妙な色合いも作り上げるところ。グラデーションを表現する技術を駆使することで、作品に立体感と臨場感をあらわします。
上京区の「つづれ織工房 おりこと」では、織っている現場を見学できるオープンスタジオを実施していました。着物で見学に来ている方や子どもが、興味津々で織り子さんの織る様子に見入っていました。


昔ながらの木製の機織り機で制作する、森紗恵子さん
かんたんに織り方を説明すると、図案に合わせて糸で柄をつくっていくというイメージです。縦糸が張られているところに横糸を通し、クシのような道具で手元に糸を詰める。それを繰り返し行うことでだんだん織られた糸の幅が大きくなり、糸の色を換えて作業をすれば色とりどりの模様ができあがっていきます。

織り子の森紗恵子さんに、今回「Design Week Kyoto ゐゑ 2016」に参加した感想についてお聞きしました。
「近い地域の方と連携を組めたことが良かったなと思います。別の織物屋さんが参加者の方にうちの工房をおすすめしてくださったり、一緒にスタンプラリーの場所として組むことになったり。また、来てくださった方と直接お話できたこともすごく嬉しかったですね。ビジネスにすぐつながるというのは難しいかもしれませんが、来てくださった方につづれ織とはどんな織り方なのか?どうやって織っていくのか?ということを知っていただけたのは本当によかったと思っています。」
また、工房ではつづれ織体験もおこなっていました。

体験版のつづれ織り。森さんのものにくらべるとガタガタなのがわかる
「小さなお子様から海外の方まで、幅広い方に体験していただきました。難しいという方もいれば、やりはじめたらとまらない!ハマる!という方もいました。今回、つづれ織を知ってほしいという思いで参加したことからすれば、本当にありがたいことです。」

使用していた道具。手前のクシのようなものは、横糸を通したあとに糸を手元に詰めていくときに使うもの
今回、一番驚いたことは、森さん自身の爪までも道具になっていたことです。やすりで定期的に細かな溝を作り、細かい箇所は爪で作業していると話してくれました。

のこぎりの刃のような細かい溝が彫られていました
つづれ織ではおもに帯を織ることが多いそうですが、「つづれ織工房 おりこと」さんでは、伝統の技法を使ってブローチやカフスボタンなどのアクセサリーもつくっているそうです。もっと多くの方に気軽なかたちでつづれ織を知ってもらいたいという気持ちからはじめたと言います。

手織りならではの風合いの、着物の帯結びをイメージして作られたバレッタ
織っていて一番難しいことを森さんに伺うと、無地を織ることだと答えてくれました。同じ力、角度で織らないといけないので、かなり経験が必要になってくるそうです。自身のことをまだまだです、と話していた森さんですが、流れるように自然に織っている姿からは、脈々と継がれてきた工芸の力強さを感じました。
石田織座(JDN編集部)
つづれ織工房 おりこと
http://www.oricoto.com/
▼そのほかのイベント
・オープニングイベント
・NOSIGNER京都オフィス 展示&オープンオフィス
・KYOTO ART HOSTEL kumagusuku
・中村ローソク
・修美社
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)



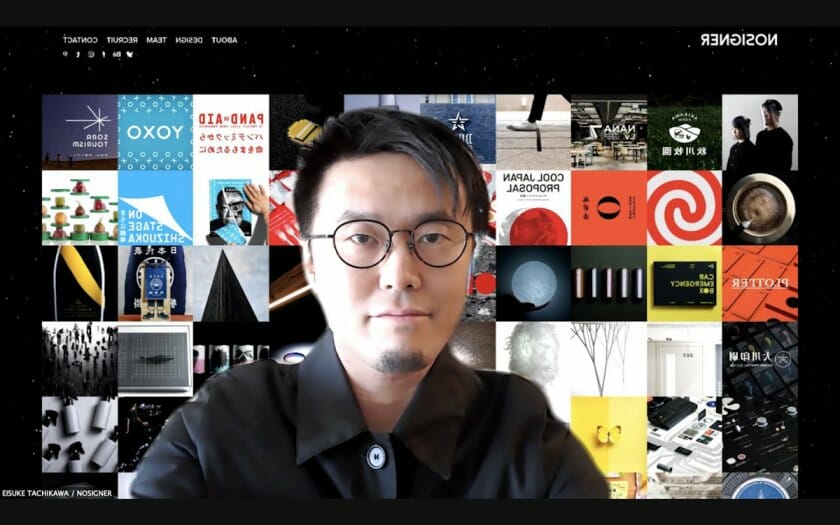




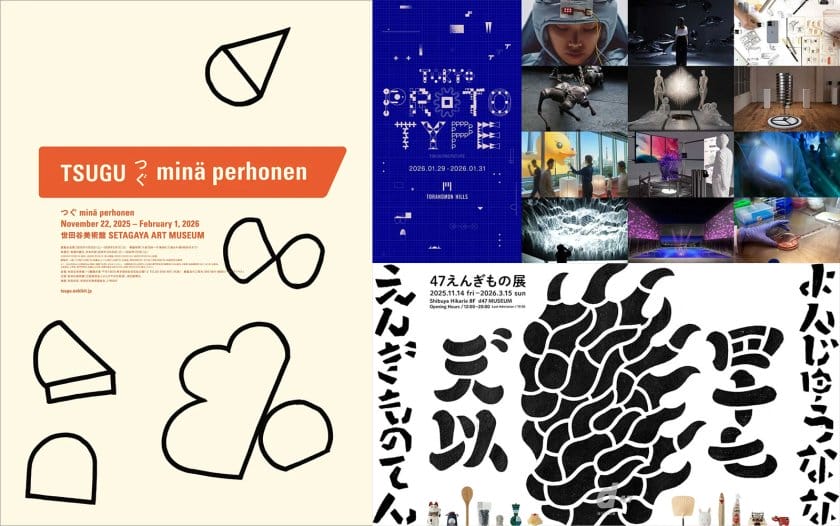








![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)