チームビルドで目指すべき方向性を明確に
――アカツキはさまざまな職種の方々が集まっている組織だと思いますが、チームづくりで意識していることはありますか?
村上:振り返りの部分はもちろんですが、アカツキはトップダウンではなく、めちゃくちゃフラットな組織です。何かを決めるために承認をとって会議の場を設けることもありませんので、現場の若手も中堅も、つくるなかで疑問に感じたことはその場でストレートにぶつけ合っています。基本的にはデザイン・企画・エンジニアの三位一体で1つのプロジェクトが進行しますが、それぞれの職種に対して忌憚のない突っ込みや意見が入ります。だからこそ客観的に物事が見えてくるし、ユーザーに届くものができていくのだと思います。
また、各トレーナーが定期的に「1on1」の場をつくって、一人ひとりが何をモチベーションにしているか、どうすれば前を向いて一緒に走れるかなどをヒアリングして意思の疎通を図ることもあります。自分で手を動かす段階って「点」になりがちですが、1つのストーリーの中で自分がどんな役割をしているのかをイメージした上で走れるようにすることは意識しています。
カサハラ:メンバーが大体同じ方向を向いて走れるように、ビジョンを見える形にしたり、そのビジョンの自分事化や、他メンバーとの認識合わせのためにオフサイトミーティングをしたりといったチームビルドの活動を行っています。どこを目指しているかの共通認識があることで、目標設定や振り返りをする際の指標となり、メンバーの意識がブレなくなりチームの一体感が増します。

村上:チームビルドで目指しているのは「集団」ではなく「チーム」をつくることです。単なる大人数の集まりは「集団」ですが、同じ想いを共有しているからこそ「チーム」になる。そこをどうつくっていくかですね。
――いい意味でのライバル意識のようなものはあるのでしょうか?
山田:ライバル意識というか、別のチームのやり方がいいなと思ったら見学に行って真似するというのはけっこうやっています。
カサハラ:確かにいい結果を共有するカルチャーがあるので、ほかのチームの見学にはよく行きます。いろんなやり方を見て、かつ自分たちでカスタマイズしてやってみて、それをまた元のチームが見て改良するといったように「改良し合い合戦」みたいなところはありますね(笑)。
外部と連携することでより良い作品をつくる
――制作はすべて社内で行うのですか? 外部との連携も?
村上:社内のメンバーの強みはもちろん活かしますが、それだけで考えると可能性が狭まることもあるので、例えばイラストの制作を依頼するなど外部の力を借りるケースはあります。特定の分野に強い人や企業にいかにアンテナを張って巻き込めるかは重要なポイントですし、「この人(企業)と組んだら世界観がさらに良くなる」という魅力的なパートナーを探してくることもチームづくりの一つと考えています。
ゲーム事業だとイラスト、アニメーション、エフェクト、サウンドなんかも外部に依頼することがあります。あるいは新規事業で映像をつくることがあれば、映像制作会社と組んで制作を行うこともあります。
ただ、やっぱり自分の手を動かしてつくりたくなるんですよね。でもアカツキが本当に伝えたいことのためには何が最適か。それを常に考えながらバランスをとってやっています。
ゲームの可能性はまだまだ広げていける
――1つのプロダクトが完成したら、どのように世の中に広めていくのですか?
小畑:ゲームの場合はマーケティングチームと一緒に展開を考えます。プロダクトの世界観や機能を深く理解してもらった上で、プロモーション担当者が、例えばTwitterなのか動画なのか、こういう施策でいきましょうと提案してくれるのですが、僕たちが一方的に素材を渡してお任せではなく、双方が意見を出し合いながら宣伝を打つタイミングなども決めていきます。プロモーション側の施策にゲーム制作の現場メンバーが意見することもありますし、その逆も然りですね。
まだゲームをやったことがない人にはどうすれば響くかということも考えなければならない部分で、その辺りの層を巻き込むことはなかなか難しいのですが、言い換えればゲームの可能性をまだまだ広げていけるチャンスだとも捉えています。

村上:その辺の可能性はブランドとしても今後向上させたい部分です。ゲームもサービスも入り口は違いますし、ターゲットが重なる場合、重ならない場合など色々あると思いますが、「アカツキがつくったものならおもしろそう!」と思ってもらえたうえでそれぞれの入り口から、さらに他のサービスへの興味関心も持ってもらえることを目指したい。そういうワクワクする体験を、各プロジェクトがユーザーに届けられるようになればいいですね。
それには、いま目の前にいるユーザーとのコミュニケーションがとても大事で、アカツキが出したサービスを試していただいたユーザーの方から、作品の魅力がどんどん伝染していけばいいなと思っています。
――プロダクトの性質上、ユーザーの声はダイレクトに届きますよね?
村上:はい。サービスへの評価やコメントなどで直接的に見れるものも多いですし、SNSなどで反応が届くこともあります。厳しい意見をいただいた時には、きちんとフィードバックして次に活かします。
アカツキとしての世界観を届けるために僕らの中でブレてはいけない部分もありますが、最終的に楽しむのはユーザーのみなさんです。そこが楽しめないと意味がないですよね。だからユーザーの方々からの声は、僕らへの影響は大きいです。
――最後にカサハラさん・小畑さん・山田さんが感じる、アカツキでのお仕事の醍醐味を教えてください。
カサハラ:アカツキが掲げている理念の一つが「成長とつながり」です。そこに対して会社が本気で取り組んでいて、お互いの成長のためにしっかり向き合う時間が定期的に設けられています。自分が伸び悩んだ時に、ほかのメンバーが一緒に試行錯誤して成長を促し合うって、なかなか難しいことだと思うのですが、それができているのもアカツキの魅力の一つだと思います。
小畑:社内でのコミュニケーションが活発な分、みんなが楽しみながらポジティブに仕事をしている印象です。あとは、やはりクリエイターなのでよりかっこいいもの、よりワクワクするものを届けたいと常に考えているのですが、何か提案した時に意見が通りやすいところも魅力です。ビジネスライクに寄り過ぎていないところがクリエイターにはとてもいい環境だと思いますよ。
山田:経営陣を筆頭に、現場メンバーも含め未来をつくっていく社風の中で、自分自身も成長しながら参加できるとこにやりがいを感じています。時には職種の垣根を超えて協力し合い、チームで試行錯誤した取り組みが、ユーザーのみなさんの喜びの声につながったときは特に大きな喜びを感じます。
“中の人”に聞く、一問一答
<株式会社アカツキ デザイナー 小畑公良さん>
このコーナーでは他業界からコンバートし、アカツキにジョインして活躍する“中の人”にお話をうかがいます!

Q.モバイルゲーム業界へコンバートしたきっかけは?
僕は前々職でモバイルゲームの業界に入りました。その前はイベント制作会社やテレビ局の制作会社、広告会社などいくつかの職種を経験した中で、自分のアイデアで勝負したい気持ちがずっとあったんです。ちょうど前々職への転職を考えていたタイミングで、その会社がコンバートありきでブラウザゲームのWebデザイナーを募集していたので、ゲームデザインでゼロから作品をつくるのもおもしろいかもしれないと考え、コンバートしました。
Q.ゲーム業界以外での経験が活きていると感じる部分は?
世界観やビジュアルを含めて何をどう伝えるかは、ゲームであろうとテレビや広告であろうと同じですよね。より世界観に合わせたものづくりをするという意味での見せ方、考え方を必要とされる部分では、前職の経験が活きましたし苦労しませんでした。
Q.小畑さんの特技はダンスだそうですが。
高校生の時に、「かっこいいな」「モテたいな」という理由でブレイクダンスをはじめて以来、B-BOYがライフスタイル化してダンスの世界にどっぷり浸かりました。新卒で入った「東京BBOYS」というイベント制作会社では、ヒップホップミュージシャンのCRAZY-Aが主催してきたヒップホップイベント「B BOY PARK」のアシストをしていました。今は趣味ではありますが、「HIPHOP戦隊B-BOYGER」というチームで、踊りながらB-BOYのかっこよさを世の中にアピールし続けています。
Q.HIPHOPの魅力はどんなところにありますか?
HIPHOPの文化って、いい曲だったりいいフレーズなんかを取り入れたりしてそれをさらにアレンジして1つの世界観をつくり出すことがおもしろいと思うのですが、そう考えるとデザイナーの仕事もある意味HIPHOPに近いと思うんです。ゆくゆくはアカツキでブレイクダンスのコンテンツを配信して、世界中の子どもたちをB-BOY化するのが夢です(笑)。ダンスって世界共通じゃないですか!

取材・文:開洋美 撮影:葛西亜理沙
株式会社アカツキ
https://aktsk.jp/
- 1
- 2
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

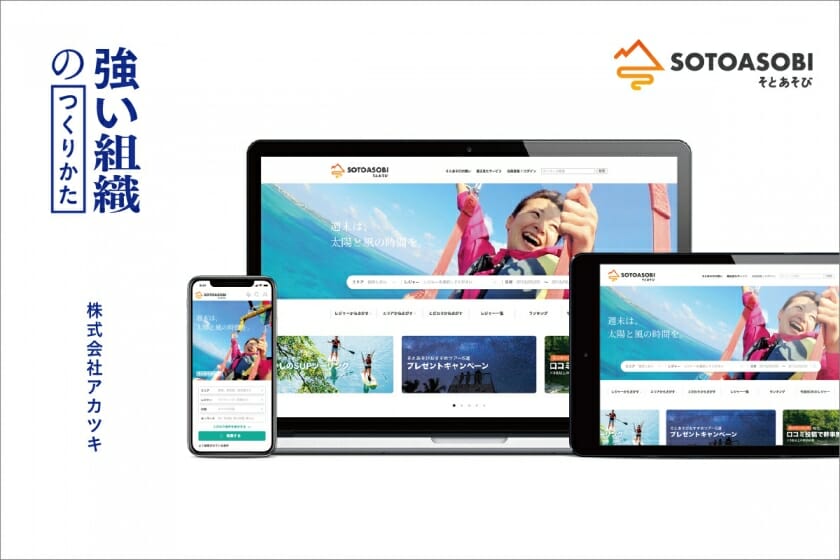














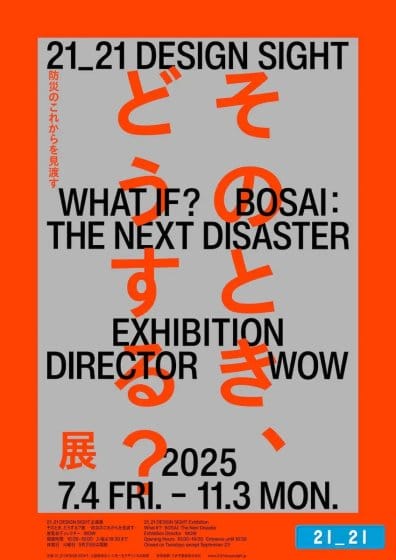
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




