JDN編集部の「そういえば、」2020年1月

ニュースのネタを探したり、取材に向けた打ち合わせ、企画会議など、編集部では日々いろいろな話をしていますが、なんてことない雑談やこれといって落としどころのない話というのが案外盛り上がるし、あとあとなにかの役に立ったりするんじゃないかなあと思うんです。
どうしても言いたいわけではなく、特別伝えたいわけでもない。そんな、余談以上コンテンツ未満な読み物としてお届けする、JDN編集部の「そういえば、」。デザインに関係ある話、あんまりない話、ひっくるめてどうぞ。
JDN編集部に届いた、ユニークな年賀状3選
■フロッピーの年賀状
グラフィックデザイナーの小玉文さん(BULLET Inc.)から送られてきた年賀状は、なんと穴だらけのフロッピーディスク!毎年小玉さんの紙を使った年賀状は凝っていてとても楽しみにしているのですが、「今年は紙じゃない…!?」と届いた時は思いました。

チーズは2種類。左はチェダーチーズ、右はスライスチーズのような色合いをしています。ちなみにフロッピーを裏返すと「Blanks for thought」という文字がペンで描かれています。

梱包方法はシンプルで、フロッピーは段ボールの台紙にビニール素材で巻き付けられていました。
しかし、手に取ってみるとフロッピーは紙でつくられており(手に取るまで見た目の質感はフロッピーそっくり)、金属部分も紙。挿入方向を示す矢印や、凹みの段差具合も本物そっくりでただただ驚きでした。以下、小玉さんのFacebookに掲載されていた、コンセプトや製作プロセスに関するコメントを抜粋してご紹介します。
「BULLET Inc. 2020 子年の年賀状は穴だらけのフロッピーディスク。令和の新春から平成ノスタルジーに浸ることができる一品です。黄色いフロッピーは[GAボード]、白いフロッピーは[OK ACカード]という紙をそれぞれ6枚貼合して作成しています。型抜きの圧力により、紙の断面が押し込まれ、柔らかく歪んでチーズのように美味しそうに仕上がりました。このフロッピーは穴だらけでデータを記録することもできずまったく役に立たない物体ですが、なにか、「面白い」。無用の長物を、労力をかけて制作する。そこには、大切な何かがあるような気がしています(小玉文さんFacebookより)」。
見て驚き、手に取って驚きの、ひと際ユニークな1通でした。
■カットチーズの年賀状
Webデザインを中心に手がけるスタジオディテイルズから送られてきたのは、カットスポンジでチーズを表現した年賀状です。子年ということもあってチーズに関連した年賀状は多かったのですが、送られてきた中ではいちばん立体感もあり大胆で目立っていました。

スタジオディテイルズの年賀状

原材料名には「掃除用スポンジ」と書いてあるのも面白い
コンセプトは、年賀状をもらった人にとって磨きある1年を願う、というものだそうです。実際に使える年賀状というのはなかなかないですし、プロダクトとしての可愛らしさもたっぷりの1通でした。
■「1枚の紙から生まれる可能性」を追求した年賀状
印刷から加工まで一貫して製造する福永紙工から送られてきたのは、ネズミのしっぽが小窓からちょろんと見えている年賀状です。段ボール紙でできた封筒を開け、きれいに折られた1枚の紙を広げると年始にふさわしい「福」の一文字が。

福永紙工の2020年 年賀状

よく見ると福の文字はパーツごとにそれぞれ「ネ」「ズ」「ミ」とも読め、ネズミの毛の感じをイメージさせるフサフサ感があります。以下、福永紙工のサイトに掲載されていたコンセプトを抜粋してご紹介。
「2020年の年賀状は『A Cat In Gloves Catches No Mice』(=手袋をつけた猫は、ネズミを捕まえることができない)というネズミにまつわることわざを、シンプルに紙で表現しました。手袋を脱ぎ、時に大胆に。これからも福永紙工は『1枚の紙から生まれる可能性』を広げていきます」。
以上、編集部に届いたユニークな年賀状3選をご紹介しました。また不定期に印刷物をご紹介していきたいと思いますので、お楽しみに!
(石田 織座)
デザインとは“こさえる”こと 映画『つつんで、ひらいて』
そういえば、先日装丁家の菊地信義さんのドキュメンタリー映画『つつんで、ひらいて』をシアター・イメージフォーラムに観に行きました。
装丁家の仕事場に密着するドキュメンタリーとしての見どころはもちろんですが、映画を通して「デザインってなんだろうな」と考えてしまうような、印象的なことばに溢れた映画だと感じました。
映画では、菊地さんがモーリス・ブランショの『終わりなき対話』の装丁を手がける過程を追っていきます。ブランショの『文学空間』が装丁家を目指すきっかけになったという菊地さんが、ひとつの大仕事に臨む様子をカメラはとらえていきますが、テキストが表しているものと、その背景にあるものにじっくり向き合い、徹底的に文字や色、紙の選定をおこなう菊地さんの姿が印象に残ります。
本というメディアがもつ、作者名、タイトル、本文、帯といった情報が、読むひとにとってどのような意味をもたらすのか。そのことにとことん寄り添ってデザインすることこそ、装丁やエディトリアルデザインの醍醐味なのだなと感じ入ってしまいました。
「人文書の装丁をやり続けていると、中身がからっぽになってしまったような感覚がある」と、映画の中で菊地さんは語りますが、それは「人間とはなにか」について書かれたテキストに、真摯に向き合い続けてデザインしてきたというなによりの証拠なのだと思います。「デザインとは“こさえる”こと」と語る場面もとても印象的です。
映画のラスト、受注仕事のやりがいについて監督の広瀬奈々子さんが尋ねると、「そもそも人生とはそういうものだ」と菊地さんは答えます。他者である誰かのためになにかを“こさえる”こと、それはデザイナーに限らず、あらゆる仕事、ひいては生きることそのものであるということ。観終わってから、さまざまなことに頭を巡らせてしまいました。
(堀合俊博)
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)





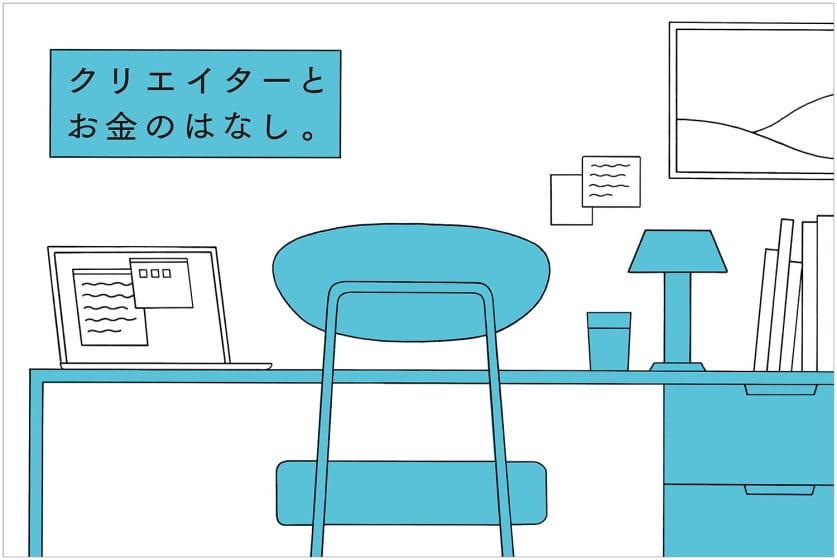







![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




