編集部の「そういえば、」2021年11月

ニュースのネタを探したり、取材に向けた打ち合わせ、企画会議など、編集部では日々いろいろな話をしていますが、なんてことない雑談やこれといって落としどころのない話というのが案外盛り上がるし、あとあとなにかの役に立ったりするんじゃないかなあと思うんです。
どうしても言いたいわけではなく、特別伝えたいわけでもない。そんな、余談以上コンテンツ未満な読み物としてお届けする、JDN編集部の「そういえば、」。デザインに関係ある話、あんまりない話、ひっくるめてどうぞ。
“未来の死”を問う展覧会
そういえば、もう会期は終了してしまったのですが、読者のみなさんにも共有したいと感じた展示をご紹介させてください。
東京・六本木のANB Tokyoにて、11月3日から11月14日まで開催された「END展 死×テクノロジー×未来=?」は、「死」をテーマとしたさまざまな問いを来場者に投げかけるという展覧会でした。主催は、多様な領域の研究者やエンジニア、企業、クリエイターなど異分野の人々を交えて活発な議論の場を創出するプロジェクト「HITE-Media」です。

会場の最初に来場者を迎えるのは、漫画家・諸星大二郎さんの「すべてここから生まれ ここへ還って行く」©Daijiro Morohoshi 2021
会場には一人ひとりが「死」の物語と向き合うヒントとして、描き下ろしの短編マンガやHITE-Mediaが選び抜いたマンガ作品の1コマ、気鋭のアーティストたちの作品が展示されており、「死」を切り口に、これからのテクノロジーがもたらす社会の変化と人間の関係を、参加者とともに考える場を創出するものでした。

会期前に行われたアンケートに沿って展示が行われていました
会場は、「魂のゆくえ」「死とテクノロジーのはざま」「生きる/自然と信仰」と大きく3つに分けて構成。
事前に行われたアンケート結果に合わせてマンガの1コマが展示されたり、「誰かの死に関して、今でも覚えている印象的な夢や出来事を教えてください」という質問に回答された、たくさんの答えがタワーのように積まれていました。どの回答も人それぞれの経験からの率直な言葉で、思わず長く見入ってしまう人が多かったように感じます。また、気鋭のアーティストによる作品も並びました。

「誰かの死に関して、今でも覚えている印象的な夢や出来事を教えてください」という質問に対して回答された答えが、タワーのように積まれていました。

(左)たかくらかずきさんによる作品「hardwere tomb “FPS”」(右)ノガミカツキさんによる作品「Image Cemetery」
「死後に何かを持っていけるとしたら、何を選びますか?」「生まれ変わりたいですか?」といった質問から、「あなたの死後、SNSのデータはすべて残してほしいですか?」「AIによって自分の将来を予測したり、生き方を示してほしいと思いますか?」といった、展示のテーマである”未来の死”について考えさせられる問いも多くありました。「亡くなった家族とVRで再会できるとしたら?」という問いでは、2016年に幼くして病気で亡くなった娘をCGで再現し、VR上で再会する母親を追ったドキュメンタリー番組『Meeting You』(2020年に韓国MBCにて放送)が紹介されたりと、実際にすでに行われた行動に対して自分はどう思うかといった問いにも晒されました。
年齢を問わず訪れた一人ひとりが、「死」に関して他者の言葉や作品などから考えを知ることができる内容で、たくさんの方の意見をそばで聞いたような、いい意味でもやもやしたりぐるぐると考えを巡らすことができる展覧会でした。

(石田 織座)
「誰がつくったのか」を知っていることの正義ー『ビリオンダラー・コード』
そういえば、Netflixで配信中のリミテッドシリーズ『ビリオンダラー・コード』をこの前観ました。Googleを相手取った実際の訴訟をもとに、4話からなるドラマシリーズとして構成された作品です。
1994年、ベルリンの壁崩壊からまだ間もないドイツにて、ニール・スティーブンソンのSF小説『スノウ・クラッシュ』に憧れた芸術家/ハッカーの若者たちが、コンピュータ上の3Dグラフィックで地球を再現し、ユーザーの操作によって地球上のどこへでも飛んでいけるソフトウェアを開発しました。「テラ・ヴィジョン」と名付けられたその作品は、京都で行われた国際的なカンファレンスで披露され、瞬く間に若者たちは時代の寵児となりました。
本作では、テラ・ヴィジョン開発までのプロセスと、そこから約20年後の2010年代、もはや若者ではなくなった元ハッカーたちとGoogleとの法廷での争いというふたつの軸でものがたりが描かれていきます。
訴訟内容は、Google Earthはテラ・ヴィジョンのアイデアを盗用しているのではないかというもので、テラ・ヴィジョンのシステムで使用されているアルゴリズムが、Google側に知られてしまう具体的な過程と直接的な原因である人物が描かれます。ものがたりはフィクション性とともに脚色されてはいますが、そこには確かな裏切りと、不正義が働いていることを観客は目にすることになります。
法廷のシーンでとても興味深かったのは、裁判員に対して、どこまでが盗用にあたるのかを説明するプロセスでした。まずはGoogleのビジネスの仕組み、マネタイズの方法を知る必要があれば、コードやアルゴリズムの存在を説明しなくてはならない。ドラマとしてある程度Google側を敵役として脚色している部分があるにはありますが、主人公側の弁護士チームは、テラ・ヴィジョンのオリジナリティがどのように侵害されたのかを証明する上での苦戦を強いられてしまいます。
このシリーズを観ながら、グラフィックデザイナーの鈴木一誌さんが朝日新聞を相手取って訴訟を起こした「知恵蔵裁判」のことが連想されました。そこでも行われたのはデザインの言語化であり、具体的にどのようにデザインという行為が行われ、デザイナーの存在というものはどういうものなのかを、デザイン/デザイナーについて知らない人に対してわかってもらわなくてはいけないということで、テラ・ヴィジョンの裁判と同様に、その困難さというものは法廷という場で浮き彫りにされてしまいます。
なにも知らずに本作をご覧になりたい人にとっては、ここからはスポイラーになってしまいますが、現実と同様、シリーズのラストでGoogleは勝訴し、ハッカーたちには敗訴という現実が突きつけられます。
本ドラマで感じるのは、その存在を疑わないほど当たり前になってしまったツールは、顔の見えないつくり手たちの営為によって生み出されているという紛れもない事実であり、もしかしたら「誰がつくったのか」という正義は、このシステム化してしまった社会において、存在したことすらなかったことにされてしまうのではないかという恐怖でした。
敗訴が決まったラストシーン、ハッカーたちの「誰も知らないんだな」という自嘲的な言葉に対して、弁護士は「私は知っている」と返します。思わず胸がつまるような気持ちになる結末なのですが、できることなら「私は知っている」と言える側でいたいと思ってしまう作品でした。
(堀合 俊博)
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)




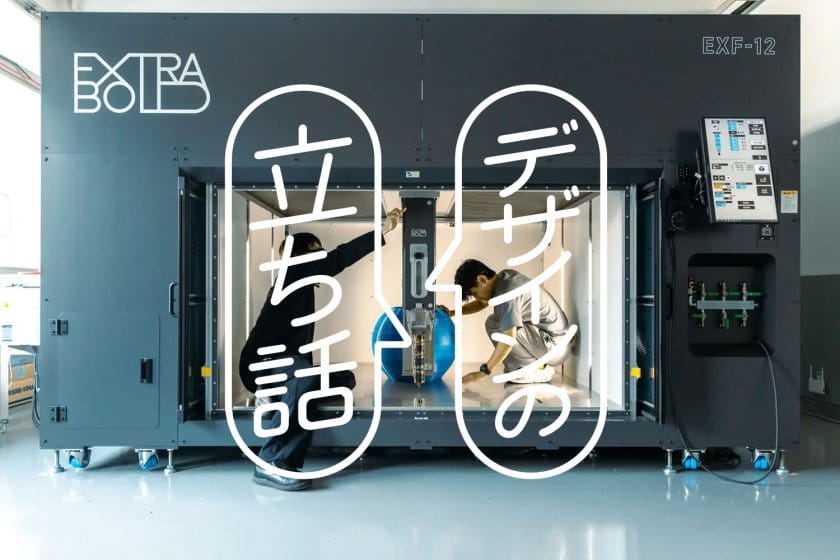








![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




