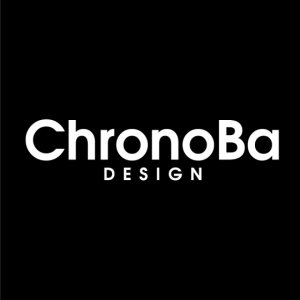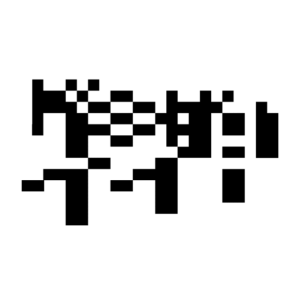幸福の解体新書『vs多様性/多様という名の一様』

読者のみなさんごきげんよう。ランニングホームラン株式会社 CCO(Chief Concept Officer)のさわくんです。このコラムでは、巷にあふれている幸福にまつわる言葉と格闘し、その本質を疑っていく。それにより、幸福のクオリアに対する解像度を上げ、ひいては本質的なクリエイティブを生み出す力を高めることを目的としている。
本日はVS「多様性」。現代の大前提となり、もはや誰も触れないこの概念をぶった斬ってみようと思う。
「多様性に配慮する」ことは世界の前提にすらなったように思う。前提になりすぎて、一周回ってそうした文言を見なくなってきたくらいには浸透した概念だといえる。こと広告業界においても、「この広告は多様性に即しているか否か」は前提の基準になってきている。
思想信条の自由はこの世界で保証されている大前提のはず。しかし、「多様性を私は重んじない」と公で言おうものなら、それこそもはや人ではないような扱いを受け、「多様性」の輪から外されることは自明だ。
それくらい、現代において神聖視され触れることさえ恐れ多い概念となっている。本コラムにおいても取り扱うのは恐れ多い。この「多様性」にあえて触れ、解体していこうと思う。
「多様性」を重んじる際、「多様性」を打ち出すことによって生じる罠が一つ存在する。「多様性」の解体において切り口となるのが、この罠についての問題である。結論から述べるならば、「多様性を打ち出すと、多様性という言葉に惹かれる人にしか届かず、結果的に多様ではなくなる」という矛盾がそこにはある。

「多様性」という言葉のクオリアは一様的である
多様性と聞いた時にあなたは何をイメージするだろうか。例えば、それは地球であったり、人が輪になって手を繋いでいる絵だったり、その人種や性別ができる限りバラバラであったり……あるいはカラフルな色のクレヨンを想起することもできるだろう。
ただ、これ以上にイメージできることはあるだろうか。私の発想が貧困なせいかもしれないが、どうにもイメージが出てこない。
ただ、一般的な「多様性のクオリア」を度外視すれば色々と思いつくはずなのだ。
例えば、アンミカさんの発言として有名な「白って200色あんねん」という言葉。
そう、別にカラフルなクレヨンを並べ立てずとも、白だけで多様性は表現できる。
逆にいうならば、カラフルな色を並べる時、そこには「白の200色」という細やかな多様性は見えなくなっている。
一様的に見えるものも実は多様で、多様に見えるものが逆に一様的だったりするわけだ。
「多様性」という言葉を使うことによって、むしろ「多様ではなくなる」。そんな矛盾が起こっていやしないだろうか。
「多様性」は多様なメッセージを発しない
僕の経験から具体的な事例を提示しておこう。この前、僕はとあるイベントの運営に参加していた。僕が入る前、その運営組織では「みんなウェルカム」「誰でもおいで」といったような発信を中心にメンバー募集をおこなっていたのである。結果、多様な人が来たかというとその逆、似た考えや技能を持った人々がそこに集まり、とても同質的な組織が出来上がっていた。
ということもあり、僕が入ってからその組織の目指す在り方を言語化し、その本質に沿った絞った言葉で募集をしたところ、以前であれば関わるはずもなかった多種多様な人々が組織に集まるようになった。
どうして、このようなことが起こるのか。
それは、「多様性」というワードは全ての人(つまり、本当の意味で多様な人)に刺さるメッセージを発してないから。
いたってシンプルな理由である。前節でも述べたように、「多様性」のクオリアは決して多様ではない。故に、そのクオリアから想起されるイメージにニーズを持つ人たちも限られている。
「多様性」や「みんな」「誰でも」という言葉に参加動機が生じるとするならば、それは「私でも受け入れてくれそう」という安心に対するニーズや、「スキルがなくても大丈夫そう」という居場所感に対するニーズを持つ場合である。
逆に、「より面白いものを」「自分の力を最大限発揮したい」というニーズを持つ人たちからは、「足並み揃えないといけないのかな」「全員の意見を取り扱うから中庸的になりそう」と弾かれている可能性すらある。
だからこそ、本当に「多様」を実現したいのならば、「多様」と発信して終わってはいけない。「いかに多様が実現されるのか」を考え、メッセージングをしなくてはならない。

世界は多様であると信じられるか
「多様性」は多様ではないし、あらゆる集合も決して多様ではない。地球単位で見れば全てを内包することはできるかもしれない。しかし、あなたが形成する集合体が地球規模でないならば、必ず何かがこぼれ落ちている。仮に全ての色をカラフルに取り揃えたとしても、すべてのカラーを200色レベルでそろえられているかといえばそうではないだろう。
逆に、それでも無理やり「多様」であることを実現しようとすれば、むしろ誰かの色を奪うなんてことさえ起こるかもしれない。
「多様性」を目指し、すべて内包することを試みて、結果的に強烈な排除を生む環境をつくってしまうこともある。
それは、自分ですべての「多様性」を担おうとしているからかもしれない。キャパシティ的に全てを内包できないのだけれど、「多様性」という言葉に執着し、無理してまで全てを背負い込もうとして破綻している——と、私は主張する。
ではなぜ、すべてを抱えるような状態に陥ってしまうのか。それは無意識のうちに「世界全体の多様性」への「不信」を抱え込んでいるからだ。最終的に世界全体が多様であれば良いのであって、あなたがそのすべてを実現させる必要はない。
私には“私が抱えられる多様性”があり、あなたには“あなたが抱えられる多様性”がある。それが世界中あらゆるところで発生して初めて、世界は多様になる。
それでも、あなたが「あなたにとって抱えられる、いや、抱えたい範疇の多様性」を言明せず、すべてを背負いこもうとするのは、世界や他者に対する「不信」が生じているとしか言いようがない。
仮にそうだとすれば、その時点で「多様性」を受け入れきれていないという他ないだろう。
処方箋:自分が抱える多様性を言明し、世界=あなたを信じよ
これまでの話を通じて、「多様性」を掲げれば掲げるだけ逆に「一様的」になるという問題について指摘してきた。「すべて」を内包しようとあらゆる概念を含めていった結果、すべての「多様性」が一様的なメッセージになり、そのメッセージングに集う人々も一様的になっていく。では、どうすれば「多様性」を本当の意味で大事にすることができるのか。
私からの処方箋としては、
「『自分にとっての多様性』をしっかりと言明し、その言明から漏れてしまう『多様性』は世界の別の誰かの『多様性』に内包されると信じる」
ことを提示したい。先ほど述べたように、あなたが集団をつくる時にもたらす多様性と、私が集団をつくる時にもたらす多様性は大きく異なる。それはすなわち、あなたの個性に惹かれて集まる人々は、私に惹かれて集まる人々と異なるということだ。
『自分にとっての多様性』を言明せずに「多様性」を謳ったとしても、自分の価値観の提示には繋がらない。何が好きで、何が嫌いか。これをはっきりさせない限り、あなたが望む多様な未来は依然として何かが不明瞭なままだ。なぜなら、世界や他者への不信と同じく、「自分への不信」が根本に存在するからである。
世界はどうせ私を受け入れてくれない。だから、そんな自分でも受け入れられるような「多様な世界」であってほしいと願う。
価値観を言明しないのも、価値観で線引きした結果、その「多様性」に自分が漏れてしまうという可能性を恐れているから。つまり「自分への不信」である。
あなたが望む多様性は、この世のすべてを包括した「多様性」ではない。あなたが望む多様性は、あなただけの「多様性」であるはずだ。
その世界から、自分がのけ者にされるといった「不信」や「恐れ」をまずは捨てた方がいい。それができて初めて、あなたが望んだ「多様性」が目の前に広がることになるだろう。そして、あなたがあなたの世界で生きることができるのならば、それに感化された結果、誰しもがその人にとっての「多様性」をこの世界にもたらせるはずだ。
その最初の一歩は、あなた自身の考えを言葉にし、あなたがあなたの多様性を受け入れることからはじまる。私はそう考える。

まとめ
以上で「多様性」の解体ショーを締めくくろうと思う。
「多様性」を多用するとむしろ「一様的」になってしまう。恐ろしい矛盾を引き起こす罠が、そこには隠されているのだ。
ブランディングやクリエイティブに携わる人へのTipsも、最後に一つ提供しておこう。クリエイティブにおいて安易に「多様性」を使うとき、「どうせ私の/クライアントの想いを言葉にしても受け入れられない」というあなたの諦念が入っている可能性がある。クライアントを信じよう。そして何より、自分を信じよう。そうやって初めて、本当の意味での「多様性に叶った」提案ができるようになるはずだ。
以上、本日も対戦ありがとうございました。
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)


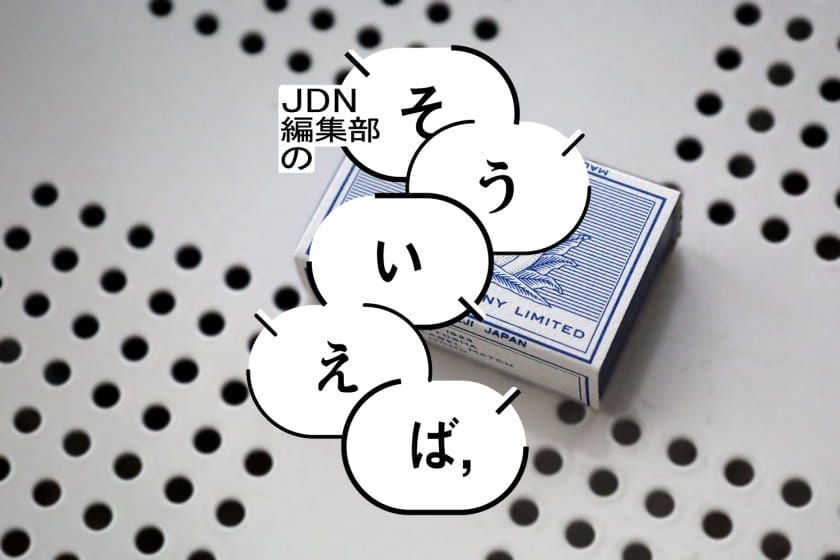
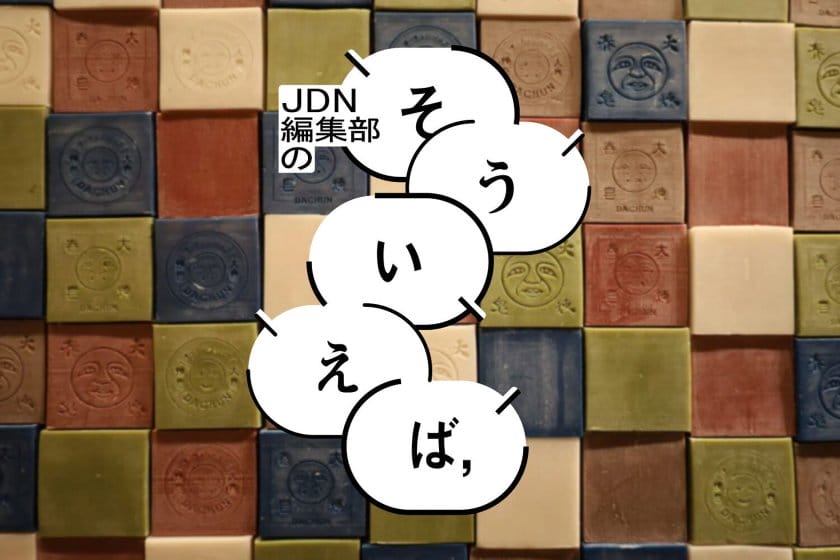


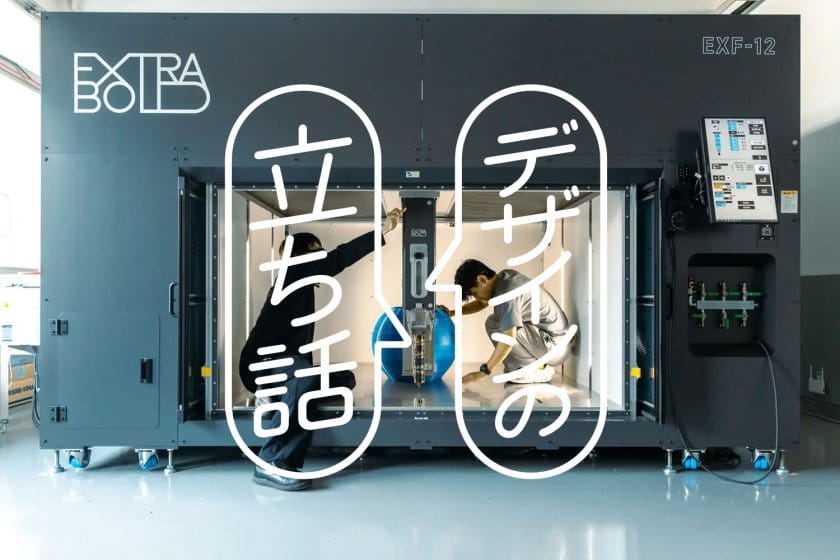





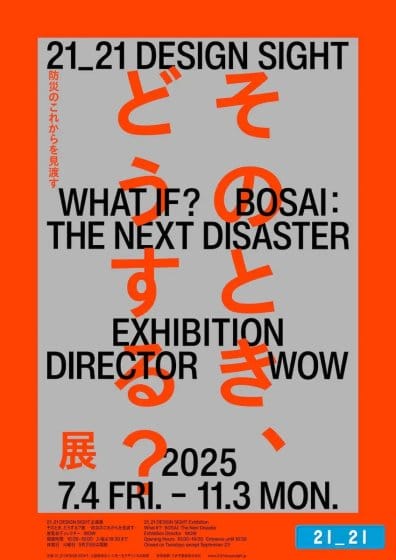
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)