編集部の「そういえば、」2021年12月

ニュースのネタを探したり、取材に向けた打ち合わせ、企画会議など、編集部では日々いろいろな話をしていますが、なんてことない雑談やこれといって落としどころのない話というのが案外盛り上がるし、あとあとなにかの役に立ったりするんじゃないかなあと思うんです。
どうしても言いたいわけではなく、特別伝えたいわけでもない。そんな、余談以上コンテンツ未満な読み物としてお届けする、JDN編集部の「そういえば、」。デザインに関係ある話、あんまりない話、ひっくるめてどうぞ。
水のように静かに沁み込む展覧会
そういえば、少し前に箱根のポーラ美術館で開催中の企画展「ロニ・ホーン:水の中にあなたを見るとき、あなたの中に水を感じる?」を観に行ってきました。
本展は、アメリカの現代美術を代表するアーティスト、ロニ・ホーンさんの国内の美術館における初個展。近年の代表作であるガラスの彫刻作品をはじめ、1980年代から今日にいたるまでの約40年間におよぶ作品の数々を紹介しており、来場者は水のようにしなやかに多様な解釈を受け入れる彼女の作品のあり方を探ることができます。
写真や彫刻、ドローイング、本など多岐にわたる彼女の作品の中で印象的だったのは、最初に来場者を迎える「ガラス彫刻」シリーズ。来場者は8つの彫刻作品のまわりをぐるぐると回りながら鑑賞することができますが、自然に囲まれたポーラ美術館の美しい風景とあいまって、独特の時間が流れているかのような雰囲気に包まれていました。

水を湛えた器のようにも見える作品は、見る角度や周囲の風景、時間帯によっても表情を変えます。

(左)アメリカの詩人、エミリ・ディキンスンが書いた手紙の言葉から選んだ一節をモチーフにした作品『エミリのブーケ』(右)これまでに発行された作品集なども会場に並びます。
会場ではそのほかにも、どの1枚とも同じ表情がないロンドンを流れるテムズ川の水面をとらえた写真や、呼吸するように継続して描かれてきたという巨大なドローイング作品など、40年間でつくられてきた彼女の作品を多様な角度から知ることができます。

ロンドンのテムズ川の表情をとらえた作品『静かな水(テムズ川、例として)』。

展覧会のメインビジュアルにも使われている『あなたは天気 パート2』。彼女にとって主要なメディアだという写真を使った作品。まっすぐに視線を向ける女性のポートレートが100枚ほど並びます。アイスランドの温泉で6週間にわたって女性の表情の微妙な変化を記録し続けたものだそうで、一人の女性が見せる唯一無二の100の表情を追いかけています。
会場に並ぶ作品自体はもちろんですが、個人的には哲学者・ニーチェの有名な格言である「深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ」を想起させるような詩的な展覧会タイトルにとても惹かれました。彼女の作品自体は、来場者それぞれが感じたことを優先するよう、余計なものをそぎ落として構成されているのかなと思いましたが、会場全体では一貫したポエティックさを感じ、来場者に静かに、だけどひしひしと訴えかけてくるような不思議な空気を感じた展覧会でした。
会期は2022年3月30日まで。少しあたたかくなってきた季節に足を運んでみてはいかがでしょうか。
(石田 織座)
なにかが生まれる瞬間とコミュニケーションの記録ードキュメンタリー「ザ・ビートルズ:Get Back」
そういえば、ディズニープラスで配信中のドキュメンタリー「ザ・ビートルズ:Get Back」を観ました。ザ・ビートルズのアルバム「Let It Be」のレコーディングの様子と、4人が揃ってパフォーマンスを披露した最後の場となったルーフトップ・コンサートが開催されるまでの過程を映したドキュメンタリーシリーズで、「ロード・オブ・ザ・リング」のピーター・ジャクソンが監督を務めています。
「Get Back セッション」といえば、ビートルズが解散に向けて関係性が悪化していく中で行われたものであり、のちにフィル・スペクターのプロデュースによってリリースされたアルバム「Let It Be」に対してポール・マッカートニーが抗議するなど、あまりいいが印象がないファンも多いと思うのですが、本ドキュメンタリーは、ビートルズ史のイメージが刷新されるような素晴らしい作品ではないかと思います。
ピーター・ジャクソンは、本ドキュメンタリーの前に手がけた「彼らは生きていた」においても、第一次対戦時のフィルムを美しいカラー映像に蘇らせていますが、本作においてもまず目を見張るのは映像の美しさだと思います。まるでつい最近の記録映像のような生々しさは、ビートルズというバンドとの距離感を縮めるのには十分で、「いま自分はビートルズを聴いている」という特別な感情に、いまになってまた新しい感覚が追加されるような体験でした。
……といったように、「ビートルズ好きがなんだかまたうるさいことを言っているぞ」という感じでスルーしてしまう人に向けて書かせてもらうと、このドキュメンタリーの魅力は、そういったファン垂涎の秘蔵映像的な要素だけではなく、音楽というものをつくり上げていく過程をつぶさに映し取っているところだと思います。
バンドによるロックミュージックの制作プロセスはさまざまですが、ビートルズにおいては4人がプレイヤーとしての魅力にあふれ、それぞれがソングライターであることがなによりの素晴らしさであり、本ドキュメンタリーではそれらの個性がひとつの音楽として結実していくドラマが十二分に描かれています。ほとんど仕上がった状態の曲をポールとの掛け合いの中でブラッシュアップしていくジョン・レノン、頭に浮かんだアレンジをメンバーに次々と提案していくポール、「昨晩書いたんだ」と控えめながら弾き語りはじめるジョージ・ハリソン、そして急にタコの曲を書いてくるリンゴ・スター……とにかく4人の才能がひとつの空間の中で生み出される興奮に満ちた瞬間ばかりです。
そしてあらためて、バンドで音楽をつくるということは、コミュニケーションそのものだということが、本シリーズを通して得られたなによりの気づきでした。新たに書き下ろされた曲がスタジオに持ち込まれ披露される瞬間や、セッションを通してアイデアが積み重なっていく過程は、互いの信頼関係があってこそ生まれるコラボレーションであり、クリエイター同士による真摯なコミュニケーションそのものだと思います。そして、何度も何度も演奏を繰り返しながらアレンジのアイデアについて意見を交わし、それらがひとつの音楽として仕上げられていく。ここまで制作プロセスを丁寧に追ったドキュメンタリーはなかなか観られないのではないかと思います。
音楽についてのドキュメンタリーではあるのですが、彼らがセッションを通して交わしていたコミュニケーションは、日常生活の中でアイデアを提案したりそれについて意見を交わす場面にも生きる言葉があるように思います。関わるすべての人が真剣になにかを生み出すことに向き合っているからこそ生まれるものがあり、それはなにかをつくる仕事や活動に携わる上で必要な姿勢だと、あらためて思いました。
観終わってから、はたしてぼくはジョン・レノンのように無邪気にアイデアをぶつけられているだろうか、ポール・マッカートニーのようにつくることに没頭できているだろうかと、つい反省してしまう自分がいました。そして、ジョージ・ハリソンのように途中で辞めるとか言い出すのはよそうと、自分を戒めたのでした。ジョージの曲は好きですけど、あれはよくない。
(堀合 俊博)
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)




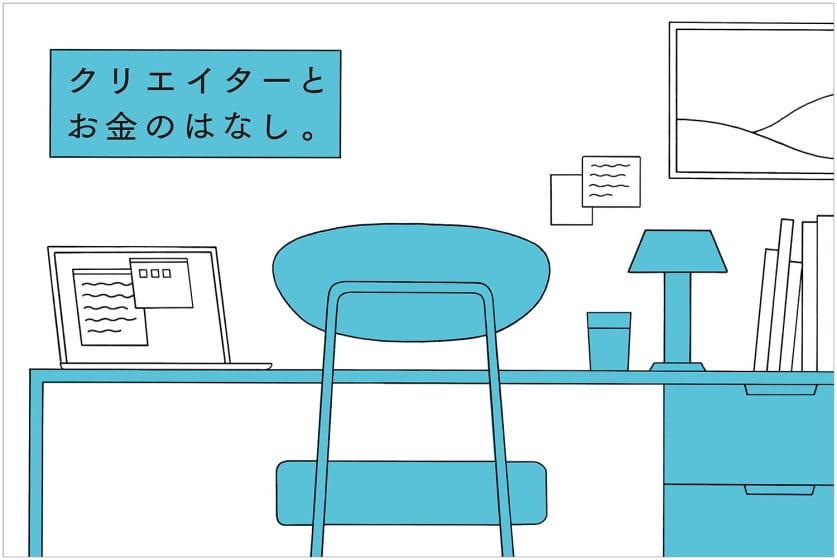







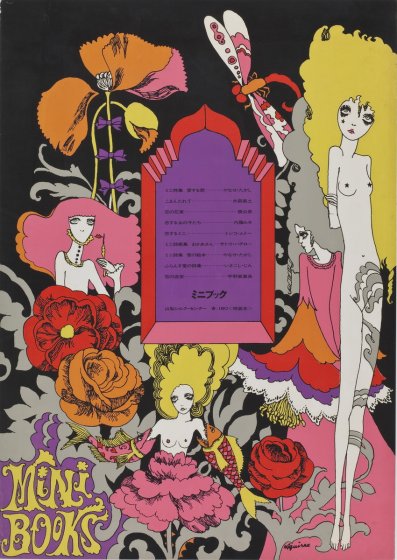
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




