人口約1万人、少子高齢化が進む新潟県の田上町。この小さな町に4万人もの人を集めるのが、今年で4回目を迎える竹林を活かしたアートイベント「たがみバンブーブー」です。
同イベントの立役者である馬場大輔さんは、2024年に地域活性化への貢献が評価されてグッドデザイン賞を受賞した「道の駅たがみ」のプロデューサーで、館長でもあります。そしてこの道の駅が、たがみバンブーブーをはじめとしたさまざまなプロジェクトの拠点としても機能しています。

道の駅たがみ
小さな町の道の駅から、人が人を呼ぶ「場」や「仕組み」を次々と生み出す馬場さん。その活動にかける思いとともに、「たがみバンブーブー」「道の駅たがみ」の魅力をレポートします。
放置竹林がテーマパークに大変身。竹と光の癒し空間へ
新潟駅から電車に乗ること30分。町の大部分を田園と竹林が占める、小さな町「田上」に到着します。ここで開催されているのが、切り出した竹に穴を開け、中に灯りをともす「竹あかり」のアートイベント「たがみバンブーブー2025」。2022年の初開催時には2万人が訪れ、町に20年ぶりの渋滞が発生したという人気イベントです。

たがみバンブーのロゴやグラフィックは、新潟を拠点に活動するデザイン事務所「hickory03travelers」のデザイナー・迫一成さんが担当する
会場全体のプロデュース・制作をおこなうのは、あらゆる空間を竹あかりで演出する集団「CHIKAKEN」の三城賢士さん。日本中のさまざまな場所で制作をおこないながら、地域が抱える課題にも向き合ってきました。
15年以上にわたるCHIKAKENの活動のなかでも、今回はじめての試みとなるのが「放置竹林」の中での竹あかり設置です。一度竹を切り出し、竹あかりとして再び竹林に戻すことで竹林自体の価値を伝えたいという田上町と三城さんの思いが一致し、プロジェクトが本格的にスタートしました。

プロジェクションマッピングの演出には、プロジェクションディレクター・岸本智也さんが参加

竹あかり制作にはボランティアのみなさんも参加。夏の期間、町内外から多くの人が集まり竹に一つひとつ穴を開ける
竹林に足を踏み入れると、竹の隙間からこぼれる灯りの数々が幻想的な世界をつくりだしていました。あたりに響く虫の声が耳に心地よく、また、少しの雨風は竹が防いでくれます。

光を用いた表現をおこなうアーティスト・髙橋匡太さんの作品「まきまき竹あんどん」。工場で廃棄される予定だったハギレを活用し、地域の人々と一緒につくり上げられた

ロープ遊具アーティストのはんすさんによる作品
竹の間を進んでいくと、アート作品やロープでできた巨大な遊具が出現。ロープ遊具は靴を脱いで登ることができ、背の高い竹の間を縫うように全身をつかって進んでいく体験は、子どもはもちろん大人も楽しいアクティビティです。
ほかにも、プロの演奏家による音楽ライブ、竹林でととのうテントサウナなどプログラムは盛りだくさん。
なかでも音楽フェスやグッズ販売、飲食などを楽しめるプログラム「たがみバンブーナイト」は、地元中学生のみなさんが学校の「総合」の時間を約半年間使い、自分たちで企画から進めてきました。バンブーブー実行委員会の大人たちは、そのサポート役としてプロの協力者をつなぎながら当日まで見守ります。子どもから大人まで、地域の人々を巻き込みながらイベント開催の日を迎えました。
田上の豪農屋敷、枯山水の庭園にも竹あかりが灯る
テーマパークのような竹林会場と打って変わるのが、田上が誇る豪農屋敷「椿寿荘」の竹あかり展示です。

バンブーブーの期間だけ、夜の庭園が特別な演出で生まれ変わる
ヒノキを使った寺院様式で、釘を一切使わずに仕上げられた椿寿荘。江戸末期には小作人2,794人を抱えたという巨大地主の離れ座敷で、1897年に建てられました。
建物には見どころが多く、例えば縁側のひさしには約20mの節ひとつない吉野杉が使われています。そんな歴史や職人技に思いを馳せつつ、縁側に座って眺める竹あかりの庭園には、心を落ち着かせてくれる特別な静けさが漂っていました。
ほかに、羽生田駅前や道の駅たがみなどでも展示を楽しむことができます。場所ごとに異なる表情を見せる竹の空間演出が見どころです。
人が集まる田上町の拠点。「やさしい」道の駅たがみ
会期中は温泉旅館や飲食店の前などいたるところに竹あかりのオブジェが設置され、町全体が盛り上がる田上。なかでも道の駅たがみには総合案内所が設置され、イベントの拠点となっています。

建物の内外に設置されたベンチでは、地域住民の方たちが談笑する
「やさしい道の駅」を掲げる同施設では、農作物や土産品の販売、特産品の梅やたがみポークを使ったメニューの提供のほか、地域の方向けの無料スマホ教室、町内外の方が交流できるタケノコ掘り体験や梅干しづくりなどのワークショップも開催。地域資源を魅力的に活用し、人々に親しまれています。
ハード面でも、防災トイレの設置やユニバーサルデザインの導入、一部施設の電源を自家発電でまかなうなど、「やさしい」を軸としたデザインが特徴。これらの活動が評価され、2024年にはグッドデザイン賞を受賞しました。

明るい店内は平日の昼間も人でにぎわう

特産の梅を氷砂糖と一緒に漬けたシロップ。この特製シロップでつくる「やさしい 梅ソーダ」はさわやかな酸味で、小休憩のお供にぴったり

地域の小学生たちが考えた田上のキャラクターを缶バッチにして販売。竹やアジサイ、梅などがモチーフ
道の駅たがみとたがみバンブーブーのデザインを担当するのは、新潟で地域に根差したデザインをおこなうhickory03travelers。プロダクト、グラフィック、空間をはじめ幅広く手掛けるクリエイティブ集団です。「日常を楽しむ」をコンセプトとし、新潟だからできることに素直に取り組む――そうした、無理なく地域活性化に貢献する姿勢が評価され、2015年に彼らのデザイン活動がグッドデザイン賞を受賞しました。

店内では道の駅のロゴを使用したグッズも展開。ロゴのデザインは、田上のシンボルである「護摩堂山」とそこに暮らす生きものを組み合わせてつくられた
取材に訪れた日も、店内には年配の方から若い層までたくさんの利用者がいました。屋内外には気軽に座れるベンチが充実し、ショップには丁寧な商品説明が添えられ、食堂では「おじさんでも食べ切れる小さめサイズ」というコメントつきの「おじさんソフト」が販売されているなど、ハードとソフトの両面において「やさしさ」が散りばめられていたのが印象的でした。
地域を編集し、当たり前だったものを「再価値化」する

馬場大輔さん 「道の駅たがみ」館長。新潟市の「豪農の館 北方文化博物館」での勤務を経て、2020年に田上町へ。道の駅の運営のほか、田上の地域文化を発信するさまざまなプロジェクトを仕掛ける
道の駅たがみの館長で、たがみバンブーブーの発起人である馬場大輔さんがおこなうのは、田上町で先人がつないできたものや文化をいまの暮らしや価値観に照らし合わせ、「価値を見直す」作業だといいます。
新潟市の「豪農の館 北方文化博物館」で、新潟の生活文化を次世代につなぐ仕事をおこなってきた馬場さんが、生まれ故郷の田上町に戻ったのは2020年。道の駅立ち上げのタイミングでした。道の駅をつくるにあたり新潟県民を対象にアンケートを実施したところ、半数が田上町の存在を知らず、そのうち7割が田上町に「特産品はない」と回答したといいます。その結果に、「田上の子どもたちに、故郷に誇りを持ってもらいたい」という思いを強くした馬場さん。
田上の特産品である竹や筍は、子どもたちが登校時に蹴って転がし、学校帰りには担いで帰っていたというほど当たり前の存在でした。市場にあふれ、地域の人々が価値を見出さなくなっていたのです。そんな竹の町に誇りや愛着を持ってもらうには、驚きや感動が必要――そう考え、放置竹林を活かした「バンブーブー」の開催を思い付きます。
日本には多くの竹の産地があり、竹あかりイベントも各地で開催されています。その中でたがみバンブーブーが魅力を放つのは、馬場さんの求心力と行動力に引き込まれて参加を決めるアーティストやさまざまな分野のプレイヤーの存在があるから。自身の思いを人と共有し、発信したいものの価値を再編集して伝える――今回の取材でも感じられたそんな馬場さんの力が、人と人をつなぐ「場」や「仕組み」をつくりあげていました。
会期:2025年9月13日~10月13日
ライトアップ:18:00~20:30 ※道の駅たがみのみ23:00まで
会場:新潟県田上町(たがみバンブーブー竹林、椿寿荘、道の駅たがみ、駅前アート)
料金:たがみバンブーブー竹林 1,500円、椿寿荘 800円(いずれも中学生以下無料)/ロープアスレチック 500円(中学生以下100円、未就学児無料)
※道の駅たがみ・駅前アートは無料
※休日料金、一部オンライン販売料金あり
取材・執筆:萩原あとり(JDN)
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)












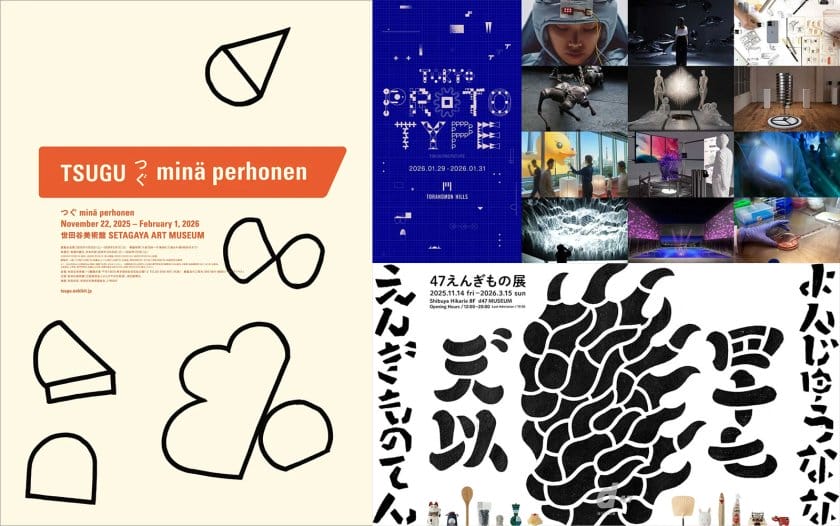


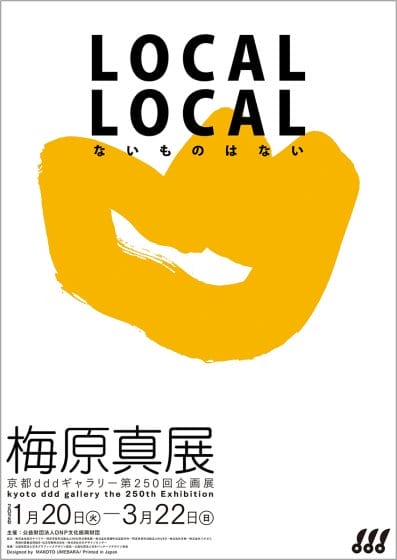
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




