東京造形大学の自由な校風
鈴木マサル(以下、鈴木):僕がテキスタイルデザインの仕事を手がける一方、東京造形大学に勤務しはじめたのが2002年です。これまでいろいろな大学を見てきましたが、やっぱり造形大ならではの校風というか、特徴ってあるんだなあとつくづく思います。比較的小規模な分、先生同士もそうだし、学生と先生との距離が近いのは確かです。規模の大きな大学だと、同じ学科専攻の学生でさえ教授に会うのが半年に1回レベルのところもあると聞きますので、何か相談したい時でもすぐに動いていきやすいメリットはありますよね。この小ささが有利に働いている面って大きいと思います。藤森さんが東京造形大学を卒業されたのはいつですか?

鈴木マサル(すずきまさる)
多摩美術大学染織デザイン科卒業後、粟辻博デザイン室に勤務。1995 年に独立、2002 年に有限会社ウンピアット設立。2005 年からファブリックブランド OTTAIPNU(オッタイピイヌ)を主宰。自身のブランドの他に、2010年よりフィンランドの老舗ブランド marimekko のデザインを手がけるなど、現在、国内外の様々なメーカー、ブランドのプロジェクトに参画。東京造形大学教授、有限会社ウンピアット取締役。
藤森泰司(以下、藤森):1991年です。僕が通っていた頃はまだ高尾にキャンパスがあって、高尾駅から少し山を登ったところにあるディープな場所でした。なかなかすごいところに来たぞと思いましたね。彫刻の学生が山の中に自分が制作した人物像なんかを置いていっちゃうので、それがまた怖いんですよ(笑)。キャンパス自体の規模が小さいので、なんとなくみんなが顔見知りなんです。そういうおもしろさはありました。いい意味でコンパクトな大学ですよね。今だと考えられないですが、夜通しで学祭をやってバスがなくて歩いて帰った記憶も……(笑)。
鈴木:まだそういう昔ながらの良さが残っている感じはありますね。大きな大学だと決まった時間に一斉にセキュリティがかかって一歩も中に入れないんですが、うちは卒業制作の前なんかは結構ごちゃごちゃとすごいことになっています(笑)。何年か前の卒業制作の時に、僕が教えるテキスタイルデザイン専攻領域の学生が彫刻専攻領域の学生を連れてきて、「僕は彼と共同で卒業制作をやります」と言うので「ああ、いいね」と許可したんですが、それってほかの大学ではなかなかできないことかなと。いい意味でゆるいというか、自由な校風の大学ですね。
藤森:カリキュラム的にも専攻間の出入りが許されているので、他専攻の学生とも必然的にふれあう機会が多くなりますよね。そこはいい面だと思います。
学科を超えて幅広く知識や技術を習得できる横断的なカリキュラム
鈴木:そもそも藤森さんが東京造形大学に入学された理由はなんだったんですか?
藤森:当時は、家具のデザインをやりたいとはまったく考えていませんでした。立体が好きだったので、彫刻を勉強したいと思っていたんです。でも、ほかの美大の彫刻科に行くと、たぶん彫刻だけを学ぶことになるなと。というのも、立体は好きでしたが本気で彫刻家になろうという強い意志まではなくて。同時にアートやデザインにも興味があったので、いろいろ学べると聞いて東京造形大学を選んだんです。僕が大学生だった頃は、デザイン学科がⅠ類とⅡ類に別れていました。Ⅰ類がグラフィックや広告、映画や写真などのいわゆる平面系で、Ⅱ類がインダストリアルや家具や建築などの立体系。ちなみに僕はⅡ類を受けました。Ⅱ類で入ったんですけど、やっぱりⅠ類の写真の授業を取ったり、映画の授業を取ったりしていましたね。写真の基礎も、その選択授業の中で学びました。あとは、建築のゼミに籍を置いているけど写真の勉強もしたいということで、写真の先生にも教わりに行っているような学生も結構いました。

藤森泰司(ふじもりたいじ)
東京造形大学デザイン学科Ⅱ類卒業後、家具デザイナー大橋晃朗に師事。長谷川逸子・建築計画工房を経て、1999年に「藤森泰司アトリエ」設立。家具デザインを中心に据え、建築家とのコラボレーション、プロダクト・空間デザインを手がける。近年は図書館などの公共施設への特注家具をはじめ、アルフレックス等のハイブランドの製品から、オフィス、小中学校の学童家具までジャンルを超えて幅広く活動中。桑沢デザイン研究所、武蔵野美術大学、多摩美術大学、日本工業大学非常勤講師。
鈴木:何年か前の話ですが、ID(インダストリアルデザイン)に在籍していた学生がテキスタイルの授業も選択していて、最終的には自動車メーカーに入社して車両のカーシートのデザインをしています。まさにIDとテキスタイルのいいとこ取りをして就職していったという。そんなふうに、自分の意思で専攻科目以外の授業を学ぶことができるのは、可能性としてすごく広がりがあるように思います。価値観が多様化してきた今、何かひとつのことを学んでいればいいという状況ではなくなってきていることも確かなので。

鈴木氏が教授を務める、テキスタイルデザイン専攻領域の授業風景
藤森:そうですね。そこはメリットですよね。ただ、全部自由に選択できるのってもちろんいい面ではあるし、合う人にはすごく合うと思いますが、逆に自由すぎてどうしていいかわからなくなっちゃう学生もいたみたいです。
鈴木:自由ってその分責任も伴いますから、学生によっては難しいと感じる面もあるのかもしれませんね。そういう意味では、東京造形大学のカリキュラムはいろいろな授業を幅広く選択できるけれど、単に自由に選べることがメリットではなくて、自分が選んだものに対して責任をもって学ぶということが学生自身に委ねられている。そこがいいのかもしれないですね。

表参道のスパイライルで行われた、「東京造形大学テキスタイル専攻有志卒業・修了制作展2016」の展示風景
藤森:そうですね。まずそこでよく考えるじゃないですか。自由に選択できるけどどうしようかって。自分が選択したからには責任と熱量をもってやらないといけないですし。学生のうちからそういう感覚を養える場はとても貴重だと思います。
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

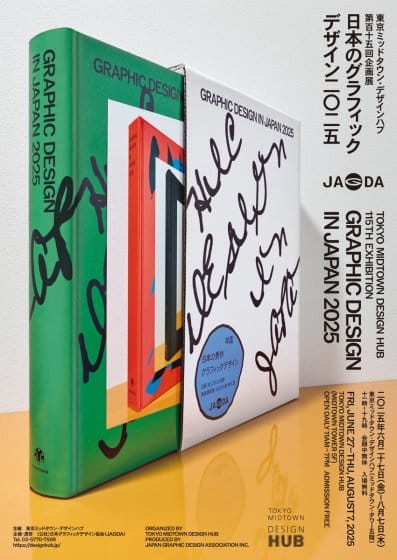
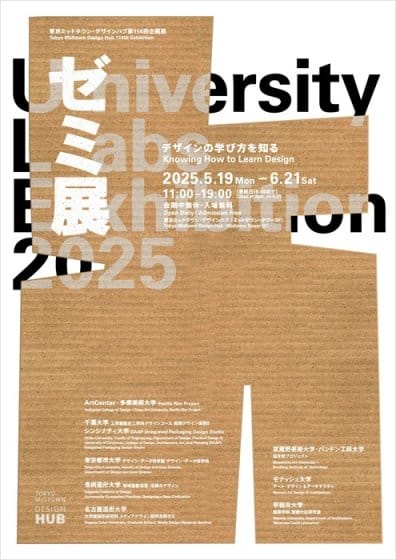


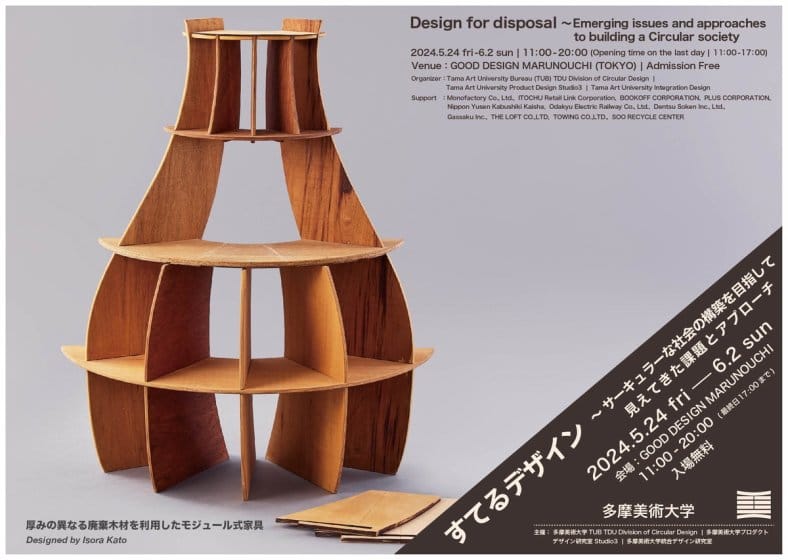










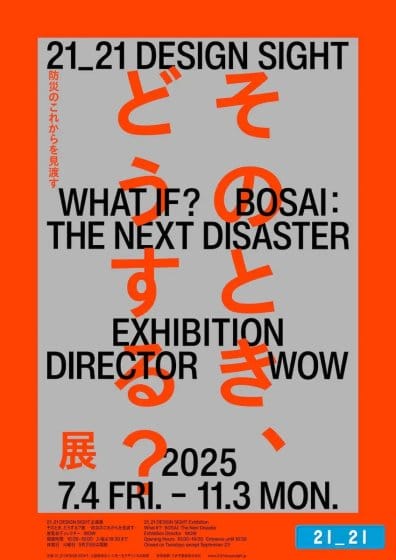
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




