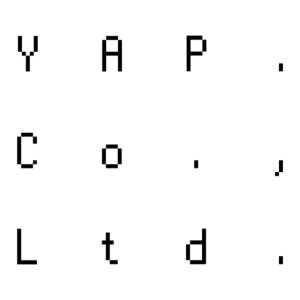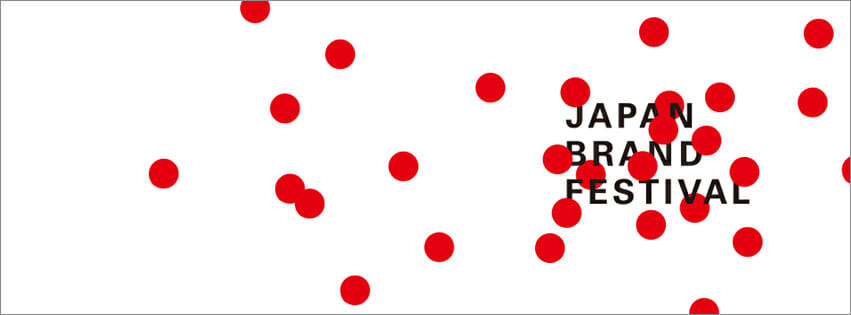
JAPAN BRAND FESTIVALとは、いったい何なのか?
二本栁友彦さん(以下、二本栁):理想のイメージは、安土桃山時代に自由取引市場をつくって成功した「楽市・楽座」の現代版です。ジャパンブランドに情熱を傾ける人たちをどんどん巻き込んで、つながって新しいネットワークをつくれば、何か新しい“価値あるもの”が生まれるんじゃないか。そう思って、この活動をはじめました。
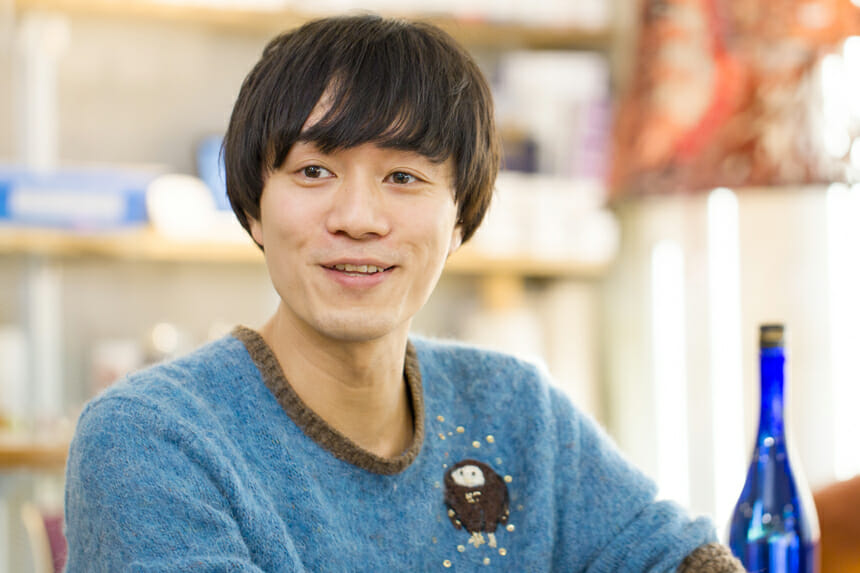
二本栁友彦さん(株式会社 ロフトワーク)
堀田卓哉さん(以下、堀田):二本栁さんから「ちょっと相談したいことがあるんだけど」ってJAPAN BRAND FESTIVAL(以下、JBF)の話をもちかけられたのが、2015年の10月頃です。それまでお互い面識はあったんですが、それぞれが関わっているプロジェクトについては実はあまり深く知らなかったんですよね。
同じゴールを目指すためのアプローチはひとつじゃない
二本栁:僕がいま関わっているのは、「MORE THAN プロジェクト」という経済産業省の事業。ジャパンブランドの中小企業と、国内のプロデューサーやデザイナーとがひとつのチームをつくって、そのチームの力で海外に日本のモノやサービスを売り出していこうというプロジェクトです。
堀田:僕は、「CONTEMPORARY JAPANESE DESIGN PROJECT(以下、CJD-P)」という、世界で勝負できるジャパンブランドをつくるための商品開発プロジェクトに携わっています。海外のバイヤーやデザイナーの協力を得て、日本のメーカーはさまざまなアドバイスをもらいながら、アイデアを形にします。
世界を目指すために、売れる商材がある企業は「MORE THAN プロジェクト」で最後のひと押しを。片や、まだ商材が確立していない企業は「CJD-P」と一緒に商品開発からスタートすることもできるんです。

堀田卓哉さん(株式会社 Culture Generation Japan 代表取締役)
二本栁:堀田さんも僕も、「世界を目指す」という同じゴールを見ているんだけれども、まったくアプローチが違うのが面白いですよね。
堀田:でも、JBFをスタートする前までは、僕たち自身も、まだお互いが何をやっているのかを正確に理解できていなくて。日本のメーカーはなおのこと、どのプロジェクトにどう参加すればいいのか、正直わからないと思うんですよ。
二本栁さんとふたりで、「何でいままで横の連携がなかったんだろうね」っていう話からはじまって、「まずは、僕たちふたりが連携して、そのネットワークを少しずつでも大きくしていけば、絶対に何かが変わるんじゃないか」という結論に至って。「これは、絶対にやらなきゃいけない!」と即答しました。
二本栁:だから、JBF自体は、特定の人のための組織じゃないんですよね。いろんな地域の人、いろんな立場や目線の人たちがつながるためのものなんです。各々が必要な人やモノに自らアプローチして関係性を広げていくためには、「とにかくまずは、自分から発信しよう!」「ジャパンブランドに関わる人たちと話をしてみたい!」と、2016年1月に第1回イベントをさっそく企画しました。

2016年1月に行われた「JAPAN BRAND FESTIVAL 2016」。ジャパンブランドに関わるさまざまな組織・立場の人たちによるトークセッションをはじめ、ジャパンブランドを支援するプロジェクトやパートナー企業による展示、メンバー同士の交流会などを、1週間にわたり開催。3,519人を動員した。
知られずになくなってしまうのは、もったいない!
二本栁:JBFスタート当時から、ジャパンブランドを支援するいろんなプロジェクトに参加していましたが、つくづく、「とってもいいものをつくっているのに世界に届いていないんだなぁ」と思っていたんですよね。
そのまま放っておいたら、確実になくなってしまうものがたくさんあるんですよ。それが、すごくもったいない気がして……。この思いをきちんと伝えたいんですよ!

堀田:「もったいない!」はわかります。日本各地の職人さんたちに話を聞きに行っても、「この技術ができるのは、自分だけなんだ」という話をよく聞きますからね。本当に切なくなります。
一方、海外でも、「実は、自分の国にも伝統工芸ってあるんだよね。でも、もうすたれてしまって、産業としては成立していないんだ」って、いろんな国の人が言っています。
伝統と変化を同時に受け入れてきた日本の強み
堀田:各国の伝統工芸がすたれてしまった原因のひとつは、現代の大量生産、大量消費のサイクル。そこから脱して、新しいライフスタイルを生み出していかないといけないって、世界中の人たちが漠然と感じているんじゃないか。そして、新しい未来の姿を提示し得るような地場産業は、もしかしたら日本ぐらいしか残っていないんじゃないか……そんな危機感をずっと抱えていた気がします。
二本栁:なぜかというと、新しいスタイルに変化していくことを受け入れつつも、いままで培ってきたことをきちんと伝承していくというマインドを、世界で唯一、日本がもっているからなんですよね。鎖国という歴史的背景や、島国という地理的な特性もあって、日本は先進国でありながらも、伝統的な国の文化がしっかり残っている。それはすごく誇れることだし、失うのは絶対にイヤだなぁと思いますね。

“やる気のある、おせっかい”たちをつなぎ合わせたい
二本栁:僕らに何ができるかっていったら、伝統的な日本の文化を失いたくないという熱意をベースに、「何かが変わる」「変わるかもしれない」という立ち位置で動くこと。
ふたりとも、行政の仕事にこだわっている理由は、「プロジェクトの存在意義は?」とか、「組織の仕組みをこう変えたい!」とか、いろいろ意見を言うことができるから。それが全部反映される訳ではないけれど、言い続ければ少しずつでも変わっていくと思うからなんですよ。
行政にも、民間業者にも、熱量の高い人たちがたくさんいるはずなので、その人たちをどんどん巻き込んでいきたいんですよね。「あの取り組みは面白そうだから、お前やってみろよ」とか、「あの取り組みと、この取り組みは、つながると面白いことになりそうだ」とか、どんどん意見を言う発信力のある人。言うなれば、“やる気のある、おせっかい”タイプの人たちを集めたいんです(笑)。

- 1
- 2
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)














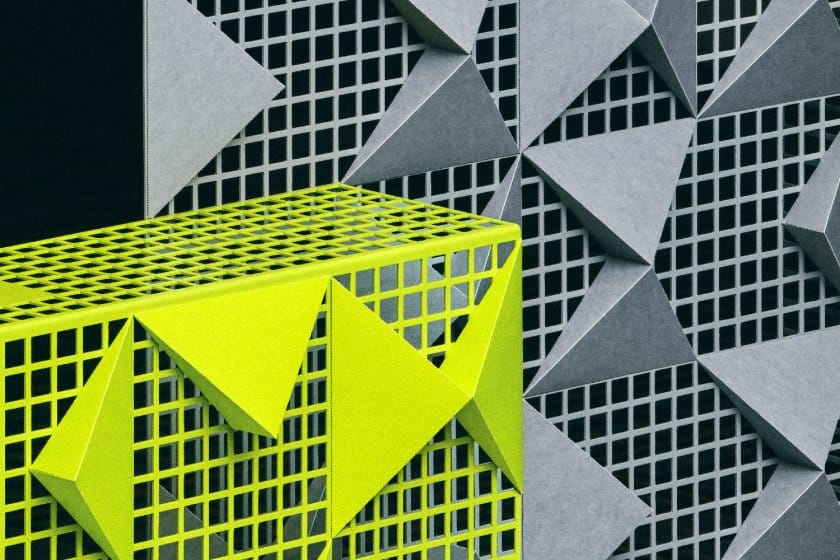

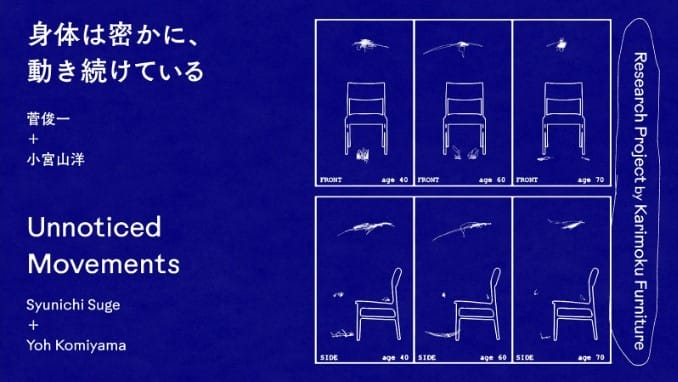
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)