編集部の「そういえば、」2021年1月

ニュースのネタを探したり、取材に向けた打ち合わせ、企画会議など、編集部では日々いろいろな話をしていますが、なんてことない雑談やこれといって落としどころのない話というのが案外盛り上がるし、あとあとなにかの役に立ったりするんじゃないかなあと思うんです。
どうしても言いたいわけではなく、特別伝えたいわけでもない。そんな、余談以上コンテンツ未満な読み物としてお届けする、JDN編集部の「そういえば、」。デザインに関係ある話、あんまりない話、ひっくるめてどうぞ。
JDN編集部に届いた、ひと際ユニークな年賀状
そういえば、今年もJDN編集部にたくさん年賀状が届きました。その中でも特にユニークだった、グラフィックデザイナーの小玉文さん(BULLET Inc.)から送られてきた年賀状をご紹介します。
小玉さんは毎年とても手が込んだ、こだわりがぎゅぎゅっと詰まった熱量のある年賀状を送ってくださっています。昨年はねずみ年にちなみ、チーズをモチーフにしたフロッピーディスク型の年賀状。今年は、なんと牛をモチーフにしたカセットテープ、その名も「COWSETTE」です。

手元で見ても本物そっくり見た目と質感ですが、よくよく側面などを見ていくと紙を重ねてつくられたものだと気付きます。

個人的にぐっと来たポイントは、中央の穴が空いたリールハブと呼ばれる部位で、昔気になって指を突っ込んだ時の感触を思い出すほどの再現度でした(笑)。カセットテープを実際に使ったことがある人ならわかる、テープのたゆみ具合もそっくり。


以下、小玉さんのFacebookに掲載されていた、製作プロセスに関するコメントを抜粋してご紹介します。
「実はこちら、本物のカセットではなく、牛乳パックの再生紙[スノーボード]を8枚積層してつくっています。カセットらしさを再現するために、リアルにネジ止めしているところがポイント。この数日間で、電動ドライバースキルが上がりました。伸びたテープ部分には、箔押し加工に用いる[金の箔ロール 3号金(裏面BL接着剤)]を4mm幅にカットしたものを使用。ほかにも、カセットテープ世代には懐かしい要素をいろいろと盛り込んでみました(小玉文さんFacebookより)」
ちなみに今回の「COWSETTE」は、箔押し印刷工房のコスモテックさん、紙の加工会社の東北紙業社さんと一緒につくり上げたものだそうです。ライフワークと呼んでいいのではと思うほどの毎年の年賀状。1つの作品を届けていただいている感覚で、つい来年の寅年にも期待が膨らんでしまいます。
(石田 織座)
『ソウルフル・ワールド』のビジュアライズとストーリーテリング
そういえば、昨年末にDisney+にて配信されたピクサーの最新作『ソウルフル・ワールド』について、年末年始にかけて絶賛の声を多く見かけたように思います。ぼくもお正月の休みに鑑賞して、そのあまりのすばらしさに感激してしまいました。
プロのジャズピアニストになることを熱望する人物が主人公の本作は、全編に渡って溢れるジャズへの愛がなによりの魅力だと思うのですが、ピクサー映画好きにとっては、『モンスターズ・インク』や『カールじいさんの空飛ぶ家』、『インサイド・ヘッド』を手がけたピート・ドクターが監督した作品だということに注目して観ていました。
『ソウルフル・ワールド』では、キャラクター化されたまだ生まれる前の魂たちが、地球へと降りていくための準備をする、“ユーセミナー”という学校のような空間が描かれます。そこでは、性格を決定する“館”が存在し、ジェリーと呼ばれる講師のような存在によってそれぞれの魂が館へと送られ、「愛想がない」だとか「心配性」、「自己中心的」などといったパーソナリティが決定されていきます。
さらに、魂たちの胸には7つのバッジがあり、生きていく上での“きらめき”を見つけることでバッジを埋めていくことができるんですね。そのために、魂たちはさまざまな職業を体験できる“万物の殿堂”と呼ばれる場所で、自分にとってのきらめき=才能のようなものを見つけていくのです。そして、バッジを集めることで魂たちは地球への通行証を手にすることができます。
こういった、とてもユニークな設定の映画なのですが、本作の監督であるピート・ドクターは、前作『インサイド・ヘッド』においても、喜怒哀楽の感情がキャラクターとして人間のあたまの中に存在するという、とても変わった映画をつくっています。『ソウルフル・ワールド』では、「魂」「生きる目的」「才能」といった、抽象的な概念を見事にビジュアライズしているので、本作はある意味で、前作からの路線の延長線上にあるとも言えると思います。
とはいえ、ふと「人間をビジュアライズする」という設定だけを取り出して考えると、「そんなことって、そもそもできるのかな」と思ってしまう人もいるのではないでしょうか。ぼく自身、『インサイド・ヘッド』を観る前は、「それぞれキャラクター化できるほど人間の感情って、はっきり分かれているものじゃないんじゃないかな」と、ビジュアライズされることによってこぼれ落ちてしまうものがあるのではないかと考えていました。
いまとなっては『インサイド・ヘッド』も『ソウルフル・ワールド』も大好きな映画なのですが、その理由には、あくまでビジュアライズは手段であって、作品の主眼はストーリーに置かれているところにあると思います。
※以降、物語の結末に触れる箇所がありますので、鑑賞前の方はご注意ください。
『ソウルフル・ワールド』は、プロのジャズピアニストを夢見る主人公、ジョー・ガードナーが、晴れの舞台への出演が決まって浮き足立っていたところ、不運にもマンホールに落ちてしまい、ユーセミナーの世界へと迷い込んでしまうことから物語がはじまります。そこで、数百年の間もきらめきを見つけることができていない、「22番」と呼ばれる魂に出会います。
詳述は控えますが、22番がきらめきを見つけるためにジョーが奮闘する中で、ふとしたことで、22番とジョーの魂が地球へと降り立ち、22番がジョーの身体に入り込み、ジョーの魂が猫の身体に入り込んでしまうという展開が訪れます。そして、二人(もしくは1人と1匹)は、魂が入れ替わった身体のまま、ともにニューヨークの街で時間を過ごすのです。
その後、22番とジョーはユーセミナーへと連れ戻されるのですが、ふと22番の胸を見ると、7つ目のバッジが埋められているんですね。
22番が地球で過ごすことによって見つけたきらめきとは、空を見上げて歩くことであったり、手のひらに落ちてきた落ち葉に季節を感じること、ニューヨークの街の喧騒の中を歩くことなど、生活の一瞬一瞬に胸をときめかせるということでした。
主人公のジョーは、きらめきをもって生まれたからには、それを目的として生きるべきだと考えていました。彼にとってそれは音楽であり、ミュージシャンになることこそが生きる目的だったのですが、22番と過ごすことによって、きらめきを持って生まれることが、生きることの目的ではないということに気がつくのです。
もし、バッジを集めることのビジュアライズが軸となりストーリーが展開されるとすれば、22番の最後の胸のバッジにも、きっとなにかマークやかたちが与えられることになったのではないかと思います。でもこの映画では、それがどんなバッジなのかがわからないという結末が訪れる。つまり、「わかりやすい」ことを実現するビジュアライズを高いレベルでやってのけた後に、「わからない」ことへ帰結していき、それを肯定していくのです。そのことに、ピクサー映画のすばらしさと、考え抜かれたストーリーテリングへの畏怖のようなものを感じてしまいました。
もちろん、映画としてシンプルに楽しめる作品ではありますが、ビジュアライズされたものとストーリーテリングのあり方について考えみると、デザインの視点からも気づきがある映画なのではないかなと感じました。週末にぜひご覧ください。
(堀合 俊博)
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)




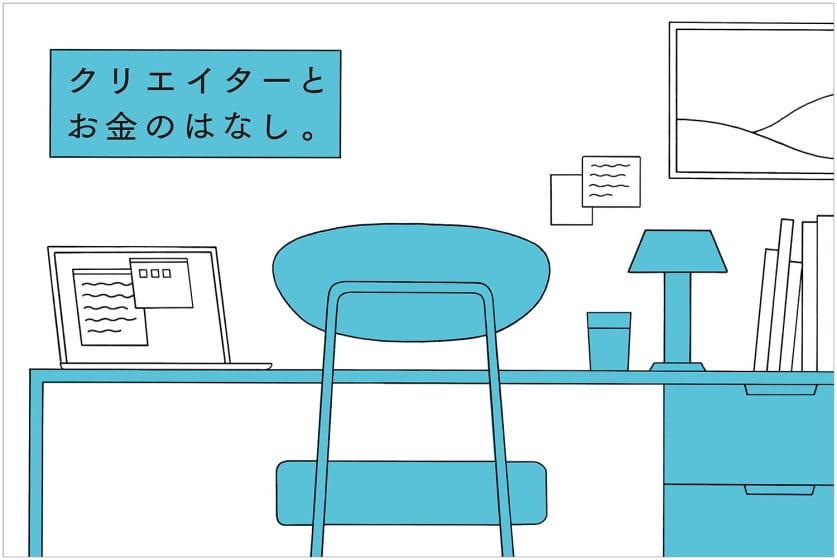




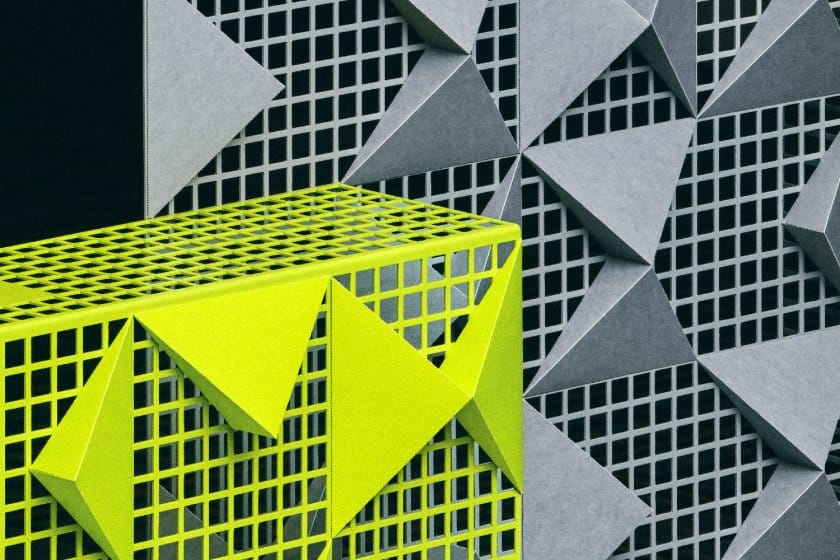

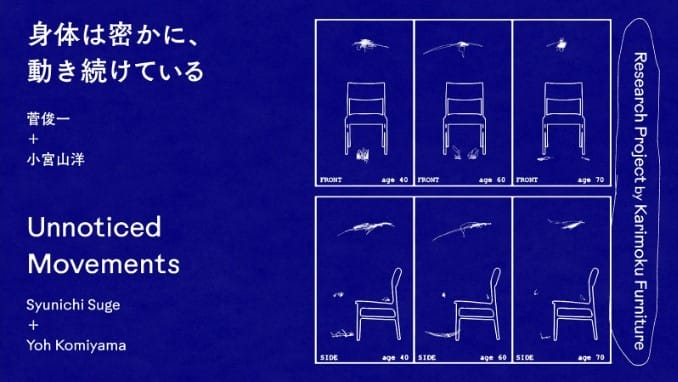

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




