9月26日、東京・半蔵門のLIFULL Tableにて、株式会社LIFULLのデザインポートフォリオサイト「LIFULL DESIGN」のローンチを記念した同社主催によるイベント「視点のセッション」が行われた。
「LIFULL DESIGN」は、不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」をはじめ暮らしや人生にまつわる様々な事業を運営する同社の幅広いクリエイティブを紹介するために制作したもの。今回のイベントでは、LIFULLの企業CMのコンセプトである「しなきゃ、なんてない。」に示されるような、既成概念や常識にとらわれないクリエイションを生み出している異分野のクリエイターたちをゲストに、新しい価値観のクリエイティブやデザインについて語り合った。

業界への問題意識と愛が、新しい価値観を生んでいく

加藤久哉
クリエイティブプロデューサー。ワシントンD.C.生まれ、滋賀県育ち。複数の名刺で活動する。広告/映像プロデューサーとしては、CannesLions等の世界の主要な広告賞でグランプリ含む220以上の賞を9年連続して受賞。
セッション1「既成概念にとらわれない発想から生み出す、事業クリエイティブ」では、建築家で建築事務所noiz代表の豊田啓介さん、テクニカルディレクター・コレクティブBASSDRUM代表のテクニカルディレクター清水幹太さん、LIFULLのCCO(チーフクリエイティブオフィサー)を務める川嵜鋼平さんが登壇。モデレーターは、Elnido代表のクリエイティブプロデューサー加藤久哉さんが務めた。

清水幹太
テクニカルディレクター。東京都生まれ。DTPオペレーター・デザイナーなどを経て、独学でプログラムを学んでプログラマーに。2005年よりインタラクティブ制作に転身、クリエイティブ・ディレクター/テクニカル・ディレクターとして様々なフィールドに渡る企画・制作に関わる。PARTYチーフ・テクノロジー・オフィサーを経て、2013年、PARTY NYを設立。2018年テクニカルディレクター・コレクティブBASSDRUM(https://bassdrum.org/)を設立。
清水さんは、自らの肩書きであるテクニカルディレクターの仕事を、“しゃべれる技術者”と定義。コンセプトやビジネスをつくるクリエイティブと、それを具体的にかたちにしていくテクノロジー、その両方の言語を理解した上で翻訳すことが仕事だと紹介した。「何にでもテクノロジーを使う社会になってきているので、開発をスムーズに進めるためには、テクニカルディレクターがプロジェクトにおける技術的な面を横断的にカバーする必要があると思うんです。BASSDRUMを立ち上げたのは、コミュニティをつくることで技術者が司令塔になることができ、エンジニアの地位や発言力を向上させて、クリエイティブのコンセプトに対して、テクニカルのコンセプトを定義する役割を社会に定着させたいと考えたからです」。

豊田啓介
建築家。東京大学工学部建築学科卒業。1996年から2000年まで安藤忠雄建築研究所。2002年コロンビア大学建築学部修士課程修了(AAD)、2006年までSHoP Architects(New York)。2007年より東京と台北をベースに、蔡佳萱と共同でnoizを主宰(2016年より酒井康介もパートナー)。2017年より建築・都市文脈でのコンサルティングプラットフォーム『gluon』を金田充弘、黒田哲二と共同主宰。東京藝術大学芸術情報センター非常勤講師、慶応大学SFC環境情報学部非常勤講師、EXPO OSAKA/KANSAI2025招致会場計画アドバイザー。
豊田さんは、noizでの活動や、テック/コンサルティングの領域横断型プラットフォーム『gluon』の活動を例に、建築とデジタル技術を融合し、従来の設計と施工のプロセスを変化させて新たな価値体験を提供しているコンピューテショナルデザインについて語る。「デジタル技術の可能性は、設計の前段階の企画や、施工の後の運営がシームレスにつながって、従来一元的に流れていった建築の行程をシャッフルさせることで、新しい価値体験を提供できること。そうした中で、必ずしも僕らのアウトプットが設計や建築である必要はなくなっていきました。事務所にも、さまざまな領域を専門とする人材がグラデーションのように集まっていて、異分野とコラボレーションをする仕事が増えましたね」。

川嵜鋼平
1981年生まれ。2017年LIFULL入社。執行役員CCOとして、ブランド・プロダクト・コミュニケーション・研究開発・新規事業など、グループ全体のクリエイティブを統括。またクリエイティブ組織の戦略策定・育成・採用など、組織づくりも担う。カンヌライオンズ金賞、文化庁メディア芸術祭優秀賞を始め、国内外の160以上のデザイン・広告賞を受賞。
川嵜さんは、LIFULLのデザイン戦略である「Think, Make and Do.」について紹介し、社会問題と向き合う中でのデザインの役割について語った。「クリエイティブの本質は社会や暮らしをよりよくするものであると考えています。手つかずの問題に対して、クリエイティブ視点で社会課題と向き合い、新しい価値をデザインしていくためには、デザイナーが常識にとらわれない新しい選択をしていく必要がある。そうすることで、“あらゆるLIFEを、FULLに。”にできるのではないかというのが、僕らが掲げているフィロソフィーに込められています」。
加藤さんからは、テーマである「既成概念」を飛び越えた瞬間や、ターニングポイントについてそれぞれに質問が投げかけられた。豊田さんは、「特に意識していなかった」とこれまでの仕事を振り返った。「アウトプットが分子構造でもいいかなと、思いついたり、いろんなアイデアで遊んでいるうちに、デジタル領域を育てていこうかなと考えるようになったんです。その後、デジタル技術と企業をつなぐような相談を受けるようになり、次第に企業のあり方自体を考えるコンサルティングを請け負うようにもなりました。gluonを立ち上げたのも、建築ではなくて企業の方向性を考える機会が増えたからですね」。
清水さんも同じく、職業の枠を飛び越えた意識がなかったと語る。「デジタルの仕事に関われるならなんでもやってみようと思って飛び込んだのが、たまたま広告だったんです。だから最初から垣根を設けていなくて、広告以外の仕事をするようになった時も特に抵抗はなかったですね」。

セッションは、建築家やエンジニアのキャリアパスについての議論につながっていった。業界の“既成概念”を変えていくことが、いかに建築と広告の業界で人材としての価値を高めていくかという点について、豊田さんと清水さんは議論を交わす。
「そもそも建築業界は賃金レベルが低い業界。同じ内容の提案をしたとしても、歴史の長い建築業界よりも新しいクリエイティブ業界のほうがチャージが高いんですよ。同じように、設計事務所よりもコンサルティング事務所の方がチャージが高くて、そこに大きな違いが出てしまうと思います」(豊田さん)
「エンジニアは、プログラマーだとずっと作業者の扱いですが、テクニカルディレクターとしてコミュニケーションやコンサルティングの領域までカバーできると、プログラマーの仕事の価値が変わってくると思います。テクノロジーが関わらない領域が少なくなっていく社会で、テクニカルディレクターの賃金レベルを上げていかないと、世の中自体がよくならないと思っています」(清水さん)
セッションの締め括りに語られたのは、領域を横断していくことの根底にある、業界への愛だった。業界の慣例や、既存の考え方に留まらない価値を提示することこそが、業界の活性化に繋がるということ。それぞれの仕事、戦い方について三者は語った。

「デジタル広告のスピード感やコミュニケーションの中で育てられてきたので、広告業界に愛着はありますが、内側で馴れ合った関係のままいるのはつまらないなと感じます。なので、これまで違う角度で戦ってきましたし、愛があるゆえに外圧をかけているんです」(清水さん)
「建築への愛があって、建築に可能性を感じるので、軸足は常に建築に置いているんですが、大企業が多いこの業界では、まだ閉じた価値観が主流になってしまっているのを感じます。未知の領域への実験や遊びを評価するような、まだ価値判断ができないことに、新たな価値を感じるような方向へ、発想を転換させることを意識してやっていきたいですね」(豊田さん)
「広告業界に長くいる中で、広告賞を受賞したソーシャルグッドなプロジェクトでも、継続していないものが少なくない現状をみていると、真剣に社会課題を解決するためには、継続にこそ価値があるんじゃないかなと考えるようになりました。社会を変えようという思いを軸に、自分なりに深く取り組み続けることで、既成概念を超えられるじゃないかなと思います」(川嵜さん)
「しなきゃ」を飛び越える、常識との向き合い方

セッション2「デザインの常識を超える、新しい時代のデザインプロセス」では、monom/YOYを主宰するクリエイティブディレクター・プロダクトデザイナーの小野直紀さん、H Inc.代表のインターフェースデザイナー・アートディレクターの長谷川弘佳さん、LIFULLアートディレクターの三宅太門さんが登壇。それぞれがこれまで手がけた仕事の例から、常識にとらわれない仕事やものづくりのプロセスについて語り合う場となった。セッション1に引き続き、モデレーターを務めたのは加藤さん。

小野直紀
『広告』編集長/クリエイティブディレクター/プロダクトデザイナー。1981年生まれ。2008年博報堂入社。2015年に博報堂社内でプロダクト開発に特化したクリエイティブチーム「monom(モノム)」を設立。社外ではデザインスタジオ「YOY(ヨイ)」を主宰。その作品はMoMAをはじめ世界中で販売され、国際的なアワードを多数受賞している。2015年より武蔵野美術大学非常勤講師、2018年にはカンヌライオンズのプロダクトデザイン部門審査員を務める。2019年より博報堂が発行する雑誌『広告』の編集長に就任。
プロダクトデザインと事業開発をチームで行うmonom、まだ世の中にない家具や照明などをつくるデザインスタジオYOY、さらに雑誌『広告』の編集長を務める小野さん。セッションでは、monomで制作したボタンのかたちをしたぬいぐるみ用スピーカー「Pechat」のデザインプロセスを紹介し、プロダクトをデザインする上で体験を「シンボリック」に見せるためのビジュアルや印象づくりと、プロダクトをいかに生活の中になじませるか=「アダプティブ」の大切さについて語った。「もともと僕はコピーライターもしていたので、コミュニケーションとプロダクトをセットで取り組んでいるんです。デザインの領域を意識するのではなくて、ものづくりという全体像の中で何ができるかをとても大事にしていて、“体験から感情を創出する”専門家でありたいなと思っています」。

長谷川弘佳
アートディレクター、 インターフェース/グラフィックデザイナー。1986年生まれ。多摩美術大学美術学部情報デザイン学科卒業。博報堂i-studio、mount inc.を経て2017年、HIROKA HASEGAWA DESIGN設立。プロダクトデザイナー&クリエイティブディレクターの早川和彦とともにH Inc.を設立し、平面・立体を問わず、様々なデザインの仕事を行う。
長谷川さんは、H Inc.の設立以降、デザインだけではなく、クリエイティブディレクションや、インフォメーションアーキテクト、ビジネスモデルの策定など、仕事の領域が広がってきている現状について語る。セッションのテーマである「常識を超えるデザイン」を受けて、新しい開発プロセスの提案を化粧品ブランド「AGILE COSMETICS PROJECT」について紹介した。「もともとパッケージデザインとアートディレクションの依頼だったんですが、ブランドのビジネス戦略から開発することになりました。この化粧品は、スマホのようにバージョンアップしていくという、アジャイル開発の発想を取り入れていて、この考え方や仕組み自体の提案から携わっています」。

三宅太門
2018年3月に株式会社LIFULLに入社。LIFULLのブランドデザインを統括するグループで、アートディレクターとして従事。デジタル、プリント、空間など領域問わず、課題解決のためのデザインを行う。
LIFULLのブランドデザインチームに所属し、これまで大小20以上のプロジェクトのデザインとアートディレクションを手がけてきた三宅さん。公開されたばかりの「LIFULL DESIGN」では、多岐にわたるLIFULLのプロジェクトを紹介するにあたって、シンボルマークである「L Focus」を軸に、サイト内で視点を変える体験を再現し、ひとつひとつの社会課題に対するLIFULLの姿勢を表現したという。「L Focusは、ぼやけていたものが明確になることや、本質を捉えるという意味を込めていて、それらをサイト内のインタラクションとして表現しています。LIFULLではブランドの目的意識を表現するブランドデザインガイドラインを設けていて、“モストダイバース”をコンセプトにしています。あらゆる境界線を超える生き方、逆に超えない生き方も肯定し、それぞれの生き方を導くブランドになっていきたいといと考えています」。
セッション2のテーマである「常識」について加藤さんは、「普段制作する上で、“常識”を意識されることはありますか?」と質問。小野さんは、博報堂の広報誌として1円で販売した『広告』について、“広報誌を値付けする”という常識を外した試みを例に、常識への考えを語る。「常識というのは大事にしていますね。常識というものがあってこそ、“常識じゃないもの”が見えてくるので。常識と、その反対としての非常識という分け方ではなくて、“未常識”といういつか常識になりえるものをポジティブに考える視点として、デザインが寄与する可能性があるのかなと思います」。続けて三宅さんも、常識との向き合い方について語った。「広告とサービスをつくっていく上で常識の重要性は感じてはいる一方で、常識を越えていくことにクリエイティブとしての豊かさを感じますね」。

「これまでの働き方やアウトプットのプロセスで、かかわる領域が増えたきっかけはなんでしたか?」と、三宅さんから長谷川さんに質問する場面も。「あまり領域を広げようと意識したわけではなくて、そのほうがいいからという考えたたらこうなったんじゃないかなと思います」と答える長谷川さんは、独立後に感じた心境の変化について話した。「会社に所属しているときは、自分の発言が会社の発言になってしまうということを意識するあまり、うまく話せなくなってしまう場面があったんです。独立することで自分の責任で発言できるようになったことが、その後の領域の拡大につながった気がします」。
会場からは、デザインする上での常識のはずし方の難しさについてどう考えるか質問が上がった。小野さんは、「常識を外すことで社会にメッセージを伝えたり、それが力を持つことがあると思うので、そのことには前向きに取り組みたいと思いますが、常識を外すことは目的ではなく、あくまで手段としています」と答える。三宅さんも、LIFULLのブランディングを実践していく中で、常識を外すことが目的化してしまうことの危険性について話した。「なにか突飛なことをするというより、同じ姿勢と価値観を積み上げていくことがブランディングなんだと思います。常識から外れることを目的にしてしまうと、軸がずれてしまったり、それが“一瞬の打ち上げ花火”で終わってしまうこともあると思います」。
2つのセッションを通して、加藤さんは複数の肩書きを持つ未来について語る。「まだスタンダートとは言えないにしろ、職業の枠を越境する人たちがいることが当たり前になる社会に、これから向かっていくんじゃないかなと思います」。LIFULLのコンセプトである「しなきゃ、なんてない。」ということばの通り、イベントを通して常識であること=「しなきゃ」を越える議論が交わされた時間となった。

文:木村早苗 写真:木澤淳一郎 編集:堀合俊博(JDN)
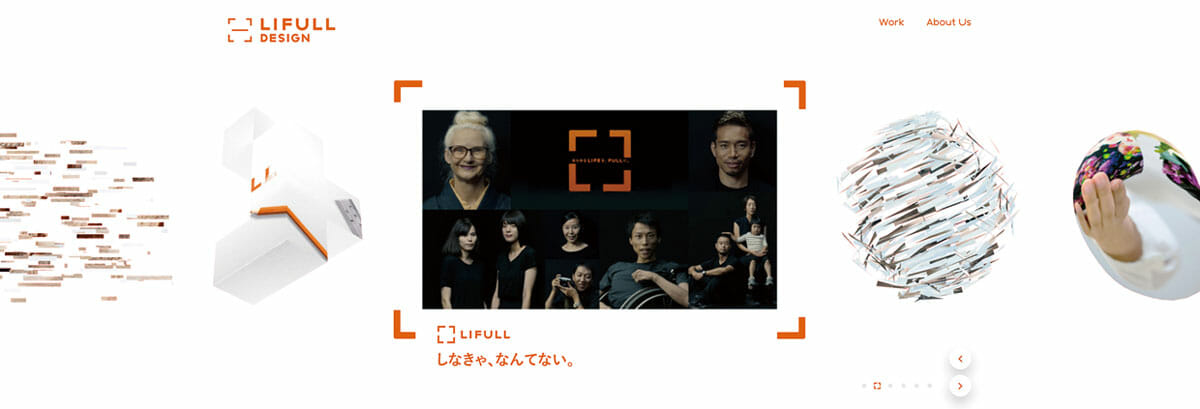
株式会社LIFULLのデザインポートフォリオサイトでは、不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」や旬の花の定期便「LIFULL FLOWER」、空き家問題に取り組む「LIFULL 地方創生」、地球の新たな食材を見つける「地球料理-Earth Cuisine-」など、暮らしや人生にまつわる様々な事業を運営する同社の幅広いクリエイティブを紹介しています。
多岐にわたるプロジェクトを一覧することで、「あらゆるLIFEを、FULLに。」というLIFULLのコーポレートメッセージを感じることができるサイトです。
LIFULL デザインポートフォリオサイト
https://design.lifull.com/
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

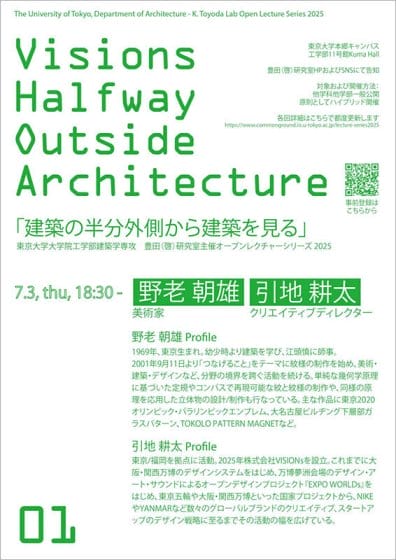

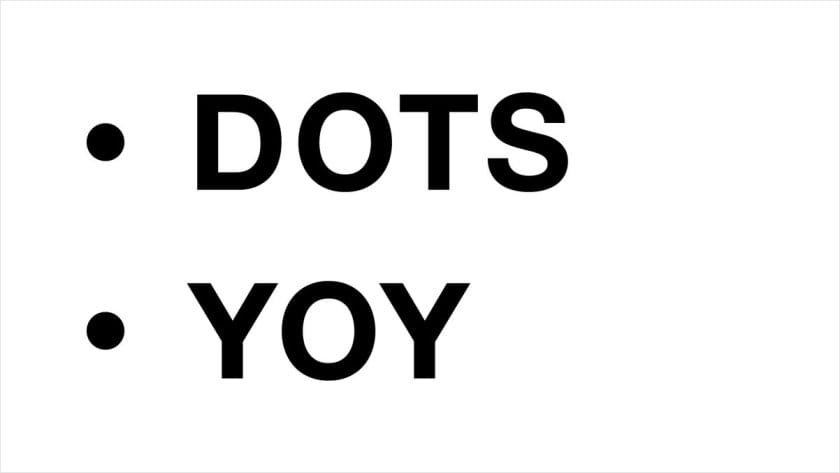






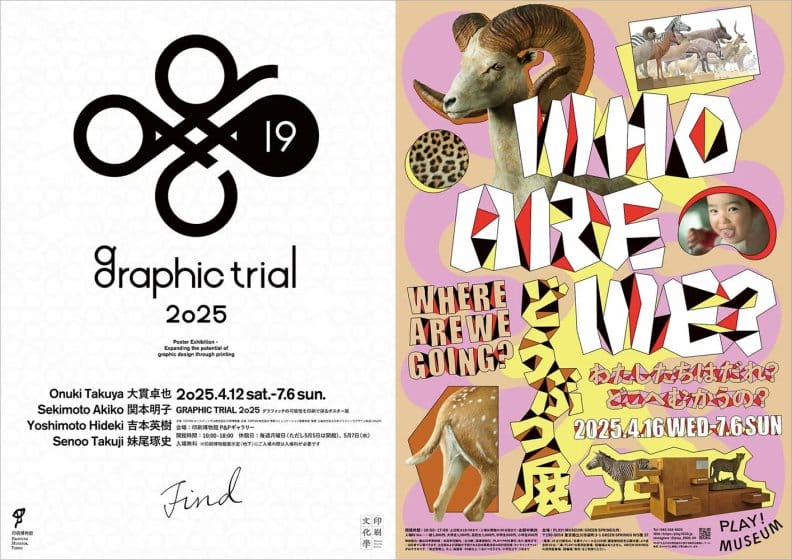




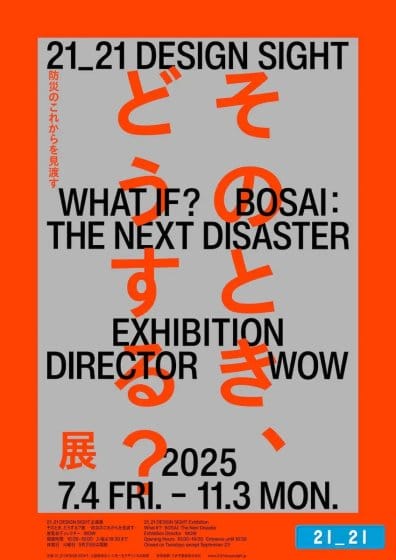
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




