次世代のクリエイターの支援・育成を通じてより良い未来を共につくり上げることを目的に毎年開催している「LEXUS DESIGN AWARD」の公募締切が、10月16日に迫っている。
LEXUS DESIGN AWARDは2013年にスタートし、今年で11回目を迎える国際デザインコンペティション。前回は57の国と地域から1,726作品もの応募があり、世界中の次世代のクリエイターが目指すプラットフォームとなっている。
公募で選出された受賞者は、アイデアを具現化するためのリサーチ、プロトタイプ制作などのプロジェクト費用として最大300万円の支援を受けられるほか、作品を世界に向けて発信する機会が用意されるなど、さまざまな賞典がある。中でも、世界的に活躍するクリエイターによるメンタリングが同アワードの最大の特徴。受賞者はメンターからのアドバイスを受けながら作品をブラッシュアップし、最終発表に挑むという制度が導入されている。

LEXUS DESIGN AWARD 2022 ポー・ユン・ルーによるグランプリ作品「Rewind」。
今年、そのメンターの一人として、ロンドンを拠点に活動する日本人デザイナー、世界最大のインディペンデントデザイン事務所ペンタグラムのパートナーであり、サウンド・アーティストのスズキユウリさんの参加が決定。本記事の1ページ目では、スズキさんの経歴や現在の活動、コロナ禍で変化した自身のテーマ、作品に対する気持ちの変化などについて着目。2ページ目では、LEXUS DESIGN AWARDに抱く印象やメンターとしての向き合い方、期待することなどについてお話しいただいた。
音楽活動を経て、サウンドアーティストとして世界へ
――まずは、スズキさんの経歴について教えてください。
音を軸にデザインや作品づくりをしています。作品は、インスタレーションに限らず、音のデザインや音にまるわるプロダクトなどさまざまです。現在はロンドンを拠点に、デザイン事務所ペンタグラムのパートナーとして、企業とのコラボレーションやアート作品の制作を行っています。

スズキユウリ サウンドアーティスト、エクスペリエンスデザイナー。1999~2005年までアートユニット明和電機に所属後、イギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)修士課程卒業。スウェーデンの楽器メーカーのティーンエンジニアリングやディズニーのリサーチ部門の在籍を経て、2008年Yuri Suzuki Ltd.を設立。2018年より世界最大のインディペンデントデザイン事務所ペンタグラムのパートナーに就任。https://yurisuzuki.com/
――デザイナーとして活動する前は、音楽活動をされていたとうかがっています。その当時のお話も少しうかがえますか?
はい、1999~2005年までアートユニットの明和電機のアシスタント(工員)として活動していました。高校は、クラスの4分の1がバンドをやっているくらい音楽活動が有名な和光高校に通っていました。僕は明和電機が好きで、コピーバンドをしていたんです。自分で楽器をつくって活動していたところ、明和電機の土佐正道さんと土佐信道さんのおふたりが興味を持って声をかけてくれたのがきっかけです。
その後、イギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)で学んだ後、スウェーデンの楽器メーカーのティーンエンジニアリングやディズニーのリサーチ部門に勤務し、2008年に独立して、個人活動をしていました。
――スズキさんの代表作を教えてもらえますか?
歴史をたどっていくと、「Breakfast Machine」は国内外で人気があったり、DIY楽器「OTOTO」もMoMAの永久保存コレクションに選出されたり、「Tube Map Radio」も人気がありましたね。コラボレーションだと、デトロイトテクノのパイオニアであるJeff Millsと一緒に取り組んでRolandのドラムマシンTR-909を再構築した「The Visitor」などでしょうか。
作風の転換期となったコロナ禍
――コロナ禍で作風への影響はありますか?
作品に影響はありましたね。コロナ禍で、Webとインスタレーションのハイブリッドのようなことを考えはじめました。2019年に、アメリカのダラス美術館のために制作した「Sound of the Earth:Chapter 2」のツアーをするはずでしたが、コロナ禍でキャンセルになったんです。
そこで担当者から、「実際に行けなくても、Web上で追体験できるようなことって考えられない?」と言われて、つくったのが「Sound of the Earth: The Pandemic Chapter」です。その影響は、そのあとの作品や企業でのコラボレーションにもあり、現在も続いています。前述同様、転換期というか方向性が見えたタイミングでした。
――コロナ禍で仕事に変化はありましたか?
コロナ禍で仕事が停滞したという人が多く聞かれましたが、僕はむしろ忙しく、デジタルベースの作品など、コロナがきっかけで作品も増えました。あとは、企業から音に関する依頼案件が急増して、音に関するプロジェクトが多かったのも特徴です。コロナは、世の中の音に関する認知度が上がるきっかけにもなったと思います。個人的な感覚でいうと、ひとつの空間にいる時間が格段に増えたことにより、音の重要性が上がったからではないかと考えています。
デザイナーが温めているアイデアを一緒に育ててくれるアワード
――スズキさんは今回はじめてLEXUS DESIGN AWARDのメンターとして参加されますが、アワードにはどんな印象をお持ちですか?
世界のデザイナーの登竜門と言えますし、非常に意味のあるアワードだなという印象があります。2013年から長く続いていて、プログラムもしっかりしていて、デザイナーをここまでサポートしてくれるアワードもなかなかないと思います。
あと、LEXUS DESIGN AWARDは完成された作品を評価するというよりも、デザイナーが日々大事に温めているアイデアを、いろいろなメンターの意見を取り入れて、育てて共につくり上げていくというイメージです。あらゆるデザイナーにチャンスを与えて、いいところを見つけ、その種を育てていくようなプロセスがきちんと考えられている。
メンターやLEXUS DESIGN AWARDに関わっている方々が、デザイナーを育てようという想いをきちんと持っている貴重なアワードだなと、過去の作品を見てもそう思いました。僕の学生時代にもこんなアワードがあったら嬉しかったですね。
――主催者側がそういう積極性を持っているのはアワードにとって大事なことですよね。では、今回スズキさんがメンターを引き受けた理由を教えてください。
引き受けたのは、アワードのシステムがすごく良いと感じたことが大きいです。もちろんみんなが応募できるという懐の広さは希少ですよね。
――スズキさんは、RCAで教鞭を取った経験もお持ちですが、メンターとして受賞者に教えるという立場についてはどう考えていますか?
RCAにいた時は、「教えている」という感覚はなく、学生と対等に意見をぶつけあう感じでした。学生の中にはすでにいいデザイナーは何人もいたし、彼らの方がいいアイデアを出すことだってある。教えるというよりは、いろいろと意見を聞き、フィードバックするという感じでしたね。
LEXUS DESIGN AWARDも同じで、メンターとして対等にデザイナーやクリエイターが意見を交わす場にできたらと考えています。アワードで入賞している時点で、すでにかなりいいものを持っていると思いますし。
- 1
- 2
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)















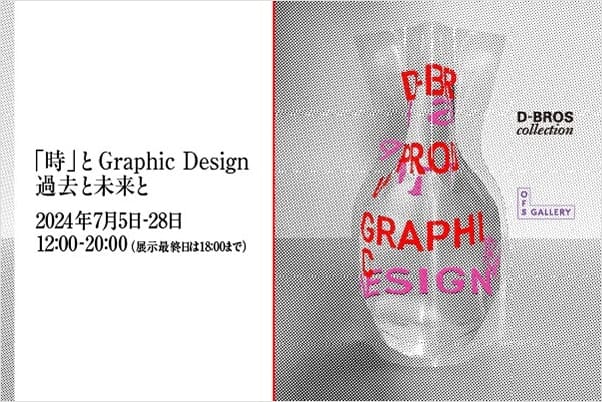

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




