外部とのコラボレーションでマーケットを広げる
——オルテラインのチームの編成を教えてください。
大田:デザイナー、「デサント ブラン(オルテラインの商品を販売するデサントブランドの直営店)」のディレクター、プレス、企画アシスタント、それからMD兼グローバルセールスの僕。決して人数は多くない小さな部隊です。
山田:チームは小規模なほうが動きやすいですよ。MDをしながら営業ができるのも大きな強みだと思います。ふつうの営業は、できあがった商品を受け取るところからスタートしますが、MDもやっていればどんな経緯で商品がつくられていったのかを見てきているわけですから。
大田:どうしてその生地が選ばれたのかなんて、営業だけをやっていたら知る機会がないですし。
山田:企画からはじまって、生産したものを営業が売り込み、店舗に並べ、お客さまに届くという過程にはいろんな人が関わります。その人数が少ないほど、企画当初のメッセージがお客さまに伝わりやすい。そこも小さなチームの利点だと思います。

——オルテラインはほかのブランドとも多くコラボレーションしてきました。そこから得られたことを教えてください。
山田:コラボレーションをする際には、ファッションブランドのデザイナーと意見を交わすことになります。トレンドの話には弱いのですが、機能については僕らの専売特許のようなもの。お互いに知らない情報を交換できることは、コラボレーションの大きなメリットです。
もともと、機能性に特化したものづくりは、アパレル以外にももっと広げられるんじゃないかと思っていて。それは、ノウハウのない自分たちだけでは難しいけれど、鞄は吉田カバンの「PORTER(ポーター)」と、シューズは「SUICOKE(スイコック)」というようにコラボレーションすることで実現できました。一方がテイストを寄せることはせず、一緒にイチからプロダクトをつくり出すというやり方をしています。他ジャンルの人と組んで得た知識や経験を持ち帰って、自分たちのものづくりに応用したりできるので、すごく刺激的ですね。
大田:営業の視点では、新しいマーケットにアプローチできることも大きなメリットです。たとえば、ウィメンズのファッションブランド「mame(マメ)」とのコラボレーションでは、機能的な素材やディテールを扱いつつ、mameが得意とするカラーパレットやディテール、シルエットをうまく融合しながらコレクションをつくりました。オルテラインのようなテックウェアはどうしてもメンズのイメージが強く、女性にアプローチしづらいところがあるなかで、このコラボが女性に広く知ってもらうきっかけになったと思います。

コンセプトを視覚化し、新たな購入体験を生み出した店舗空間
——直営店の「DESCENTE BLANC(デサント ブラン)」は、商品の在庫を天井から吊るしていたりと、独特の空間デザインです。店舗のデザインを手がけられた長坂常さん(スキーマ建築計画)とはどのようなやり取りをされたのですか?
山田:実は長坂さんはもともと水沢ダウンを愛用してくださっていました。お会いしてオルテラインのコンセプトを説明したところ、私たちの考え方を理解していてくださっていて、「お店だけどそこに余計なものはいらないね」とおっしゃっていました。
いざ内装ができあがり、商品を搬入する前に見に行ったら、壁や天井がむき出しになっていて……すごく驚きました(笑)。ふつうの店舗は商品が置いてなくても成立する空間デザインになっていますよね。でも長坂さんは商品が並ぶことではじめて完成するようにつくってくださった。逆に言えば、商品が主役の空間なんです。

デサント ブラン 代官山店
大田:長坂さんが、ストックルームを設けずに在庫を天井の昇降ラックで吊るすことにしたのは、主役である洋服を隠さないようにしたいから。それから、接客のあり方を変えたいという思いもあったそうです。従来の接客スタイルだと、店員さんと話をしたうえで、もし自分のほしいサイズがあるか店員さんがストックルームに確認しに行って、在庫を手に戻ってくるという時間が生まれます。その間にお客さんが冷静になって「やっぱりやめておこうかな」となってしまうのがすごくもったいないと。天井から降りてくる光景を引っくるめて、ジャケットを1着買う以上の購入体験ができるというアイデアはすばらしいと思いました。
山田:オルテラインのものづくりの考え方をうまくすくいあげ、わかりやすく表現してもらえたことがうれしいです。
——オルテラインでは毎シーズン、カタログ冊子をつくっていますよね。Webのみでラインナップを見せるブランドも多いなか、あえて紙媒体をつくるのはなぜですか?
山田:形に残るものがほしくて。よく漫画の単行本で、並べると背表紙の絵がつながってひとつの絵柄になるものがありますよね?ああいうことをオルテラインでもやってみたいのです(笑)。何十年後かに見て、「オルテラインは変わらないな」と思いたい。それに、1着10万円するものを買おうと思った人は入念に下調べをするはずなので、情報をなるべく多く発信したいなと。店に入ってパッと買うのではなく、車を買うときのようにいろんな商品を比較検討してもらうということを目指しているんです。だから、時代錯誤かもしれないけれど、いまだに紙のカタログをつくり続けています。

世界をシームレスにつなぐ場をつくりたい
——オルテラインがこれから目指す姿はどのようなものですか?
山田:僕が突き詰めている「シンプル」には、ゴールがないなと感じています。“Simple”って、和訳すると「単純」や「簡素」ですが、それはちょっと違うんじゃないかと思っていて。もしかしたら「最適」とかのほうが近いのかもしれない。シンプルにしていこうと思うと終わりが見えないので、ロングスパンで「オルテラインをこうしていきたい」という展望は描いていません。それよりも、ワンシーズンごとに、着実にシンプルさを追求していきたいと考えています。そうやってキャリアを積んでいくうちに新しいテクニックが身についていき、できることが増えていく。もちろん世の中の技術も進歩していくでしょうから、それまでできなかったことができるようになるはずです。
大田:常に新しいものをつくり続けるとともに、よりたくさんの人に届けるためにプラットフォームを広げていきたいと考えています。海外のお客さんに、「日本のデサント ブランに行ったよ。あれはすごいね!」と言ってもらえることも多くなりました。ものづくりをしているだけでは幅広く伝えることは難しいので、実店舗などで商品をいかに上手に、魅力的に見せるかがすごく重要だと思います。
オルテラインのソリッドな商品は、ほかの洋服やアイテムと組み合わせることで、より機能性が際立ってきます。いまはそれを提案できる直営店が日本にしかないので、海外にも広げていきたい。デサントの店舗が世界のいろんな都市にあれば、国境を超えて相互作用が生まれたり、海外での成果を日本国内で応用できたりすることもあると思います。そうやって、各国をシームレスにつなぐ場をつくりたいですね。
山田:オルテラインの商品自体は、現在20カ国以上で販売しています。おもしろいのが、置いてもらっている店のテイストがばらばらなんです。ハイブランドを中心に扱っている店もあれば、ウッディな内装のカジュアルなセレクトショップもある。それは、オルテラインのアイテムは見た目の主張が強くないので、どんな場所にもなじむからだと思います。だからこそ、いろんな国に広げられる可能性がある。オルテラインの機能性を、もっと多くの人に知ってもらえたらうれしいです。
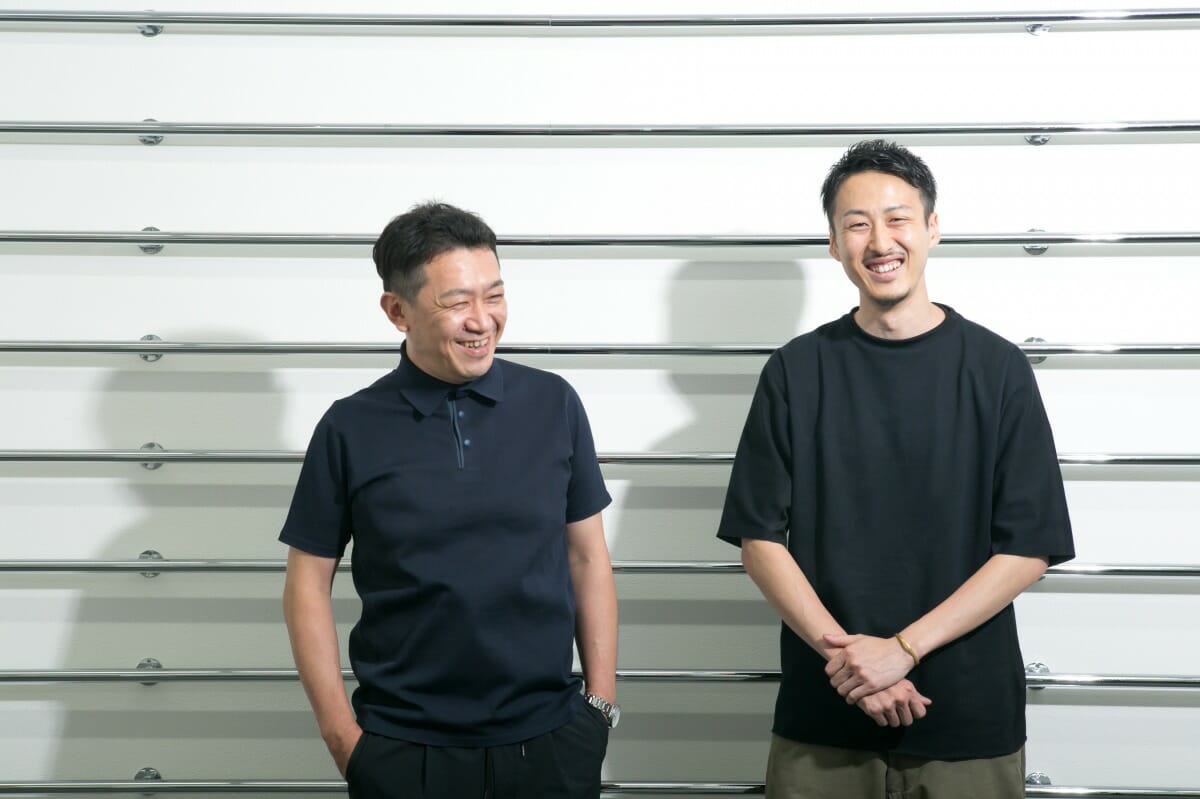
撮影:中川良輔 取材・文:平林理奈 編集:瀬尾陽(JDN)
- 1
- 2
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)



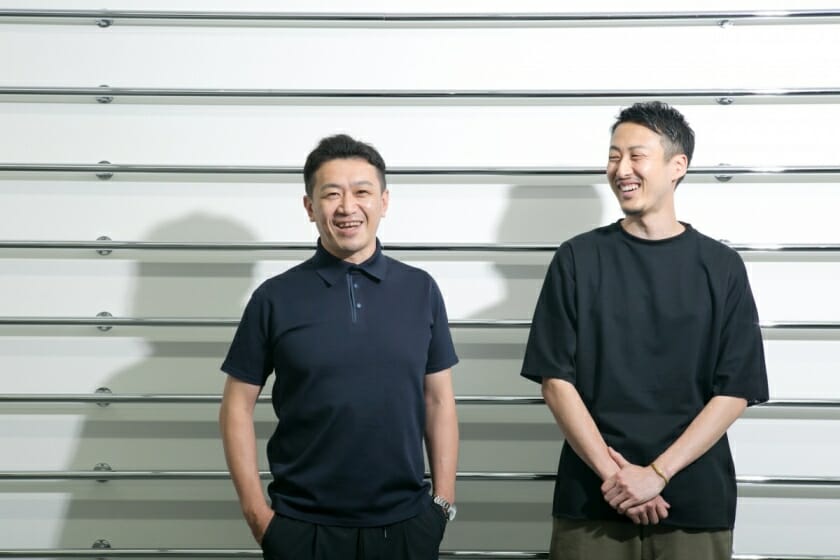









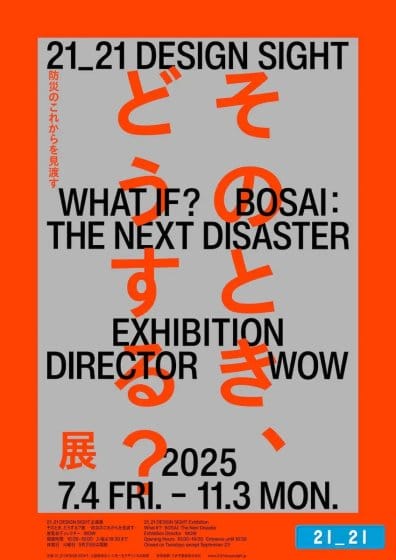
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




