幸福の解体新書-はじめに(前編)

読者のみなさんはじめまして。コンセプトを軸とした企業やサービスのブランディングコーチをしているさわくんです。
弊社はクリエイティブ×ブランディングの能力を用いて、企業やサービスを『コンセプティング』している、コンセプトメイクカンパニーです。インナーとアウターを切り分けることなく、両者の起源となる「コンセプト」を見出すことに主眼を置きながら、法人やサービスが自然と躍動していくような、クリエイティブ×ブランディングサービスをおこなっています。
そのような会社で私はCCOを担っています。CEOやCOO、CHROなどは小耳に挟んだことがあるかもしれませんが、私の場合はCCO(Chief Concept Officer)です。
文字通り、「コンセプト」についてめっちゃ詳しく、かつめっちゃ取り扱いがうまい人間ということになります。という説明をしたところで、「ここでいう『コンセプト』って何?」「そもそも、そんなCCOがなんで『幸福論を解体する』なんていう怪しいコラムを書くんだ?」などと無限に疑問が湧いてきているのではないでしょうか。
そんな方のために、今回は、
・コンセプト≒幸福という話
・幸福をクリエイターが学ぶ重要性
・幸福を学ぶ手段は、幸福を疑うことによって成せる
という話をしていこうと思います。これらの話をすることで、上記の疑問に解答できるはずですので、しばしお付き合いいただければ幸いです。
クリエイターとは、企業や個人の「幸福のクオリア」を形にする仕事だ
おそらく読者のみなさんは、「なぜ、デザイン情報メディアで幸福論などという胡散臭い話を連載するのだろうか。そもそも全然関係ないではないか」と、思っているのではないでしょうか。私も読者だったらそう思います。疑問を持たれた方に向けて、今回は「クリエイターこそ最も幸福論について詳しくなければいけない」理由について解き明かしていきます。
結論から先に述べさせていただきます。
クリエイターとは企業や個人の「幸福のクオリア」を形にする仕事であり、その仕事のプロフェッショナリティはデザインやコピーなどのクリエイティブスキルよりも、「幸福のクオリア」≒コンセプトに対する解像度の高さに宿る。ゆえに、クリエイターはコンセプトの軸となる人々の幸福について深く知っておく必要がある。以上のように私は考えています。
「クオリア」とは主観的な経験や感覚の質のことを指します。
たとえば「赤」という単語を耳にしたとき、意味としての「赤」だけではなくバラや夕焼けの赤というイメージが広がり、そこに付随した香りや温度などの五感的感覚が付随してくるはずです。そこで感じるイメージや感覚は、その人がこれまでの人生で体験した出来事によって変化する、個々人によって性質が大きく異なる主観的なものになります。そのため、ただ「文字情報」を把握するだけではなく、その質感までも捉える必要があります。

クリエイターの仕事はクリエイトの意味の通り、「何かを生み出すこと」にあります。デザイン、コピー、写真。その人の持つスキルを生かして顧客のイメージを創造することがクリエイティブです。ここで肝心なのは「何を軸に生み出すのか」ということなのです。
たとえば、採用ブランディングの世界で考えてみましょう。弊社でよく依頼されるものに「採用サイト」があります。クリエイターの仕事はもちろん「採用サイトをつくる」ことです。ただし、いきなり「採用サイトをクリエイト」できるかといえばそうではありません。もし「採用サイトをつくって」と依頼をしてすぐに「はい、かしこまりました」と納品してくる業者がいたら、僕はあまりその会社はおすすめできないと思います。
なぜか。それを考えるには「いいサイト」とは何かを考える必要があります。
採用サイトの目的は「その会社にとって望ましい人物を採用できるよう、適切な情報訴求をする」ことにあるからです。では「望ましい人物とは何か」という話になるのですが、それは「今後の事業戦略」——すなわち「何をしていくのか」に紐付き、その「何をしていくのか」はその企業が「何を望んでいるか」に起因してきます。
そのため、究極的には「その会社とっての幸福は何だろうか」を考えないとクリエイティブはつくれないわけです。

今回述べたのは採用サイトですが、駅の中吊り広告やwebバナーもそうです。大元を辿っていくと、「その会社の望みとは何か」という部分に行き着きます。
会社の望み、すなわちその会社にとって何が幸福なのか。そこから逆算してすべてのクリエイティブが生み出されていくわけです。ここを踏まえずに何かをつくろうとすると、根本ではズレたものができてしまいます。
そして、冒頭で説明した「赤」に宿るクオリアも人それぞれであるとするならば、より抽象度の高い「幸福」に対するクオリアはもっと人によって異なることは自明でしょう。
これが、「クリエイターこそ最も幸福論について詳しくなければいけない」と冒頭に述べた理由となります。ここまでで、
・コンセプト≒幸福という話
・幸福をクリエイターが学ぶ重要性
の2点に関しては説明できたと思います。ですが、最後の「幸福を学ぶ手段は、幸福を疑うことによって成せる」の部分に関してはまだ述べられておりません。こちらは後編でじっくり語っていければと思います。
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)
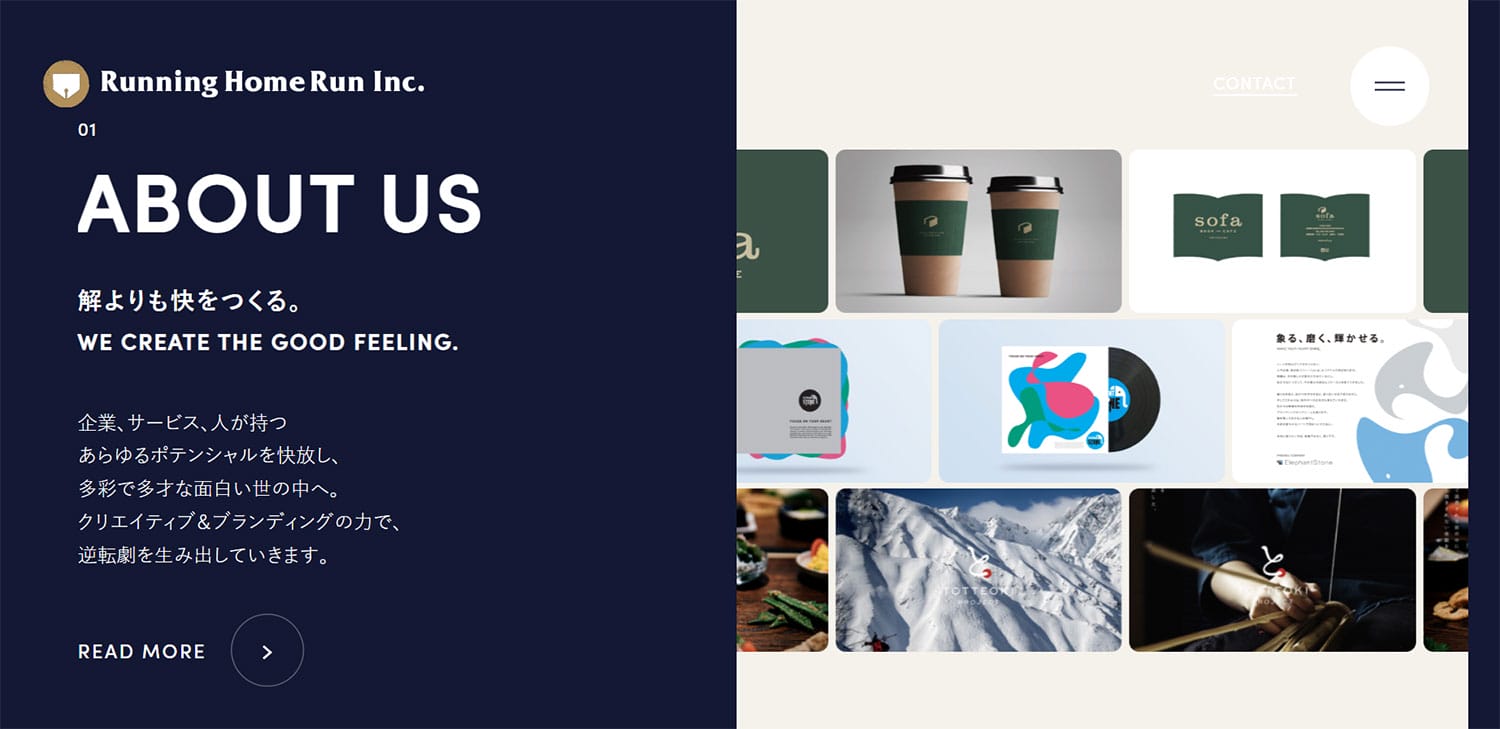


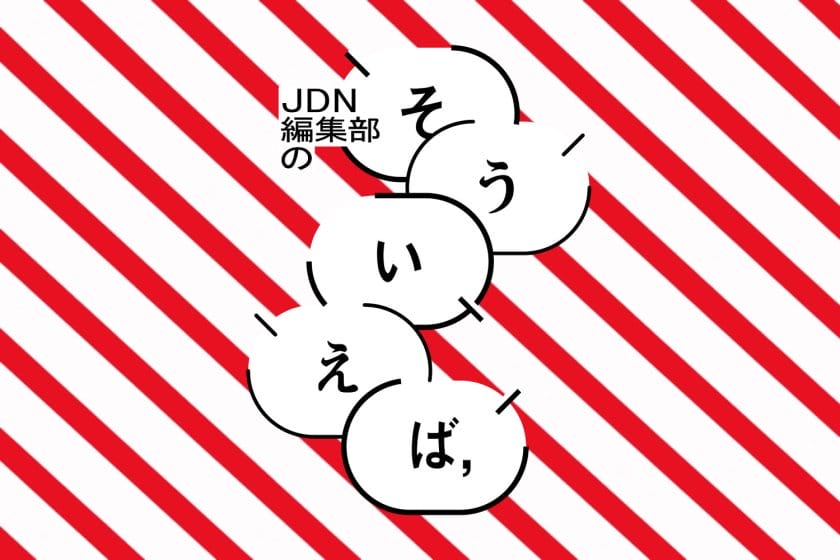

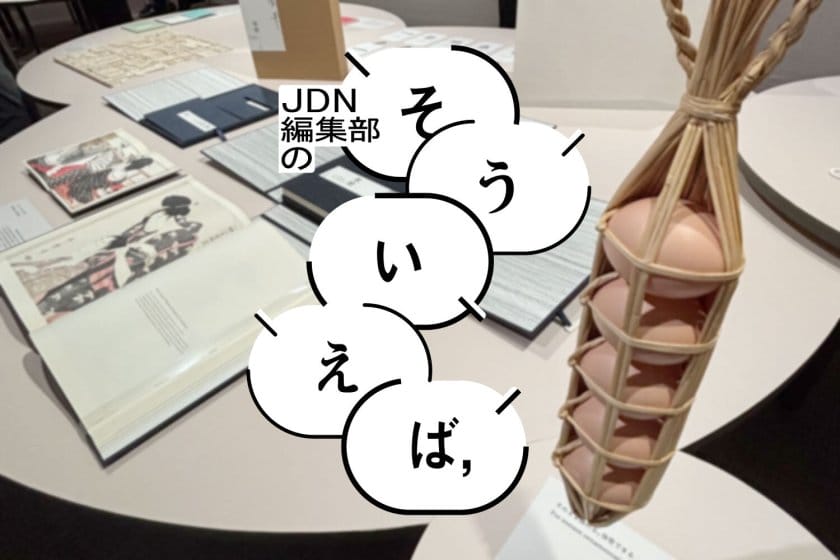
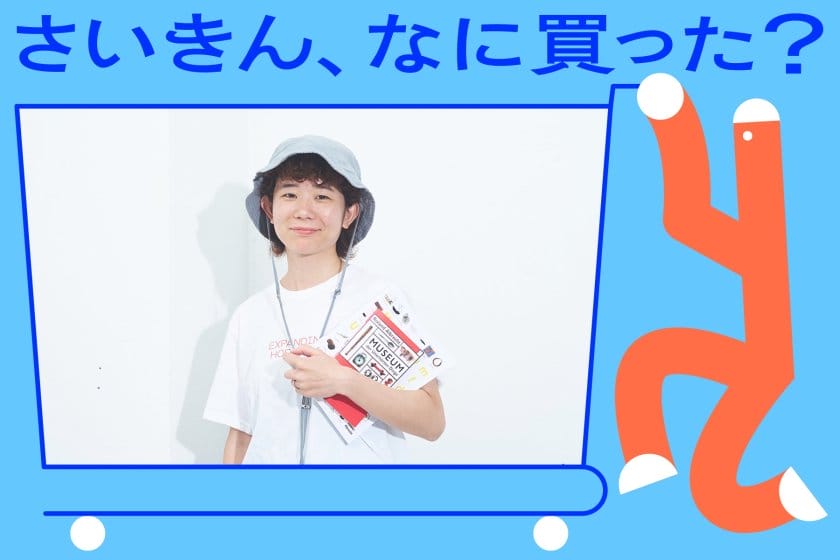
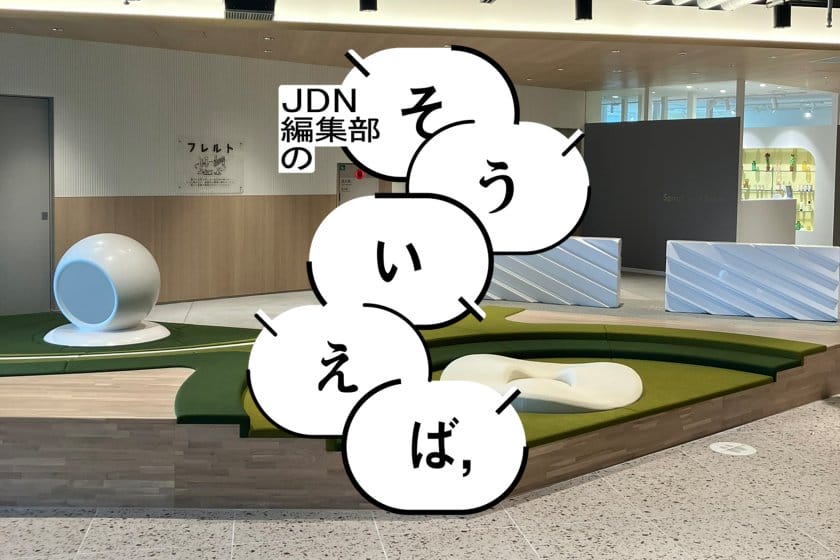





![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




