page: 1 / 2
目には見えないデザイン
展示で心掛けたのは、見る人の印象に少しでも強く残ること。ミラノサローネ会期中、多くの場所で魅力的な展示が行われる中で、自分たちの印象を深めるにはどうしたら良いか、パナソニック電工の何を展示すべきか、会社の姿勢やアイデアをどう伝えるかを徹底的に議論した。2010年の展示に向けては、前年の10月頃から電工のデザイナーや商品企画担当者がディスカッションを繰り返し、納得いくコンセプトをまとめ上げた。そして同社のコンセプトを伝えるためのデザインをマルティノ氏が引き出した。
今回の会場では、大きく分けて二種類のデザインが展示されている。“目に見えないデザイン”と“目に見えるデザイン”である。目に見えない「情報のネットワーク」は、パナソニック電工の中核を担うべき技術。トイレ「アラウーノ」の技術を伝えるために製品を切断して内部の構造を見せ、空気循環パネル「エアロウォッシャー」の空気の流れを床に描いて分かり易くするなど、展示方法に工夫を凝らした。「コンセプトや技術を理解しやすい形にまとめることができた」と、岡井氏は語る。
一方目に見えるデザインでは、昨年の展示で話題を集めた深澤直人氏デザインの照明「MODIFY」を含む10アイテムを、洞窟内に配置した。
|
 |
※クリックで拡大

【8】3年連続でパナソニック電工の会場構成を手がけたマルティノ・ベルギンツ氏。
|
※クリックで拡大

【9】「マルティノ氏が、展示空間に洞窟のイメージを出してきたときは驚きました」と振り返る岡井氏。右は、広報部東京広報主任の岡本麻菜美氏。 |
 |

【10】建物内の各種設備を連動させる「情報のネットワーク」という見えないシステムを、どうやってわかりやすく見せ、伝えるかが課題だった。 |
 |

【11】展示商品を分かりやすくするために、それぞれの商品を博物館のように展示するコーナーも設けた。 |
|
 |
ミラノサローネ効果
岡井氏がミラノサローネでの展示を考え始め、知人の編集者や記者に相談した際、「毎年欠かさず出展することが大切だ」と言われたという。毎年出展することで、その変化を見る人が多いからである。実際に、2年目に「去年はこうでしたね」と進化を指摘された。年々ステップアップする展示を見てもらい、その反響を受けることが次の活動へのヒントにつながるという。
「展示をすることで自分たちの技術がメディアに取り上げられたり、社外の人から“展示をされたんですね”と声を掛けられることからコミュニケーションが始まっています」と岡井氏は成果を話す。
注目を集めるのはイタリアにいる間だけではない。昨年は、ミラノサローネでの展示を、日本の同社ショールームでも再現した。現地に足を運べなかった人にも、デザインを通じて自分たちが考えていることを表現できる。「こういうことができるんだ、楽しいことができる会社なんだ、と知ってもらえるきっかけにしたいですね」と岡本氏はいう。
|
 |
※クリックで拡大

【12】2009年の会場を再現したコーナー。東京都汐留の、パナソニックリビングショウルームにて。2010年の展示も、今後期間限定で再現される見込み。

【13】2009年のミラノサローネで発表された、深澤直人氏デザインの照明MODIFY。今年のミラノサローネでは、さらに大きなタイプのMODIFYが発表された。
|
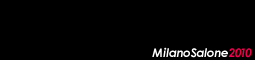
 JDNトップ > レポート > ミラノサローネ2010 > [Interview]デザインの未来を考える パナソニック電工
JDNトップ > レポート > ミラノサローネ2010 > [Interview]デザインの未来を考える パナソニック電工







