2016年のミラノデザインウィークは、家具以外にもさまざまなジャンルの出展にクオリティの高いものがあった。すでに定着した自動車メーカーやファッションブランドに加え、今年はナイキやペプシコなどによるエキシビションも話題を呼んでいた。こうした動きと並行して、デザイン関連のメディアが展示のオーガナイズや自主的なプレゼンテーションを行うケースが増えている。その意図やアウトプットの方法はさまざまだが、彼らの視点はミラノのデザインシーンをいっそう有意義なものにしている。
オランダのデザイン誌『FRAME』
オランダのデザイン誌『FRAME』は、ミラノ市内で「What’s the matter?」展を開催した。サブタイトルは「Design for a phygital world」。Phygital(フィジタル)とは物理的な要素とデジタルの要素が融合した状態を指す造語である。この展覧会では、スマートフォンに象徴されるようにデジタル技術と日常性が結びついた現状をふまえ、そのような融合が生活全体へ拡大した近未来を予感させる16組のデザイナーたちを選定。展示構成を手がけたのはイタリア人デザイナーのフェルッチョ・ラヴィアーニで、彼は会場の床のチェックのパターンを忠実にコピーして壁面に使い、現実と非現実の境界を曖昧にしようと試みた。

オランダのデザイン誌『FRAME』の「What’s the matter?」展
手前のテーブルはロンドンのKUKKA STUDIOによる「ABCD」「O」
会場で特に目を引いたのは、ベルリンで活動するZeitguisedの映像作品「Geist.xyz」。形状やパターンが有機的に変化しつづけるテキスタイルを主題とし、その表現は手で触れられそうなほど生々しい。物質とデジタルデータによる表現との区別がつきにくくなっているのがわかる。また金属を真空蒸着させた色鮮やかなダイクロガラスを使い、見る角度によって外観の変わるインタラクティブ性をそなえさせたKUKKA STUDIOのテーブル「ABCD」「O」も今後の発展が期待される。
geist.xyz from ZEITGUISED
一連の作品に感じたのは、モダニズムの時代からプロダクトデザインの根幹にあった合理性という原則が、デジタル技術によって無意味化しつつある新しい現実である。今後、人工知能のような技術が発達すると、ものづくりのプロセスにおいて複雑とシンプルは等価になるだろう。今から約100年前、工業化する世界を背景にバウハウスなどで合理性に基づくデザインが発展したように、デザインの新しい原則の探求が世界中で始まっていることを、この展覧会では漠然とながら実感させられた。その企画力が『FRAME』の先見性を示している。
ベルギーのデザイン系カルチャー誌『DAMN』
ミラノを代表する歴史的建築物のひとつ、パラッツォ・リッタでは、ベルギーのデザイン系カルチャー誌『DAMN』がキュレーションする「A Matter of Perception」展が行われた。ミラノデザインウィーク会期中の同会場でのエキシビションは3回目だが、今年はミラノ中心部のこのエリア一帯で同時期から始まったデザインイベント「5vie」の活況もあり、順調に来場者を増やしたようだ。

ベルギー『DAMN』誌による「A Matter of Perception」展の中庭の特設パビリオン ©Rafael Medina Adalfio
全体のテーマは「トラディション&テクノロジー」とあまり明確でないが、アルベルト・メダ、ジャスパー・モリソン、フォルマファンタズマ、ダニエル・リバッケンといった著名デザイナーの作品も多く、十分な見応えがあった。中庭ではブルキナファソ出身の建築家、ディエベド・フランシス・ケレが自然素材を多用したあずま屋のようなパビリオンを制作し、人々が自由に集える場とした。

「A Matter of Perception」展にて、Valerie_Objectsが展示したオランダのクリス・カベルによる新作「Hidden Vase」 ©Rafael Medina Adalfio

「A Matter of Perception」展の「Belgium is Design」の展示空間、手前の椅子はジュリアン・ルノーの作品 ©MikkoMikko Studio
参加したブランドやデザイナーの中で、特に充実していたのはやはりベルギー勢である。アントワープを拠点とするValerie_Objectsは、ミュラー・ヴァン・セヴェレンやクリス・カベルによる新作を発表したほか、マーテン・バースや二俣公一を起用したカトラリーのプロジェクトもミラノ初披露。またベルギーの新進デザイナーとメーカーによる13のコラボレーションを紹介する「Belgium is Design」では、やはり『DAMN』がコンセプトを担当している。

Valerie_Objectsが展示した二俣公一によるカトラリー ©Rafael Medina Adalfio
「A Matter of Perception」展では、『DAMN』誌は基本的に裏方となり、ミラノデザインウィークの文脈を的確に捉えながら、規模の大きい会場を巧みに構成していた。長期にわたり現場を観察してきた経験が、人を引き寄せるキュレーションに生かされたということだ。年ごとにエリアが広がり、全体を把握するのが難しくなっているミラノデザインウィークの傾向をふまえると、こうした戦略を採るエキシビションはさらに増えていくに違いない。

「A Matter of Perception」展に展示されたイタリア人デザイナー、アルベルト・メダによるオフィスチェア ©Rafael Medina Adalfio
ギリシャのウェブマガジン『Yatzer』
ギリシャの『Yatzer』は高度な編集力が特徴のウェブマガジン。今年はその10周年を記念して「10 by Yatzer」と題したポップアップショップをミラノデザインウィーク中から限定オープンした。そこで販売されたのは、10組のデザイナーやブランドが手がけたリミテッドエディション作品。ブラックとゴールドをテーマカラーとし、エクスクルーシブ感のあるアイテムを揃えた。

ギリシャのウェブマガジン『Yatzer』のポップアップショップ「10 BY Yatzer」は、ブラックとゴールドがテーマに
10点限定のラグ「Rugthko」はCC-TAPIS、サム・バロンがデザインしたプレート「Traces」は1824年創業のVISTA ALEGRE、イオナ・ヴォートランの「Binic」のブラックバージョンはフォスカリーニの製品。他にバッグ、アクセサリー、ノート、鉛筆、オリーブオイルなどもあった。

「10 BY Yatzer」の壁面は、ピート・ヘイン・イークの壁紙で統一されていた
メディアが通常の役割を超えて、自分たちの志向するクオリティをオリジナルの商品として見せる試みが、ミラノデザインウィークを背景とするといっそう新鮮である。会場は普段から人通りが多いブレラ地区の中心部にあるデザインストア、スパツィオ・ポンタッチョの一角で、一帯ではブレラデザインディストリクトも行われている。コンパクトなスペースだったが、十分な密度と一貫した美意識があり、相当の存在感があった。
ミラノのアートマガジン『KALEIDOSCOPE』
ミラノを拠点とするアートマガジン『KALEIDOSCOPE』は、編集部に併設したプロジェクトスペースで「EPOCSODIELAK」という作品を展示した。これは『KALEIDOSCOPE』とドイツの『ZEIT』誌が共同で行ったもので、「EPOCSODIELAK」はともにミュンヘンで活動するプロダクトデザイナーのコンスタンティン・グルチッチとグラフィックデザイナーのミルコ・ボルシェが共同制作したものだ。

『KALEIDOSCOPE』のプロジェクトスペースでは、コンスタンティン・グルチッチとミルコ・ボルシェによる「EPOCSODIELAK」を展示
直方体に組んだ高さ3mのフレームにはスピーカー、数種類のLED照明、スモークマシン、サイネージなどがそなわっている。これ1台あれば、その場がクラブになるという代物である。4月13日には実際にこの作品を使ってパーティが開催されている。グルチッチは今年もカッシーナ、マジス、ドリアデ、クラシコンなどの多くの家具ブランドから新作を発表した一流のデザイナーであり、ミルコは上記の雑誌のアートディレクターやクリエイティブディレクターを務める。友人同士でもあるふたりにとって、「EPOCSODIELAK」は楽しみながら進めることができたプロジェクトだったようだ。

「EPOCSODIELAK」はスピーカー、照明、スモークなどの機能を搭載
『KALEIDOSCOPE』は、これまでもエンツォ・マーリが所蔵するペーパーウェイトを展示する「The Intellectual Work: Sixty Paperweights」展や、ジャスパー・モリソンらがオーガナイズした「Source Material」展などを開催してきた。いずれも規模は小さいものの、それぞれに実力と実績あるデザイナーがかかわり、通常の新作発表とは異なる自由かつ批評的な姿勢を感じさせるものだった。
拡張するミラノデザインウィーク

恒例の「Wallpaper Handmade」展で展示された作品、 ‘The Barony’ bar / Glenn Sestig Architects, Dinesen and Ocular ApS
これまで紹介してきた他にも、イギリスのデザイン誌『Disegno』がミラノデザインウィークのためにタブロイドを制作して配布したり、イタリアの建築デザイン誌『ABITARE』がファッションブランドのジル・サンダーと共同でデザインカンファレンスを行ったりと、今年はメディア絡みの目新しい動きがあった。
またすでに恒例になっている催しには、『Wallpaper』誌による企画展「Wallpaper Handmade」、世界で展開する『エル・デコ』のデザインアワード(EDIDA)の授賞式、『INTERNI』誌がミラノ大学で行うイベントなどがある。デザイン系ウェブサイトの『Architonic』も、ミラノサローネ国際家具見本市のガイドを独自に制作して配布している。
それぞれのメディアは、メーカーやデザイナーとは違う角度からデザインを捉え、しばしば先見的な方向を提示している。新しいムーブメントを紹介したり、未知の才能を発掘したり、ビジネスを離れた価値を提案したりすることは、デザインシーンの好循環に貢献するに違いない。そのためにメディアに求められる俯瞰的な視野や鋭敏な感性は、彼らの通常の活動にもフィードバックされていく。メディア自体の質を高め、ブランド価値にも反映されることだろう。またSNSが定着した現在、情報発信のあり方が変化するのは必然でもある。
なお日本のメディアについては、ミラノでのこうした動きはほぼ見られない。言語の壁などの要因はあるが、そこに風穴をあけるようなアクションもありうるのではないかと、今回の記事をまとめながら考えさせられた。
1970年北海道生まれ。会社員などを経て、2001年からフリーランスで活動。国内外での取材やリサーチを通して、雑誌をはじめ各種媒体に寄稿中。家具などのプロダクトを中心とするデザインと、その周辺のカルチャーについて執筆することが多い。
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

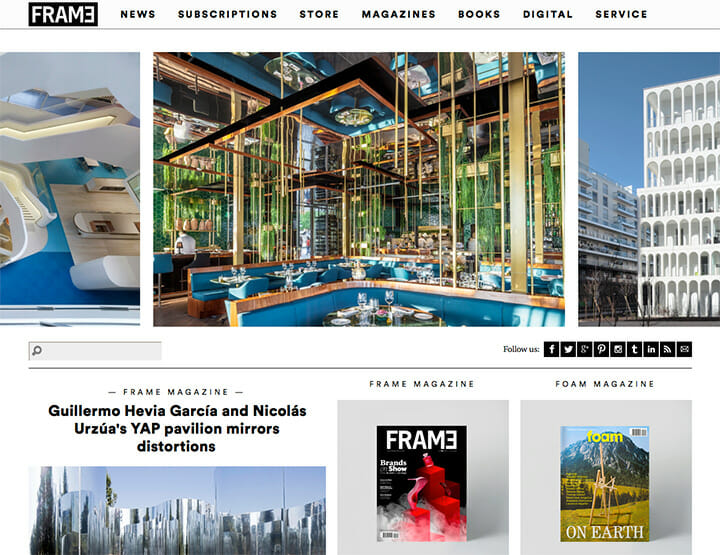
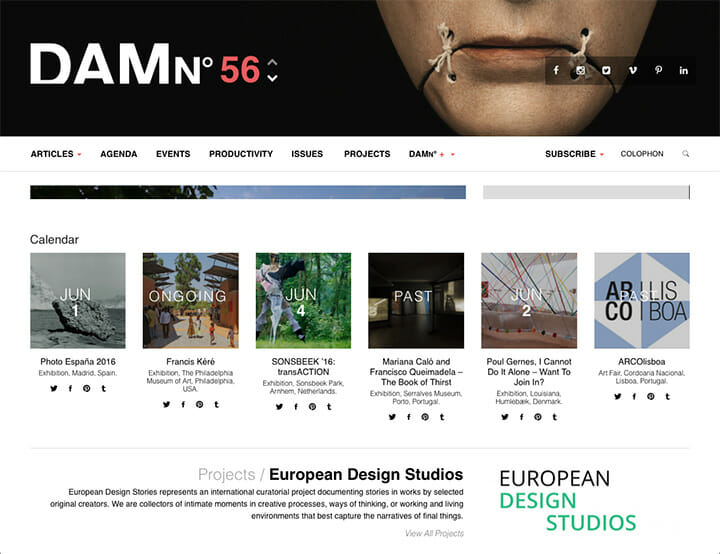
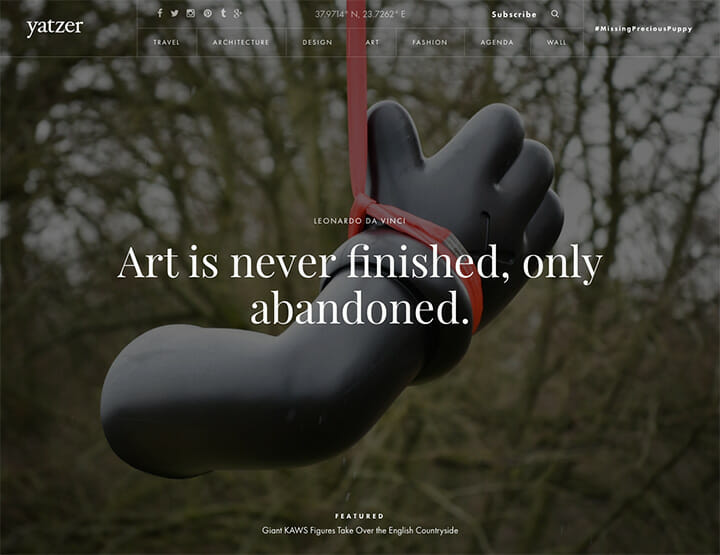
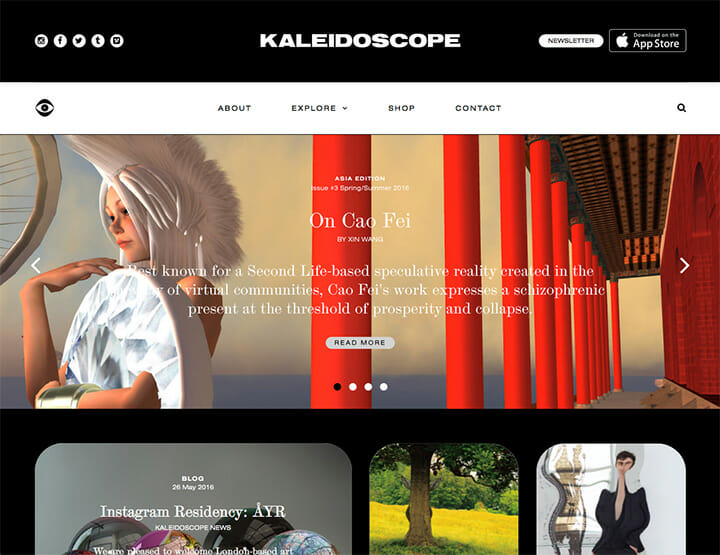





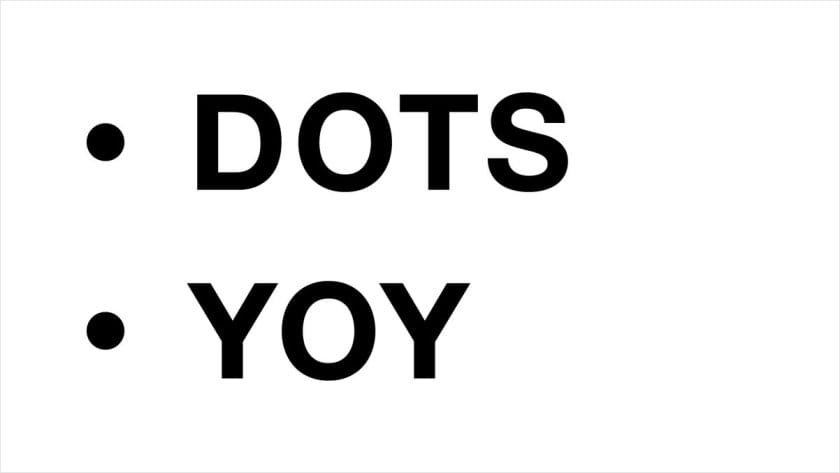







![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




