江戸切子や東京染小紋、江戸木目込人形など42品目が指定されている東京の伝統工芸品。江戸時代から脈々と受け継がれてきた職人の技を、未来につなげていくためのプロジェクトがあります。
「東京手仕事」商品開発プロジェクトは、繊細な技術を持つ職人とデザイナーなどのビジネスパートナーが協働することで、新しい「東京の伝統工芸品」を生み出す取り組み。2015年から公益財団法人東京都中小企業振興公社が主催し、職人とデザイナーのマッチングから商品開発中のアドバイス、試作品製作費用の支援などをおこない、実際に商品として完成するまでをサポートしています。
2025年度は6月2日から6月20日まで、商品開発をおこなうビジネスパートナーを募集します。

今回お話をうかがうのは、2023年度の同プロジェクトにて東京都知事賞を受賞した、木目込みのお面「木目込神楽」のデザイナー・板倉健太郎さん。普段は株式会社ディークロスの代表としてアミューズメント製品のプロダクトデザインなどを手がけています。
「遊び心や驚きのあるデザインをつくるのが好きです」と語る板倉さんが本プロジェクトに参加した理由とは何だったのか。そして、どのような想いで「木目込神楽」をデザインしたのか。参加の動機からプロジェクトのその後までうかがいました。
応募のきっかけは、伝統工芸品の魅力を広めたいという想い
――まずは板倉さんのご経歴と、「東京手仕事」商品開発プロジェクトに参加された経緯から教えてください。

板倉健太郎 株式会社ディークロス代表、プロダクトデザイナー。東海大学教養学部芸術学科で工業デザインを専門に学び、卒業後は試作メーカーでプロダクトデザインに携わる。デザイン設計事務所を経て、2018年に株式会社ディークロスを設立
幼い頃からものづくりに興味があったため、大学でインダストリアルデザインを専攻し、卒業後は試作メーカーでデザイナーとして働いていました。その後2018年に独立して株式会社ディークロスを設立し、現在はおもにアミューズメント製品や日用品などのプロダクトデザインを手がけています。
弊社のデザインの特徴は、初期段階から3D CADを用いることです。また、パッケージの見た目からは想像できない不思議な構造にしたり、手に取ったときに発見があったりなど、遊び心や驚きのあるデザインをつくることが得意ですね。
そんな中で公募展に目を向けるようになったのは、ひとえにデザイナーとしての今後を見据えてのことでした。自分が貢献できる領域をより広げていくためには、実績を積むだけでなく発信していく必要がある。また、いま頼りにしてくださっているお客様に真摯に向き合うのはもちろん、さらに多くの方の目に触れる機会も増やしていきたい。そう考えてコンテスト情報がまとめられているサイト「登竜門」を見ていたところ、「東京手仕事」商品開発プロジェクトを見つけたんです。
――参加の決め手は何だったのでしょうか?
自分の実績として発信できる点にも惹かれましたが、決め手となったのは伝統工芸品を扱うプロジェクトだったことです。一つひとつの商品に職人の方々の知識と伝統技術がぎゅっと込められている。そしてアートではなくあくまで商品として、使いやすさや耐久性もとことん追求されている。そうしたたくさんの魅力を持つ伝統工芸品に昔から興味を持っていたんです。
職人の方々は、どのようなこだわりを持って商品に向き合っているのだろう。東京の伝統工芸品の魅力を、どうしたら広く届けることができるのだろう。そんな興味から応募を決めました。
人形に用いられる木目込技術を「お面」に転用
――参加にあたり、株式会社柿沼人形の「江戸木目込人形」に注目したのはなぜだったのでしょうか?
すべての職人さんの紹介動画を拝見した上で、最も自分が貢献できそうだと感じたのが柿沼人形さんでした。

柿沼人形による江戸木目込の雛人形
そもそも木目込技術とは、人形などの原型に溝を彫り、そこに布を挟み込んでいくことで衣装を着ているように仕立てるという技法で、おもに五月人形や雛人形などに用いられてきたもの。しかし柿沼人形さんは、人形という枠にとどまらずに木目込技術を活用したい、そして世界に発信したいという強い想いを持っていました。

原型の溝に布を挟み込む様子
また、昨今は職人不足が喫緊の課題となっているため、3Dプリンタといった新しい技術も積極的に取り入れていきたいとも話をされており、私がこれまで遊び心や驚きを大切にしてきたこと、また3D CADを長年扱ってきた経験が活かせるのではないかと考えたのです。
――その後、どのようにアイデアを練っていったのでしょうか?
木目込技術を活用できる新たな商品とはどのようなものか。長きにわたり人形に用いられてきた技術であること、それを世界に発信するということを軸に考え続けた結果、辿り着いたのがお面でした。

木目込神楽。左上から白狐、赤般若、お多福、黒狐、般若、茶お多福の6種類を展開
お面は五月人形や雛人形のように飾る(祀る)という機能だけでなく、身につけるという機能も持っていて、用途が幅広い。かつ、「海外の方にとって身近な日本文化といえば?」と聞かれてまず候補に上がる着物と、お面はとても相性が良い。その証拠に、日本に観光に来られた海外の方が、着物姿でお面を被っている写真をSNSにアップしているのを見かけることも多いですよね。
日本古来から信仰と縁起の象徴として扱われてきたお面と木目込技術を掛け合わせ、世界にはばたく商品を生み出す。「綺麗ですね」で終わらせずに、「自分の手元に置きたい」と思っていただける商品を目指す。その2点を大切にしながら、アイデアを詰めていきました。
――ビジネスパートナーを選ぶマッチング会がはじまってすぐ、柿沼人形さんは板倉さんとのコラボを希望していたそうですね。ご自身では手応えがあったのでしょうか?
アートではなく商品として展開できるものをつくるということに重きを置いていたのが大きかったのではないかと思います。その前提のもと、海外展開や3D技術の活用などとも結びつくアイデアに仕上げたことで、納得感を持っていただけたんじゃないかと。

柿沼人形さんに限らずですが、本プロジェクトに参加されている職人さんは自分たちの技術をもっと多くの方々に届けたいと思っていらっしゃるはずなので、私たちデザイナーも作品づくりの一環として取り組むのではなく、商品としていかに優れたものをつくるかという視点からブレてはいけないと思います。
――無事にマッチングが成立した際はどのような想いを持たれましたか?
ご指名いただいた以上、しっかり期待に応えなければと背筋が伸びました。また、マッチング会で初めてお会いしたときから、柿沼人形さんの熱意や木目込技術へのこだわりを強く感じていたため、そうした職人さんと共にものづくりができることへの嬉しさも感じましたね。
- 1
- 2
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

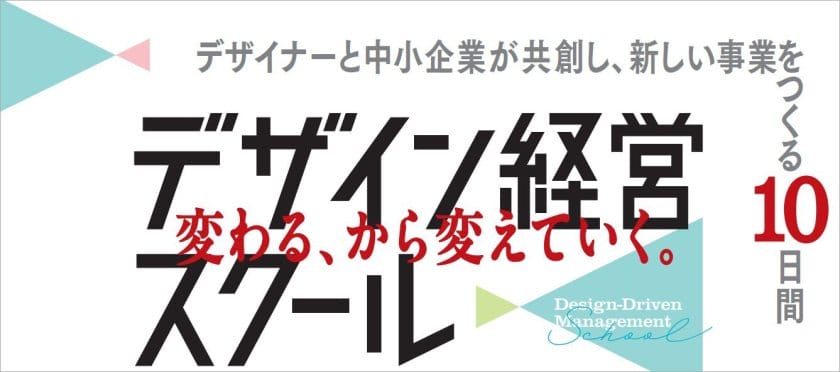












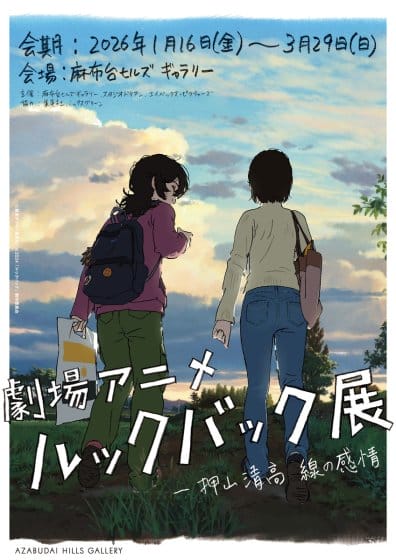
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




