
全自動衣類折りたたみ機「ランドロイド」
誰かがやっていたら意味がない。ランドロイドの開発に至るまで
――「laundroid」は世界初となる全自動衣類折りたたみ機ですが、なぜこれを思いついたのでしょうか?
阪根信一さん(以下、阪根):単刀直入に言うと、これまでに誰もつくったことがないからです。私たちセブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ(以下、セブン・ドリーマーズ)は、世の中にないものをつくり出す技術集団です。イノベーションを起こすために、私たちが最も大事にしているのがテーマの選び方です。これには3つのクライテリア(判断基準)を設けていて、1つめは世の中にないもの、2つめは人々の生活を豊かにするもの、3つめは技術的にハードルが高いもの。ここを正しく選べばイノベーションは必ず起こせると考えています。ですので、この3つをクリアするものであれば分野を問わず挑戦しようと。

セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ株式会社代表取締役社長・阪根信一さん
――「世の中にないもの」という考えは立ち上げ時から?
阪根:はい。私の父が技術者であり発明家で、「人のまねはするな」というのが昔からの口癖でした。加えてアメリカの大学院にいた時の研究テーマも、人類がこれまでに解明できなかった自然現象を解き明かすというもので、帰国してビジネスの世界に入った時には、世の中にないものをつくりたいという気持ちがすでにありました。
帰国して、2003年からBtoCのビジネスに挑戦すると決めてテーマを探しはじめましたが、思いついたものは大抵海外のどこかの企業がつくっているんですよね。なので、まず1つめの基準がクリアできずに落ちてしまう。そうこうするうちに2年経ち、ある日妻に、「世の中になくて技術的に難しそうで、こんなのがあればいいなと思うものない?」と聞いたら、「洗濯物自動折りたたみロボットが欲しい!」と、即答でした。とはいえ、すでにあるだろうと翌日リサーチをかけてみると、誰もやっていなかったんです。
よく考えたら、洗濯乾燥機までは開発されているのに、手間のかかるたたむ工程はいまも昔も人の手でやっていて、なんだか違和感がありませんか? だからこそたたむ工程を自動化できれば、当然それに費やす時間を自由な時間に変えられますから、「人々の生活を豊かにする」というクライテリアもクリアできる。灯台下暗しで、妻に聞けば10秒で済みました(笑)。
技術の追求と新たな出会い
――世界初ということで、技術面での苦労がうかがえます。
阪根:若い技術者2~3人に協力してもらい、カメラと人工知能とロボットアームを駆使して、一定の場所に衣類やタオルを置いてスタートボタンを押せば自動でたたむ仕組みは、3年ほどでできました。ただ、洗濯物を種類ごとに認識して仕分けるプロセスまではできなかったんです。2005年に製品化を決めた時点で「オールインワン」をイメージしていたので、洗濯物の山をランダムに置いてその中からTシャツ、短パンなど仕分けてたたむことができなければ意味がありません。

それからはまったくの迷走でした。定形物を認識するのは、いまや画像解析と人工知能でたやすいですが、柔軟物は持ち上げた瞬間に変形するので、仕分けるにはある程度広げる必要があります。どうすれば展開できるだろうと考えるうちに4~5年経ち、ようやくブレイクスルーが出たのが2012年頃でした。これはいまだに世界中で当社しかできません。

――ライゾマティクスでは、ランドロイドのブランディングからクリエイティブディレクション、プロダクトデザインなどトータルでサポートされていますが、関わりはじめたのはその頃からですか?
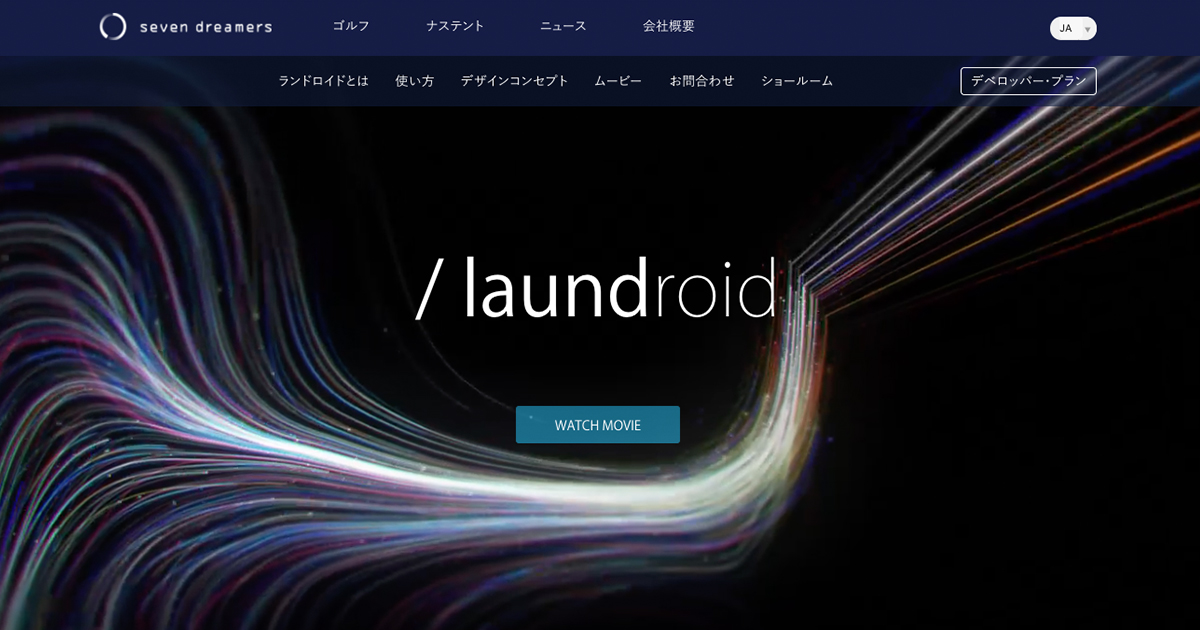
ライゾマティクスがブランディングやプロダクトデザインなどトータルでサポート
阪根:そうですね。いよいよ商品化が見えて製品としての世界観を構築する段階になってからですね。コーポレートブランディングが重要なことはわかっていたのですが、我々は何せ技術者集団なので右も左もわからず、そんな時にライゾマティクスさんを紹介していただきました。当時から名だたる企業とお仕事されていたのに、ランドロイドの話をすると乗っていただき、会社のブランディングを含め一からお願いできることになったんです。
清水啓太郎さん(以下、清水):僕は、プロデュース、クリエイティブディレクション、プロダクトデザインまで幅広くお手伝いしていますが、セブン・ドリーマーズさんからランドロイドのお話を伺った時に、これはおもしろいと。こんな仕事に関われるチャンスはそうそうないんじゃないかと、うちの社長の齋藤(精一)とも話して、ぜひやらせてくださいと。アートディレクターには、外部から長田桂太さん(OSSA MOND A&D)に指名で入っていただき、 これまでセブン・ドリーマーズさんの多くのクリエイティブワークを共に生み出してきました
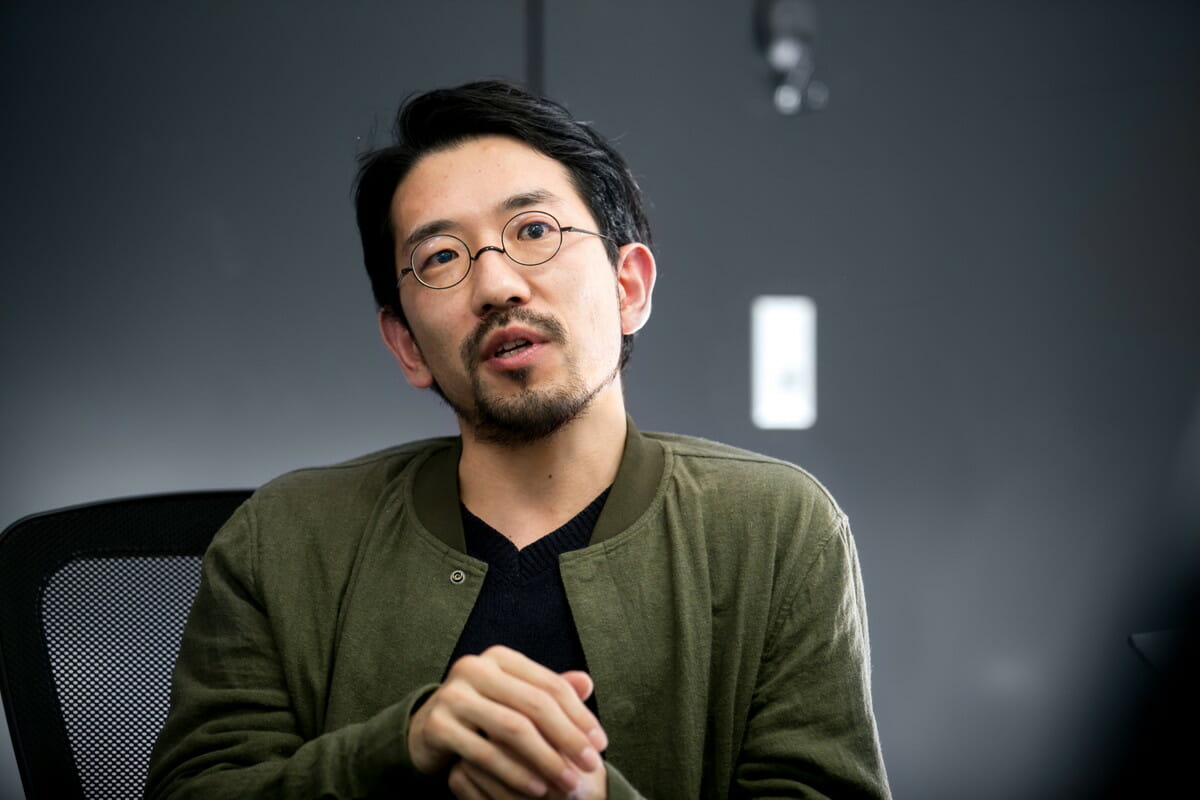
株式会社ライゾマティクス清水啓太郎さん
阪根:技術面以外に、もうひとつハードルがあって、資金調達前だったのでお金がなかったんです(笑)。開発費用については私が社会人になって初めて立ち上げた新規事業がたまたま軌道に乗り、そこから捻出できたのですが、マーケティング費用が必要な時期に落ち目になりました。しょうがないので正直に齋藤さんに話すと、「出世払いでいいですよ」と。というのも、「ベンチャーがブランディングしようと考えた場合、全力を注ぐべきなのに費用の問題でいいものができないのはよくない。だったら出世払いのような仕組みをお互いつくりましょう」と言ってくださったんです。
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

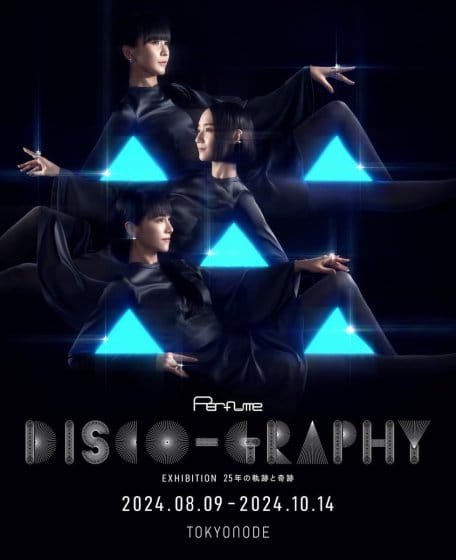
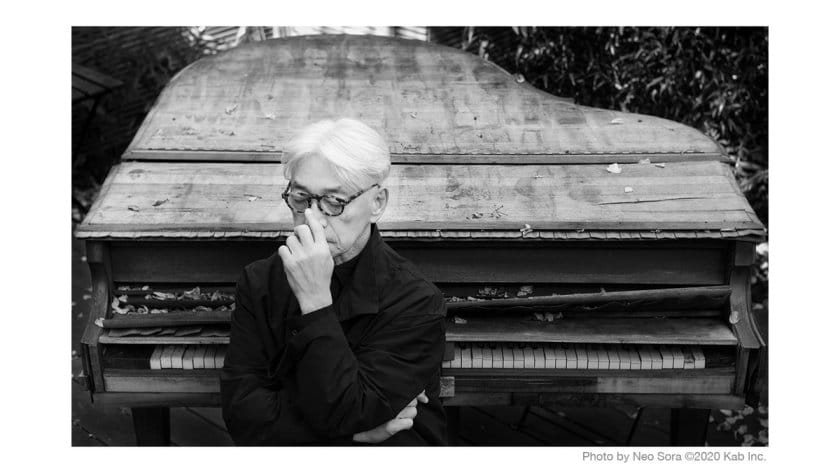



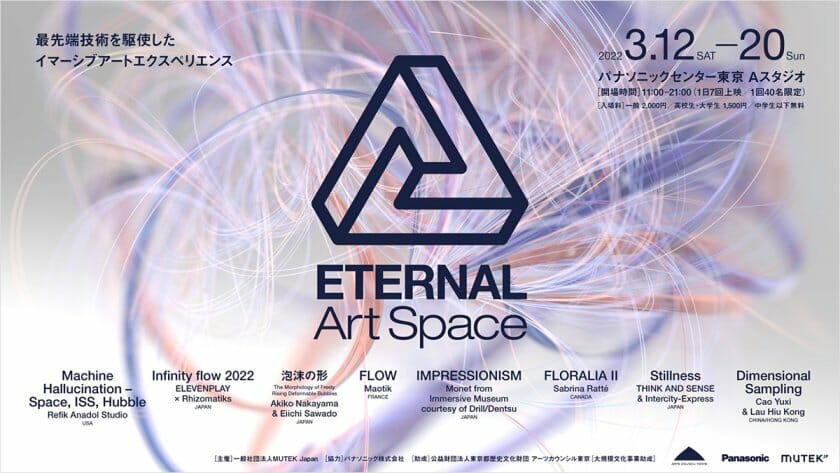








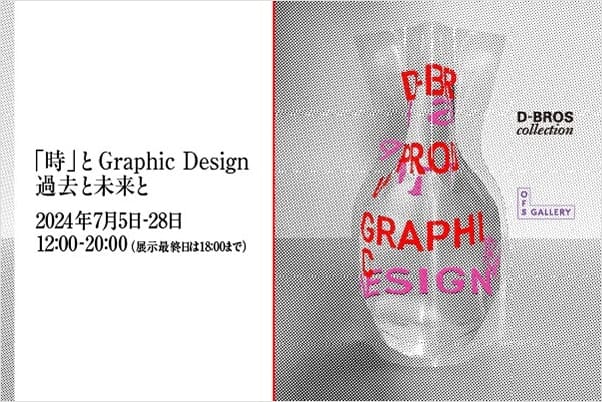

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




