非日常を踊る 第2回:長澤風海

2020年春、新型コロナウイルス感染症の影響で1回目の緊急事態宣言が発令され、文化芸術活動にかかわる人たちは大幅な自粛を余儀なくされた。フォトグラファーの南しずかさん、宮川舞子さん、葛西亜理沙さんの3名が、撮ることを止めないために何かできることはないか?と考えてはじまったのが、表現者18組のいまを切り撮るプロジェクト「非日常を踊る」だ。
コンセプトとして掲げられたのは「コロナ禍のいまを切り撮ること」と「アートとドキュメンタリーの融合写真」という2つ。プロジェクトは、タップダンサーやドラァグクイーン、社交ダンサー、日本舞踊家などさまざまなジャンルのダンサーがそれぞれの自宅や稽古場という「裏舞台で踊る姿」を撮影した、2020年を反映するパフォーマンスの記録となった。
本コラムでは、フォトグラファー3名が想いを込めてシャッターを切った写真と、南さんが各表現者にインタビューした内容を一緒に紹介していく。コラム第2回目となる今回は、ダンサーの長澤風海さんの写真とインタビューを紹介する。
長澤風海/ダンサー(撮影:宮川舞子)
18歳からバレエを始め、カナダのオペラカンパニーにダンサーとして参加。帰国後はさまざまな舞台で活躍しているダンサーの長澤風海さん。2014年には自ら立ち上げたカンパニーで「ENTERTAINMENT DANCE ART SHOW『BLUE WHITE』」を上演し、2018年にはミュージカル「メリーポピンズ」、2017年&2020年ミュージカル「アルジャーノンに花束を」など多数の舞台に出演している。2020年8月、長澤さんは弟と一緒に週1回のペースで池袋の“路上”で踊っていたという。
長澤風海さん(以下、長澤):「プロのダンサーが路上で踊るなんて!」と否定的に捉える方がいるかもしれませんが、僕は若い頃から公園で踊ることが好きだったので、いま踊ってみるとどういう感覚になるのか試したかったんですよ。

撮影場所は自宅近くの商店街。特技は中国武術とクラシックバレエで、中国武術は元全日本の強化選手だったそう。

撮影は、歩行者の流れが途切れたタイミングで素早く行われた。
長澤さんはタップダンサーの弟と共に、ヘブンアーティストの資格を持っている。ヘブンアーティストとは、東京都の指定された路上でパフォーマンスすることを許可されたアーティストのことだ。
長澤:歩いてる人がフッとこちらに目を止めてくれたり、踊り終わったら車椅子のおばあちゃんが「良かったよ〜」と声をかけてくれたり、子どもたちがわーっと盛り上がってくれたり。スタジオにこもって一人で自主練していた時より、誰かに見られていることで、体が動いたんですよね。改めて人前で踊ることの面白さを確認できました。
プロのダンサーとして10年以上やってきましたが、ちょっと傲慢になっていたかもしれないと反省もしたんです。知らず知らずのうちに、舞台に立ってお金をもらうことが当たり前になっていたのかなと気づいたというか。
長澤さんがよく公園で踊っていたのは、まだ駆け出しの20代前半の頃。当時はクラシックバレエと中国武術に長けていたが、ひとつのことを極めるより、さまざまな表現方法を学んで、オリジナルの身体表現を確立することに興味を惹かれ、コツコツと地力をつけている時期だった。

最終的なセレクトカットは商店街のものになったが、公園や歩道橋などでも撮影が行われた。
基本的に依頼された仕事はすべて引き受けると話す長澤さん。クラシックバレエや2.5次元のミュージカル、ストレートプレイなどの出演から、3Dアイドルや能楽師の振り付けまで。もはやダンスのみならず、歌やお芝居にも活躍の場を広げている。そのうち、エンターテインメントとアートの両方の要素があるステージをつくることが目標の一つだそうだ。ところが意欲的に仕事と向き合う中、コロナの影響を受けて、2020年度のほとんどの仕事は中止や延期となってしまった。
長澤:集客することで興行が成り立っていた舞台業界は大打撃を受けました。当たり前に享受していたことが、当たり前じゃなくなってしまった。舞台という特殊な場は必要ないと言われた気がしたんですよ(苦笑)。第1回目の緊急事態宣言の期間中、仕事がないことで、絶望的な気分に陥りました。役者仲間が空いた時間を利用して料理や筋トレなどに励む傍ら、たまに公園などで踊るぐらいで、あとはひたすら家でぼーっとしていましたね。人から必要とされることが、僕のモチベーションだったんだなと思いました。

緊急事態宣言が解除されると、まずは講師をしているバレエ教室を再開。生徒たちが「ようやく踊れる!」と喜ぶ様子に、長澤さんは力をもらったという。ソロで踊る機会など、徐々に仕事も戻ってきた。
長澤:特に感慨深かったのは、2020年秋に開催されたミュージカル「アルジャーノンに花束を」の出演でした。あらすじとしては、32歳になっても幼児並みの知能しかないパン屋の店員チャーリィ・ゴードンが、賢くなりたい一心で開発されたばかりの脳手術を受けます。手術の成功によりチャーリィは超天才に変貌していきますが、新たに掴んだ幸せや失ったものなど人の心について考えさせられるというストーリーです。原作は、作家ダニエル・キイスが1959年に発表した同名のSF小説で、日本でも発行部数が300万部を超えてテレビドラマ化もされ、舞台化は今回で4回目です。
長澤さんはチャーリィより先に脳手術を受けた白ネズミのアルジャーノンの役を務めた。チャーリィの心象風景を踊る大事な役どころだ。2017年の日本公演3回目にも出演し、思い入れのある作品だという。
長澤:22~23歳の時に、電車の中で原作を読んでいて、号泣してしまったんですよね。心の深いところをえぐってくる話というか、でも最終的に“人は痛みを知ることで優しくなれるんだよ”って言っている気がして、すごく好きなお話です。
そんな大好きな作品が上演される場所が、銀座博品館劇場だったこともいい偶然でした。緊急事態宣言前の直前に出演したのも同劇場ということもありましたし、この10年間で何千回出演したか数えられないぐらい、お世話になっている場所なのです。いつも知ってるスタッフさんと、大好きな役で、またこの場所からスタートを切れてすごく嬉しかったです。その公演初日の舞台に出た瞬間、照明がいつもより体に染みてきて、それくらい踊ることや舞台に立つことが自分にとって大事なものだったんだなと。
人気がある作品でもコロナ禍のため、お客さんは収容人数の半分に制限されていましたが、自分の演技に対して、フェイスガード越しにクスクス笑ってくれたりして、演者と観客が一緒にこのかけがえのない時間を共有していることを感じました。
こんな状況下でも無事に最終日まで完走することができたことに心から感謝していた長澤さん。コロナ禍の苦難において、確かな気づきがあった。

撮影カットを確認する長澤さんとカメラマンの宮川さん。
取材・執筆:南しずか 写真1~2枚目:宮川舞子 タイトルイラスト:小林一毅 編集:石田織座(JDN)
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)









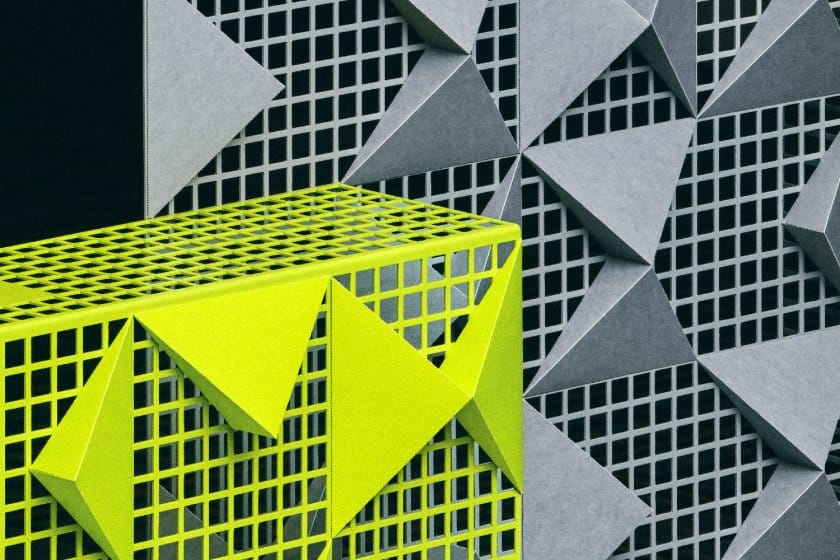

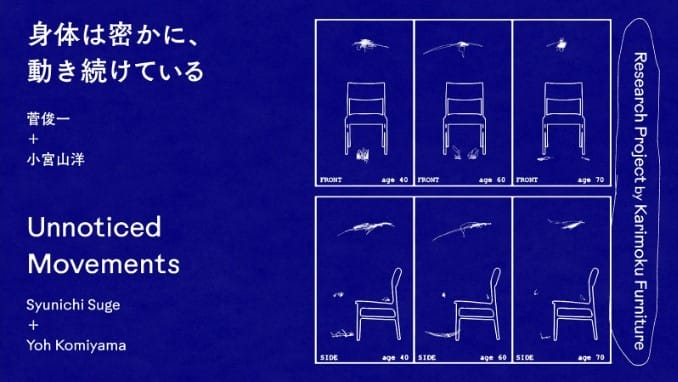

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




