非日常を踊る 第18回:治田敦

2020年春、新型コロナウイルス感染症の影響で1回目の緊急事態宣言が発令され、文化芸術活動にかかわる人たちは大幅な自粛を余儀なくされた。フォトグラファーの南しずかさん、宮川舞子さん、葛西亜理沙さんの3名が、撮ることを止めないために何かできることはないか?と考えてはじまったのが、表現者18組のいまを切り撮るプロジェクト「非日常を踊る」だ。
コンセプトとして掲げられたのは「コロナ禍のいまを切り撮ること」と「アートとドキュメンタリーの融合写真」という2つ。プロジェクトは、タップダンサーやドラァグクイーン、社交ダンサー、日本舞踊家などさまざまなジャンルのダンサーがそれぞれの自宅や稽古場という「裏舞台で踊る姿」を撮影した、2020年を反映するパフォーマンスの記録となった。
本コラムでは、フォトグラファー3名が想いを込めてシャッターを切った写真と、南さんが各表現者にインタビューした内容を一緒に紹介していく。最終回となる今回は、2020年12月に撮影を行った、治田敦さんの写真とインタビューを紹介する。記事最後には主催の3名からのメッセージも記載しているので、ぜひ最後までご覧いただきたい。
治田敦/俳優(撮影:宮川舞子)
1954年10月13日生まれ、宮崎県出身の治田敦さん。上智大学を卒業後、劇団「夢の遊眠社」で劇作家・演出家の野田秀樹さんと出会う。劇団四季時代は「オペラ座の怪人」、「美女と野獣」、「ライオンキング」などでメインキャストを務め、退団後は演出家・宮本亜門作品の常連として、30年近く第一線で活躍している。

ご自宅で行われた撮影。傍らにいるのは、治田さんの愛猫であるプーちゃん。治田さんはライフワークとして、猫の保護活動や里親探しを行うボランティア活動「がんじろう基金」を行っている。
――では最初に、「ミュージカルの魅力」について教えてください。
治田敦さん(以下、治田):基本的には普通の芝居と変わらないんですよ。ところが、ある時点で、セリフが歌に変わっていくんです。
たとえばいま、俺が医者の役だとしますよね。それで、胃ガンの患者役に「ただの胃潰瘍です」と告げて、その患者を追い返すとします。そうしたら、医者の助手役が俺に向かって「先生、何で本当のことを言ってあげないんですか!」と詰め寄る。そこで、チャラララ〜と、音楽がかかるんです(治田さん、立ち上がる)。
「わかってなーいなー、医者でいたけりゃ、おーぼえてーおけよー!せーいぜい、余命半年なんて言ったっら、おしまいだー!!」みたいにメロディがついて歌う。これが面白いところじゃないですかね、ふふふ(笑)。
コロナ禍の影響を受けて、治田さんが出演予定だった「機関車トーマス」全国公演(2020年4〜5月)は中止。2020年10月から約1カ月間、東京の日生劇場を皮切りにスタートした、黒澤明生誕110年記念作品ミュージカル「生きる」は上演され、治田さんも出演した。

キャットタワーの上にはプーちゃんもスタンバイ
治田:「生きる」は、30年間まじめにコツコツと勤めてきた市役所の渡辺課長が、ある日突然胃ガンになって余命半年と宣告され、「ずっと真面目にやってきたのに!」と一回やけになりますが、「市民のために公園をつくろう!」と己の生きる意味を見出して、必死になるというお話です。
要するに、ガンになって死ぬ人のお涙ちょうだいではなく、死ぬ間際まで一つの目標に向かって打ち込む、生きることの素晴らしさを訴えたミュージカルなんですよ。
演出家は宮本亜門さんですが、今までお仕事させていただいた演出家では亜門さんが一番多いんじゃないですかね。今回、医者と役場の係長の役をやったんですが、亜門さんから「この主人公に絶対同情せず、優しさも排除した演技をしてください」と要求されました。
2幕の後半にリーン、リーンと役所の業務終了のベルが鳴り、「はい、お疲れ!」という俺のセリフがあったんだけど、最初それを皮肉っぽく言ってたら、亜門さんから「だらっと言って。感情を一切抜きにして」と。そこで、抑揚のない低い声で「はい、お疲れ」と言ったらそれがリアルだったみたいで、主役の2人から好評でした。
亜門さんから要求されることに応えながら、集中して演技してたら、一つの流れができたという感じですかね。やっぱり、亜門さんはよく芝居がわかってるっちゅうか、もう全幅の信頼ですもん。

さまざまなポーズでベストカットを探っている様子。
――ミュージカル「生きる」で学んだことや、観客の反応についても教えてください。
治田:抑えることかな。さっき言った「はい、お疲れ」にしても、声量的には全然エネルギーを使わないけど、心が冷え切って、冷え切って、で、ポロっと一言いう。そのポロっと言うまでが大変で、つまりパーっとやる方が楽というか。抑える演技の方が難しいですね。
お客さんは、感染症対策の関係で1席おきにしか入れられなかったんですが、どの会場も満席だったんですよ。いつもの半分しか入ってなかったんですが、ものすごい拍手でした。ブワーっと総立ちで何回も何回もアンコールがあって、それはやっぱり、一生懸命ひしひしと生きる主人公の姿が感動を呼んだんじゃないですかね。
――コロナ禍での上演について、どんな感染予防対策をされていたんでしょうか?
治田:自分の出番が終わるとうがいと手洗いをし、必ずマスクをつけていました。地方公演では、靴を外と劇場内、つまり内履きと外履きを完全に分けたりもしましたね。地方に行くとホテル住まいなので、飲み屋さんで持ち帰り用の弁当をつくってもらったり。ホテルの部屋に持ち帰って、手を洗ってうがいをして、それを食べて1人飲みして眠って、それでまた朝起きて劇場に行き、手を洗って、靴を履き替えてと……その繰り返しだったなぁ。
だって、もし1人が感染したら、それで公演が終わりになっちゃうんですよ。何十人ものスタッフさんがいて、大勢のキャストもいて。それがたった1人でも感染したら終わってしまうので、地方公演の時も飲みに行ったりとかはまずなかったですね。

インタビュー中も治田さんの近くを離れなかったプーちゃん。
――今回、撮影でも一緒に写ってもらったように、治田さんは何匹かの猫を飼っていますが、治田さんにとって猫はどういう存在ですか?。
治田:猫は家族ですよね、俺もかみさんも猫好きなんですよ。猫によく話しかけるし、いろんなエピソードがあります。逝く時は必ず休演日とか稽古休みの日でさ、俺に気を遣ってんだな~と感じるね。
チノちゃんっていう、十何年前に神奈川県の海老名市の原っぱで拾ってきた猫がいて。当時はちっちゃくて、まだ目も開いてなくて、捨てられてたって感じだったかな。それでも一生懸命生きてたから、治療のために動物病院へ通ってさ。注射一本1万円とか保険きかなくて、稼げど稼げど治療費に飛んでったいう(苦笑)。
そんなチノちゃんは、俺がつくった牛すじの煮込みが好きでねぇ。ほかの子は来ないんですよ。チノちゃんだけ、タタタタってやってきて。で、チノちゃんにあげるじゃないですか。そうしたら、いつからかペロっと舐めるだけで食わなくなったんだ。
「なんだよ、お前が欲しいっていうから、あげたのにさ」って。実は、口の奥に炎症ができてたみたいでね。食べないからどんどん痩せていって……。俺にはわかっていたんですよ、3日後に稽古休みの日があるから、その日に逝くだろうなって。そうしたら、本当にその日に逝ってしまって。昨年の9月の「生きる」の稽古休みの日。だから、かみさんと2人で看取れたんですよ。「(俺が自宅に帰る日を)待っててくれたんだね、ありがとうね」って。
最後に、治田さんにこれから挑戦したい役についてうかがった。
治田:いただいた役を深めるだけですかね。(演じる前に)役を研究するのが好きなんですよ。医者の役なら病院へ行き、役人の役なら市役所に行ってじーっと観察してたりとか。
でも1回だけ、(観察を)失敗したことがありますね。2017年に亜門さん演出・脚色のミュージカル「ピノキオ〜または白雪姫の悲劇〜」の狐役を演じることが決まって、これは狐を研究しなきゃなと思って多摩動物園に行ったんだけど、狐は夜行性なんだね、檻の中でただ寝てただけでした(笑)。

最終回を迎えて
我々3人でこの企画を始めた頃は、2020年のコロナ禍の真っ只中でした。あれから、何度か感染の拡大と縮小を繰り返し、現在はウクライナ情勢が落ち着きません。平穏な日常のありがたみを改めて感じつつ、コロナ禍という非常時でも、この企画を前向きにとらえ、協力して下さった表現者の方たちに感謝いたします(葛西亜理沙、南しずか、宮川舞子)
取材・執筆:南しずか 写真1~2枚目:宮川舞子 タイトルイラスト:小林一毅 編集:石田織座(JDN)
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)






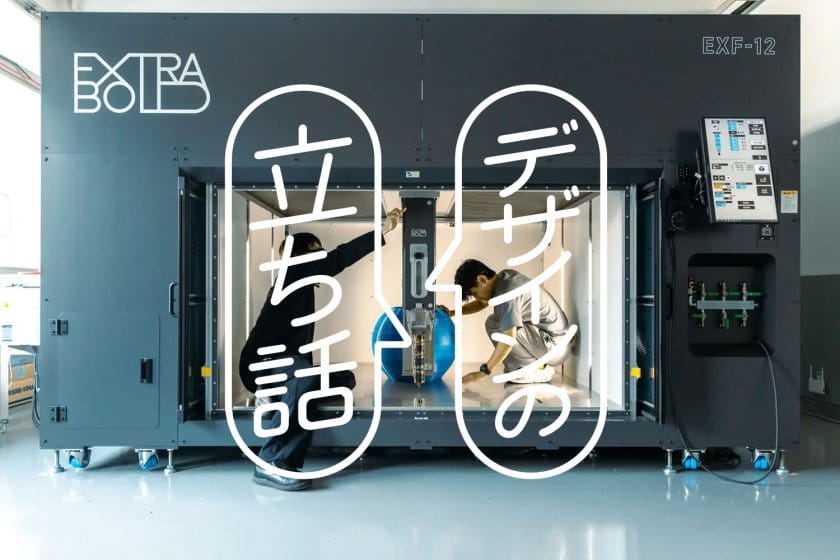





![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




