非日常を踊る 第15回:翔田真央

2020年春、新型コロナウイルス感染症の影響で1回目の緊急事態宣言が発令され、文化芸術活動にかかわる人たちは大幅な自粛を余儀なくされた。フォトグラファーの南しずかさん、宮川舞子さん、葛西亜理沙さんの3名が、撮ることを止めないために何かできることはないか?と考えてはじまったのが、表現者18組のいまを切り撮るプロジェクト「非日常を踊る」だ。
コンセプトとして掲げられたのは「コロナ禍のいまを切り撮ること」と「アートとドキュメンタリーの融合写真」という2つ。プロジェクトは、タップダンサーやドラァグクイーン、社交ダンサー、日本舞踊家などさまざまなジャンルのダンサーがそれぞれの自宅や稽古場という「裏舞台で踊る姿」を撮影した、2020年を反映するパフォーマンスの記録となった。
本コラムでは、フォトグラファー3名が想いを込めてシャッターを切った写真と、南さんが各表現者にインタビューした内容を一緒に紹介していく。今回は、2021年1月に撮影を行った、翔田真央さんの写真とインタビューを紹介する。
翔田真央/ストリッパー(撮影:宮川舞子)
2004年にストリップシアター渋谷道頓堀劇場でデビューした翔田さん。北海道から九州まで各地のストリップ劇場に出演している。特技は料理とけん玉。趣味は水泳、ゴルフ、ランニングなどのスポーツで、2015年からトライアスロンをはじめ、アイアンマンレース(スイム3.8km、バイク180km、ラン42.195km)で完走した経験がある。

撮影は翔田さんのご自宅で行われた。背景にはストリップのショーで使用している衣装や、アイアンマンレースで使っている自転車が写っている。
2004年9月21日、翔田真央さんはストリップデビューをした。
翔田:大学4年のとき、もう就職の内定をもらっててもおかしくない時期なのに、やりたい仕事がわからなかったんです。やりたいことがないから就活を頑張れず、ふわふわしていて……。そんなときに道劇(ストリップシアター渋谷道頓堀劇場)のスカウトマンに「ストリップ、興味ない?」と声をかけられまして。暇だし見たことがなかったので、タダでいいっていうから「じゃ、行ってみよう」と。
はじめて見たストリップに「わあ、きれいだな!」とけっこう衝撃を受けたんです。だからといって「これが私のやることだわ」とは思わなかったんですけど。そうしたら、劇場の社長さんが「やってみて、嫌なら辞めればいいじゃん」と話してくれて、「じゃあ、やってみます」ってなんとなく流れではじめたら、すごくハマっていきました。
ちょっとした好奇心からストリップにハマっていったという翔田さんに、まずはストリップの魅力についてうかがった。
翔田:ストリップ劇場は「本舞台」と「花道」、そして円形舞台の「盆」があり、その盆が回転式になっています。そういう日本のストリップの形というか、その空間が好きなんです。だから私はどこでも脱ぐわけじゃなくて、「ストリップ劇場以外では脱がない」という自分ルールがあります。
続けて翔田さんは、今までストリップを嫌いになったり、飽きたことがないと話した。
翔田:日本のストリップは1回16分くらいのステージで、登場してから脱ぐまで起承転結がありますが、演目するにあたって特に決まりごとはありません。自分の好きな衣装を着て、曲や構成も決めることができます。プロのダンサーじゃないのでプロフェッショナルな踊りはできませんが、逆に癖のある素人っぽい踊りがエロい雰囲気に結びつくなど、すべてが面白いなと思っています。
ストリッパーのみんなはストーリーにも凝りますが、基本的にお客さんは裸を見にきてるから、凝りすぎても仕方がない。そこら辺の塩梅は難しかったりするけど、それもまた楽しかったり。だから飽きたことがないのかもしれません。

さまざまなポージングでテスト撮影が行われた。
ストリップというと、仕事のことを家族に隠してる人もいる業界だと聞くが、翔田さんにその点についてもうかがった。
翔田:そうですね、10年以上やっていても、ずっと隠してる人もいます。私はデビューして半年ぐらい経った時に両親に伝えました。大学を卒業してから何の仕事をしているのか親が不審に感じていたし、私は「楽しいから続けたい」と決めていたので、もう隠していられないなと。両親は昔から「やる」と言い出したら絶対やるという私の頑固な性格を知っているので、「応援はできないけど、反対もできない」と言われましたね。
それから実家と疎遠になるわけでもなく、デビューから10年経った時に、お父さんから「なんの仕事であれ、10年間、一つのことをやるというのは立派だと思うぞ」と褒められたのは、ちょっと嬉しかったです。最近だと「まだ、ファンはいるのか?」と心配されたり(苦笑)、うちみたいにすごくオープンな家族は、この業界では珍しいかもしれません。
かつては日本各地にあったストリップ劇場だが、近年閉館が相次いでることについての胸中もうかがった。
翔田:それこそデビューした頃は、今より倍ぐらいの劇場がありました。ストリップ劇場でしか、裸を見られる機会がなかったから。今は、ネットとかいろんな方法で見れちゃうし。だから最近は公演をしてもいつもお客さんが満員とは限りません。この業界の衰退を目の当たりにしてて、ちょっと寂しい思いももちろんあります。でも、知らないだけで実際に見ると楽しいかもしれないから、まだ見たことない人は試しに見に来てほしいです。
あと個人のブログで、トライアスロンやけん玉、食べ歩きとか、趣味や特技について書いています。ストリップのことを知らない人が多いから、「ストリップって、いまの時代こんな感じなんだ」と、何かしら人の目に留まるきっかけになってくれたらいいなと思っています。
自身が考える“理想のステージ”について聞くと、詰まるところはやはり“エロス”だと話す。
翔田:「ストリップって芸術的だね」と言われるご時世になりましたが、なんかこう「あの子のステージ、エロかったなあ」と、お客さんの頭の片隅に残るような感じだといいかな。変な話、お客さんが家に帰って、私のステージを思い出してくれたら万々歳みたいな(笑)。
だから体つきは、ストイックに筋トレしすぎないぐらいがちょうどいいと思います。むしろ「ちょっと肉付き良すぎかも」ぐらいがステージの照明に映えて、また、そこにお客さんもエロスを見出したりすると思うから。

コロナ禍の1回目の緊急事態宣言時についても、状況を思い返していただいた。
翔田:最初に緊急事態宣言が出された2020年4月7日は、広島の劇場に出演していましたが、急きょ休演になってしまいました。全国の劇場も閉まったので仕事はないし、「さて、どうしようかな」と。そうしたら、その劇場の社長が「楽屋に寝泊まりしてええぞ」と言って下さって。だから、そのまま2カ月ぐらい楽屋に泊まらせてもらったんです。東京に帰るより地方にいた方が安全かもと思ったことと、広島在住の頼れる友達もいたので。
地方の楽屋って、お風呂や台所があって寝泊まりできるようになってるんですよ。個室だったり大部屋だったり各劇場によって違いますが、広島は個室でした。ただ、何もやることがないのは精神衛生上まずいから、「なにかできることあるかな?」と考えて、「あ、ウーバー(Uber Eats)の配達しようかな」とひらめきました。すぐに自転車を手に入れてはじめたところ、最初の2週間ぐらいはまだ配達員がそこまでいなかったのか「わりといい小遣い稼ぎになるな」という感じだったんですが、それ以降は配達員が増えたのか、稼働してもそんなに稼げませんでした。
まあ、お金よりもただ何かしたくて、ウーバーをやっていたところがあったから「もういいや、今日は昼から飲んじゃおう!」みたいな日もあったり(笑)。料理してお酒飲んで、眠って、朝起きたらウーバーに行って、という生活をしていました。そうこうしているうちに、2020年6月1日から全国の劇場が再開することになり、私も渋谷の劇場の出演が決まったから東京に戻りました。
最初の緊急事態宣言以降、現在も感染者数が増えたり減ったりしつつ、まだコロナ禍は続いている。
翔田:それこそコロナ禍になって「もう2度とストリップはできないかも」と思ったんですよ。劇場は狭い空間だから、もうこのまますべての劇場が閉まっちゃうのかなって不安になりまして。だから1回目の緊急事態宣言が発令された直後の2020年4月7日の最後のステージでは「これがいきなり(現役)最後かもしれない」と涙が止まりませんでした。演目中に泣くなんて、はじめてでした。
でも約2カ月後に「あら、再開できたじゃん」となって、嬉しかったです。見慣れた顔ぶれの常連さんは、マスクをして来て下さって。求めてくるお客さんたちがいるうちは、できるだけ劇場も減ってほしくないしという状況で、2回目の緊急事態宣言が出て……。
基本、ストリップは1日4回公演ですが、コロナ禍では3回公演にした劇場が多くて。ただでさえ劇場は経営が大変なのに、厳しさに加速がかかっていましたね。今までみたいに仕事があって当然のご時世ではなくなっちゃったから、この仕事だけで食べていくって「本当に大丈夫かな?」と、ちょっと危機を感じました。
もし引退することになったら、4年前にピラティスの資格をとって続けているので、そういう方向にいけたらいいですね。あとは、ロング(アイアンマンレース)に出たいかな。30代前半にトライアスロンを始めて、6年目ぐらいです。2018年にオーストラリアのケアンズではじめてロングに出場しました。私、けっこうサボり魔なので、バーっと頑張ったと思ったらまったく何もしなかったり。けっこう波がありますが、当時は付け焼き刃で行ったわりにはそこそこできた感覚があったので、サボり魔を封印して、いけるところまで頑張って、挑戦したいと思っています。

2021年12月現在は、ここ最近のストリップ業界は4回公演に戻ったり、お客さんも少しずつ戻ってきたりと完全とはいえませんが活気は戻りつつあります。コロナ禍を通して、これまで当たり前のようにステージに立っていたことが、当たり前ではないと思い知ったので、以前にも増してステージで踊れることを「ありがたいことだなぁ」と感じている日々です。
取材・執筆:南しずか 写真1~2枚目:宮川舞子 タイトルイラスト:小林一毅 編集:石田織座(JDN)
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)











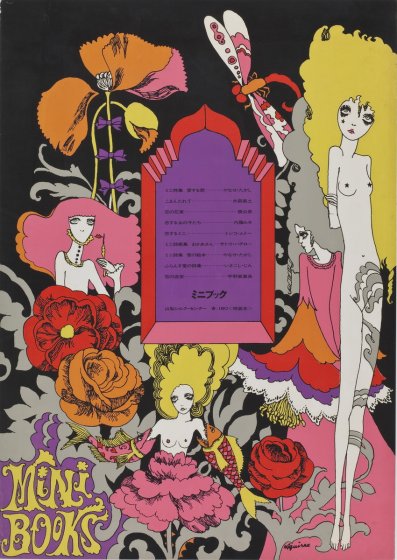
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




