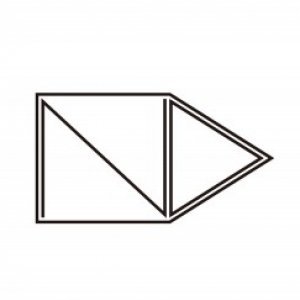非日常を踊る 第14回:前田あつこ

2020年春、新型コロナウイルス感染症の影響で1回目の緊急事態宣言が発令され、文化芸術活動にかかわる人たちは大幅な自粛を余儀なくされた。フォトグラファーの南しずかさん、宮川舞子さん、葛西亜理沙さんの3名が、撮ることを止めないために何かできることはないか?と考えてはじまったのが、表現者18組のいまを切り撮るプロジェクト「非日常を踊る」だ。
コンセプトとして掲げられたのは「コロナ禍のいまを切り撮ること」と「アートとドキュメンタリーの融合写真」という2つ。プロジェクトは、タップダンサーやドラァグクイーン、社交ダンサー、日本舞踊家などさまざまなジャンルのダンサーがそれぞれの自宅や稽古場という「裏舞台で踊る姿」を撮影した、2020年を反映するパフォーマンスの記録となった。
本コラムでは、フォトグラファー3名が想いを込めてシャッターを切った写真と、南さんが各表現者にインタビューした内容を一緒に紹介していく。今回は、2020年10月に撮影を行った、前田あつこさんの写真とインタビューを紹介する。
前田あつこ/北インド古典「カタック舞踊」ラクナウ流派の舞踊家、振付家(撮影:葛西亜理沙)
6歳からカタック舞踊に親しんできた前田あつこさん。2005年より創立50年を超えるインドの「KADAMB舞踊団」に留学経験を重ね、美しい振付で著名なクムディニ・ラキア氏に師事。インドで研鑽を積みつつ、国際文化交流の場で多くの舞台を踏んでいる。

カダムジャパンを主宰する前田あつこさん。日本文化を反映したカタック舞踊作品の創作に夢中。撮影は前田さんがコロナ禍の自粛期間中によく訪れたという公園で行われた。
インド北部で宮廷舞踊として発展したカタック舞踊は、4000年の歴史を誇るインド古典舞踊の4大流派の一つである。カタック舞踊の特徴は、足首に巻きつけるグングル(鈴)の数が100~200個と多いことだ。「自分の体ひとつあれば、リズムを刻んで楽しむことができます」。前田さんは稽古場に入り、最初の足踏みで「シャン!」と鈴の音が鳴る瞬間が好きだと言う。
前田さんは6歳の時から東京都八王子市にあるヤクシニィ・カタックセンターへ通いはじめた。日本舞踊やバレエも選択肢にあったが、子供心にインドの装飾品のエキゾチックな美しさに魅了され、なぜかインド文化が性に合ったという。
前田:教室に同世代の子どもが誰もいなかったんです。友達もライバルもいない中、先生からは特に褒められるわけでも、特に指摘されることもなく、ただひたすらのんびりと通い続けました。小学生のうちにインド公演へ連れて行っていただけたのは貴重な経験でしたけれど。
大学時代と会社勤めをする間に一旦カタック舞踊から離れた前田さん。生活をする中で何か物足りないと感じ、カタック舞踊を再開したところ、「やっぱりこれだ!」と直感したという。そこで会社を辞め、カタック舞踊に専念しはじめた。

撮影に適した動きを確認する前田さんと、カメラマンの葛西亜理沙さん。
前田:専念するといっても、日本の場合、インド舞踊はそこまで商業的に確立されていないのでセルフプロデュースが必須となります。自分で売り込んで、自分で企画・運営をして、自分で出演しないとなかなか人目に触れないんですよ。子どもの時に習っていた先生たちも、そういうふうに活動していましたね。
駆け出しの頃で思い出すのは、2005年の愛知万博です。インド留学の合間に興味本位で万博会場でバイトをはじめて、インド館で踊る機会を得たんです。名古屋のミュージシャンたちと毎日のようにパビリオンで踊っていました。ギャラはお金ではなく、カレーでしたけど(笑)。
その後前田さんは、圧倒的に不足していた知識を得るためにインドに通うようになった。振付や舞台の美しさに惹かれ、カタック舞踊界で著名なクムディニ先生の師事を仰ぎ、そこでダンサーと振付家の立場を再認識したり、舞台制作について知識を得ることになった。インドで習ったことを日本で稽古して自分の色に変えていく、セルフプロデュースの舞台活動も開始。2007年から「カダムジャパン」というダンスインスティテュートを主宰し、仲間を得るべく振付指導をはじめた。さらに第1子の妊娠を機に、ほかの日本人インド舞踊家にも目を向けるようになった。
前田:妊婦の体で舞台に上がることに抵抗があったので、依頼いただいた舞台をほかのインド舞踊家さんに振って、自分は裏方に回ることにしたんです。そうしたら、今まで知らなかっただけで、日本中のインド舞踊を深く勉強している人たちに出会うことができました。
仲間たちと一緒に公演することで得られる刺激は、セルフプロデュースで自分自身と向き合っている時とは違った喜びということを知った。
22020年もさまざまな舞台公演を企画し、カダムジャパンのカンパニーとは「ニューヨーク・カタック・フェスティバル」に参加するため、渡米する準備を進めていた。だが、1回目の緊急事態宣言が発令されると、すべてのスケジュールは白紙。前田さんの夫の仕事も全部飛び、2人の子どもたちも休園となり、家族みんなで2カ月間ほど完全な自粛生活となった。

三つ編みにした髪の毛が動かないよう、安全ピンで位置を固定する様子
前田:子どもたちはコロナなど関係ないんですよね。毎日遊ぶし、毎日食べるし、成長もする。そんなポジティブな姿に救われつつ、毎日公園にいました。
踊りを再開できたのは2020年5月末のこと。1回目の緊急事態宣言が解除された数日後に、1人で稽古場へ出向いた。いつもは無心で取り組む基本の足踏みなのに、無意識のうち涙がこぼれてきた。
前田:踊ることができない。仲間に会えない。先が見えない。いつも通りのことができないという日常を逸脱した現状に、実はすごくショックを受けて、すごくストレスを抱えていたんだなと実感しました。
その一方で、パンデミックは思いがけぬ副産物をもたらした。インド古典舞踊は、伝統的に先生から生徒へ口承で伝えられてきた文化である。インドに渡航して稽古場へ通うことが、本格的にインド芸術を学ぶ唯一の手段だったが、コロナ禍をきっかけに世界中がオンラインで繋がったのだ。
例えば、伝統的な歴史ある機関がオンラインショーを主催したり、イギリスやインドなど時間軸が違うアーティストたちがチームになってオンラインワークショップを開催し、地球のあちこちから100人もの参加者が受講した。もれなく前田さんも自宅から受講した。自宅の台所で、隣の部屋に子どもたちが寝ている中、本場のカタック舞踊に触れられるなんて、コロナ以前には考えられなかった。
前田:業界が大きく変わっていく!と、衝撃を受けました。最初にオンラインの世界を牽引した先輩方には感謝でいっぱいです。伝統を変えることは批判されるリスクもあったと思うんですよね。でも、この前例のない試練の時期に挑戦をされて「世界中でシェアしていこうね!」と、ポジティブなメッセージをいっぱい送ってくれまして。「ああ、なんて素敵な先輩方がいるんだろう!」と幸せな気持ちになりました。
インドに行かなくても学べるようになったことで、自身の存在意義を考え始めた。
前田:「自分はなぜそこに時間をかけるんだろう?」とか「自分のアイデンティティは何?」とか、仕事のひとつひとつを新しい目線で見つめ直さなくてはいけませんね。
自ら道を切り開き、日本のインド舞踊界を繋げてきた。世界が繋がったいま、今度はどんな役割を担うのだろうか。

取材・執筆:南しずか 写真1~2枚目:葛西亜理沙 タイトルイラスト:小林一毅 編集:石田織座(JDN)
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)











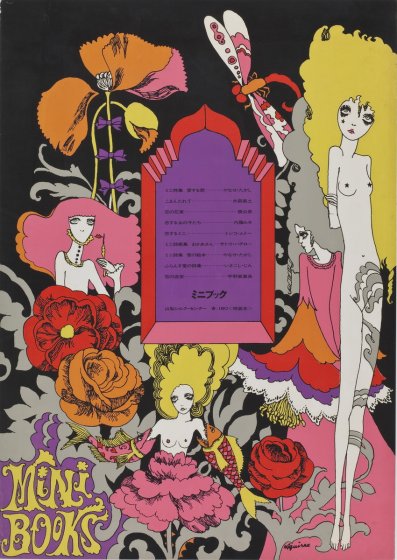
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)