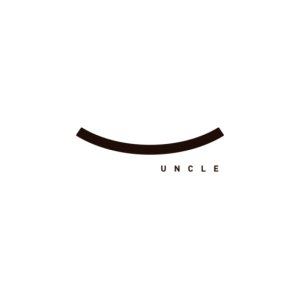「入りやすく、出やすい」、R2ならではのビルの魅力
――外観について、窓枠などに丸みがあってレトロな印象も受けます。意匠面は新旧を融合させるイメージで考えられたのでしょうか?
北村:そうですね、改修前は全体に小さい窓がリズミカルに配置されていました。この窓の柔らかい雰囲気を残しつつ、ビルの顔となる大開口のモダンな印象が合わさってバランスがとれたかなと思っています。繊維業者さんも多い場所柄なので、クールになりすぎず、柔らかさも出したいよねという話し合いの結果です。

改修後のビル外観
渡邉:こういった窓の配置は、新築ではあまりしないですよね。古い窓は表面が少し凹んでいて、新しい窓は外壁と揃えて凹凸のない面になっていたりもします。こうした意匠はR2ならではの味わいになっているのではないでしょうか。
――改修後の反響はいかがでしたか?
松本:まず最初に、建物を見た方から「建て直したの?」と言われましたね。内装だけでなく、外装のタイルも劣化したものはすべて張替え、色も塗り直しているので新築だと思われるくらいきれいになったということだと思います。

松本:リーシング開始から約半年で満床になったことからも、一定の評価をいただいているのかなと感じています。具体的な評価の理由は、これからアンケートを実施しながら探っていけたらと思いますが、デザインに加えてリーシングの仕方にもメリットを感じていただけているのかなと思っています。
というのも、「ウィンド小伝馬町ビル」は創業間もない企業をターゲットに、デスクやチェアなどがすべてそろった家具付きセットアップオフィスとして貸し出しています。初期費用を抑えつつ、パソコン一つですぐに働ける。「入りやすく、出やすい」という点も評価につながっているのではないかと考えています。
――セットアップオフィスとして貸し出すにあたって、丹青社が空間づくりで培った強みも発揮されているのでしょうか?
松本:限られたスペースでいかに使いやすいレイアウトを考えるかは丹青社の本業でもあります。その意味では、家具のセレクトや配置も含めてバリューアップにつながっているのではないかと思っています。

家具が一通りそろうウィンド小伝馬町ビルのセットアップオフィス
築古物件が「あえて」選ばれる―R2が見据える未来
――これまでの活動を踏まえて、R2のこれからについて教えてください。
北村:デザイナーとしてこのプロジェクトに参加してみて、表層的なデザインだけではなく、補強プランの段階からデザインで何ができるのか、新しい視点を持つことができたと感じています。
「ウィンド小伝馬町ビル」のように既存のストックを活用していくことがスタンダードな価値観になれば、世の中の流れも変わっていく。R2でその潮目をつくっていけたらいいなと思います。
渡邉:丹青社さんがR2をはじめたように、既存物件の利活用が注目されるのはとても喜ばしいことです。一方で、再生設計が「建て替えるお金がないから」というネガティブな理由で新築の代替案になってしまうのは、非常にもったいないと考えています。

渡邉:意匠を担うデザインと安全性などの技術面を担うエンジニアリングが分離してしまうと、「古くなったらまた壊す」といった本末転倒な結果になってしまう。デザインとエンジニアリングが統合する必要があって、統合されることで新築には出せない再生設計ならではの創造性も生まれる。
例えば、その当時ならではの技術でつくられた部材や経年劣化で生まれるタイルの味わい。それらを活かして建物を再生させることで、「古い=おしゃれ」という考えやノスタルジーとはまた違った、R2じゃないとつくれないものができると信じています。
松本:このプロジェクトを通して、築古物件を選ぶ価値をつくりつづけていきたいです。築年数の長い物件は選ばれづらい傾向にありますが、磨けば光る物件が世の中にはたくさんある。そういった物件の魅力を引き出す技術こそ、デザインやエンジニアリングだと思います。
また、物件を改修して終わりではなく、その物件の持つ魅力をしっかり伝えていくことも重要です。自分たちがその物件のどこに魅力を感じ、どのように生まれ変わらせるのか。そういった想いをオーナーさんに真摯に伝え、「愛着のある自分のビルをぜひ丹青社に任せたい」と思っていただけるような取り組みをしていければと思います。
現在、R2ではほかに2棟のビルを所有しており、バリューアップを進行中です。現在は買取再販がメインですが、今後は築古ビルの再生を総合的に支援する事業へと進化させていきたいと考えています。
オーナーの中には、売却するつもりはなくても、老朽化したビルにどのように手を入れるべきかわからず困っている方も多く見受けられます。そんな時に、建築改修工事から物件管理までを一貫して提案できる体制を整えれば、丹青社としてさらなるビジネスチャンスにつながっていく。R2はそんな可能性を生み出せるプロジェクトだと確信しています。

文:濱田あゆみ(ランニングホームラン) 撮影:西田香織 取材・編集:萩原あとり(JDN)
- 1
- 2
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)












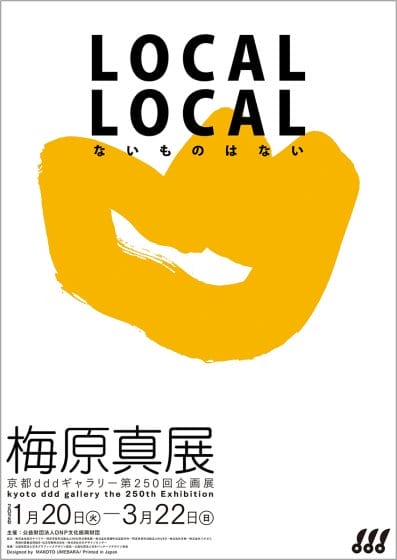
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)