
10年ぶりに再開される、「シヤチハタ・ニュープロダクト・デザイン・コンペティション」。テーマは「しるしの価値」
――いま「シヤチハタ・ニュープロダクト・デザイン・コンペティション(以下、SNDC)」を復活された理由を教えてください。
この10年で、印章や文房具を取り巻く環境は劇的に変化しました。弊社でも、オフィスや個人向け商品に付加価値をつける一方で、販売20年以上になる電子印鑑システム「パソコン決裁」の改善や個別認証技術の開発など、デジタルとITを融合したプロジェクトを行っています。こうした「印章から認証」の流れを通じ、未来の方向性を新たに探ってみたいという思いから、SNDCの再スタートを決めました。
より幅広く捉えられる「しるし」をテーマとしたのは、その可能性を考えてのことです。「しるし」は世界的に見ても、自分を「何か」で認証するものですよね。例えば私は、世界の人々が自分を示すマークを決め、それがデジタルやアナログで認証されるような仕組みができたらおもしろそうだなと思っています。こんな風に、自分の痕跡の在り方を捉え直す上でも、原点回帰と言えるテーマにできたことは意義があると思っています。

シヤチハタ株式会社代表取締役社長・舟橋正剛さん
――今回から「未来ものづくり振興会」が主催となったのはどのような理由からですか。そもそも、どのような団体なのでしょうか?
以前のSNDCはものづくり中心のコンペであり、社内での判断だけにテーマ設定や内容に偏りが出やすいジレンマがありました。ものづくりの面はもちろん今後も重視しますが、未来は未知数なので、シヤチハタとは別の企業が組むこともあり得ます。その時にブランドの名前や歴史がかえって枷にならないよう、また柔軟な動きができるようにと立ち上げた団体です。弊社の企業理念『明日の「便利」「楽しさ」「安心・安全」を世界へ』を、より大きな器で叶えられる集まりにできればと思っています。
――SNDCの新たな展開に不可欠の存在だったということですね。
はい。休止中の10年は、過去のアイデアを棚卸しし、社会のニーズを勉強し直す期間でもありました。未来は想像できずとも、10年間を振り返れば見えることがあります。そこで気づいたのは、現代のスピード感で商品やサービスを出す際に必要なのは、フットワークの軽さだということでした。そこでブランドに縛られない仕組みをつくれば、社会貢献に繋がるものや提案がより生まれやすいのではと考えたのです。
――再開の理由には、オフィス環境や社会変化の影響もあるというお話でしたが、直近で気にされている事象があれば教えてください。
1月に政府が出した「デジタル・ガバメント実行計画」です。地方行政も含めてデジタル化を推進するという内容だけに、ハンコを使う機会が減ることは必至です。銀行でも届出印なしで口座が開ける所が増えていますし、ハンコを使う場面は減っていくでしょう。まだ安定はしていますが、メーカーは社会変化や技術革新の影響が徐々に出てくるので、先手を打ちながら開発し続ける必要があるんです。

――例えば、御社の技術としてはどのようなものが?
そうですね。まず、デバイスやOSを問わず、印影をワンタッチでファイルに押すことができる安価なクラウドサービスがあります。基幹システムを組まれるIT業者さんにも「書類にはシヤチハタが必要」と感じていただける付加価値や、互換性に富む仕組みを意識して今までも開発してきました。また最新技術には、既存の製造ラインやワークフローを変えずに個体を識別できる個別認証があります。社風を活かし、「シヤチハタっぽい」と言われるニッチな強みをどんどん増やしていきたいですね。
――未来への準備を進めつつ、一方のSNDCでは印章や認証、個人の痕跡につながる「しるし」を新しい視点で捉えようということですね。
ですから、技術にとらわれず「こんなことができたら面白そう」といった形で、自由に考えていただければと思います。いまは希望や思いつきを形にできたアプリやスタートアップ企業が伸びる時代です。あの思考やスタンスを私たちメーカーも見習わなければなりません。若い会社と同じ動きは無理だと言う社員の気持ちもわかりますが、それだけではそこで止まってしまいますからね。
――シヤチハタにとって新たなチャレンジとも言えそうです。
過去のSNDCとは大きく異なる内容になりそうで、私も非常に楽しみです。今回はテーマが「しるしの価値」なのでシヤチハタの印象が強いかもしれませんが、今後は私たちの名前が出ない時があってもいいと思っています。未来ものづくり振興会が主催となることで、新たな方向に広がっていくことを期待しています。

審査員は錚々たるメンバーがそろった。(左上から右下)喜多俊之さん、後藤陽次郎さん、中村勇吾さん、原研哉さん、深澤直人さん
――ちなみに、受賞作品はどのような形で展示されることになりそうですか?
今回は発表会やトークショー、受賞作の展示を企画中です。受賞作品を公開することで受賞者や応募者に我々や審査員の思いを伝える新たな場になるのではないかなと。また、展示作品ヘの感想や弊社へのご意見もうかがえるのではないかと考えています。
――10年後の自分を示す「しるし」がどんな形になるか。ポジティブな作品がたくさん集まるといいですよね。
そうですね。デジタル化されても「個人の認証」という意味は変わりません。業界によってはアナログの形が残る場合もあるはずですし、一つの文化として世界に残したいものでもあります。そんな「しるし」を大切にしていくためにも、みなさんからのご応募をいただけると嬉しいです。

取材・文:木村早苗 撮影:木澤淳一郎
■応募受付期間
2018年4月1日(日)~5月31日 (木) 24:00まで
■賞
・グランプリ(1点) 賞金300万円
・準グランプリ(2点) 賞金50万円
・審査員賞(5点) 賞金20万円
・特別審査員賞(1点) 賞金20万円
※受賞作品は都内で展示予定
■テーマ
「しるしの価値」
自分であることの「しるし」(アイデンティティ)を表すためのプロダクト、または仕組みを募集
※応募は1人(1グループ)1点まで
■参加方法
公式ホームページの応募フォームより
※一次審査通過者は模型を提出
■参加資格
日本語でのコミュニケーションが可能な方
入賞した場合、2018年10月12日に都内で行われる表彰式に参加可能な方
※未成年は受賞した場合に親権者の同意書が必要
■審査員
(審査員)
喜多俊之(プロダクトデザイナー、喜多俊之デザイン研究所 代表)
後藤陽次郎(デザインプロデューサー、デザインインデックス 代表)
中村勇吾(インターフェースデザイナー、tha.ltd 代表)
原研哉(グラフィックデザイナー、日本デザインセンター 代表)
深澤直人(プロダクトデザイナー、NAOTO FUKASAWA DESIGN 代表)
(特別審査員)
舟橋正剛(一般社団法人未来ものづくり振興会 代表理事、シヤチハタ代表取締役社長)
岩渕貞哉(美術手帖 編集長)
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)




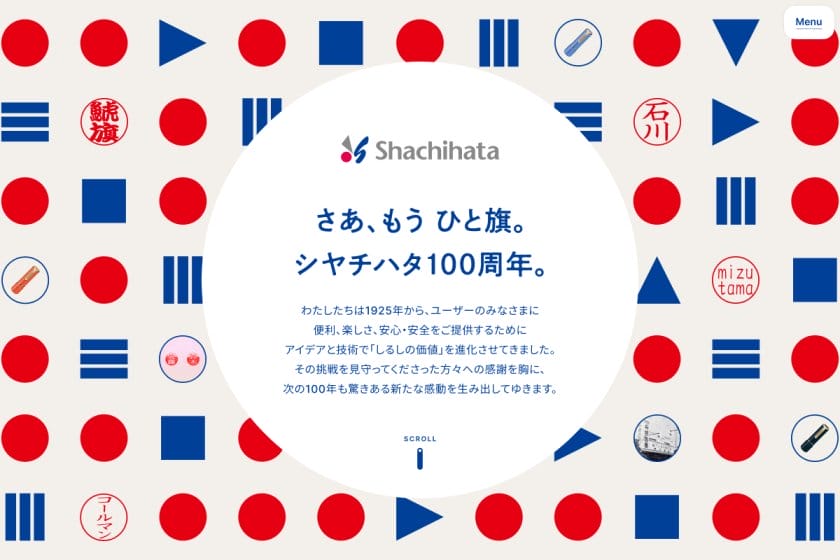

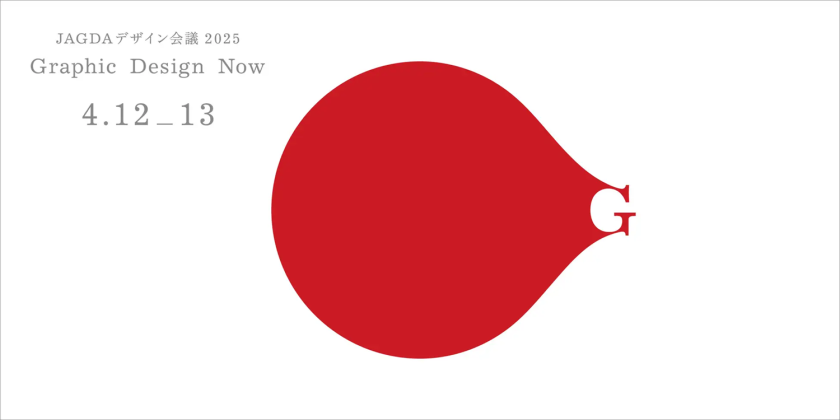









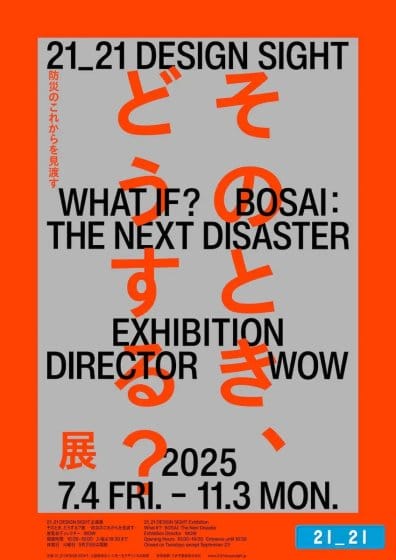
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




