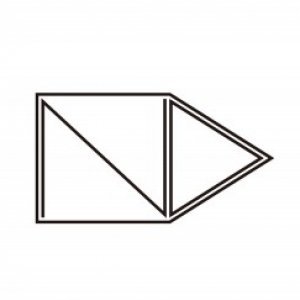“魔法”探しに夢中だった幼少時代
幼い頃は魔法の存在を信じて疑わない子供でした。幼稚園の時に行ったバス合宿での体験が、いまの僕を形づくる軸になっています。当時の送迎バスの運転手さんは手品が得意で、合宿に行くと寝る前に園児を講堂に集めて手品を披露してくれていました。たしか初めて泊まりで行った箱根の合宿だったと思いますが、みんなで手品を見ていると、運転手さんがシルクハットの帽子の中に卵を割り入れて園児の方に近づいてきました。そして僕と目が合ったかと思うと、シルクハットを僕の頭にパッとかぶせたんです。何が起きたのかわからず、恐怖で肩がすくんでしばらく動けませんでした。すると、彼が僕の目を見てウインクしました。言葉は発していないのに、なぜか「大丈夫だから安心してね」と言われた気がして、一気に緊張が解けたのを覚えています。
その一瞬の出来事が10分にも30分にも思えて、ウインクというコンタクト一つで確かに会話が成立したし、お互いの心が繋がった瞬間でした。その時の体験が強烈で、「あの人は言葉を発しなくても会話ができる魔法使いなんだ!」と思ったんです。魔法の存在を信じるようになったのはその時からですね。

MASARU OZAKI
モーショングラフィックスをデザインの原点としながら、独自の世界感をクリエイティブに織り込む。ジョン・ローレンス・サリバン、ニールバレット、ディーゼルをはじめとする世界を代表するトップブランドのファッションショー映像や空間演出なども手がけ、2010年5月開催の上海万博「日本館」では、ORIGAMIWALLなど多くのプロジェクション・マッピング演出を創作、メインエントランスには立体彫刻やアート作品が常設されるなど、その活動はワールドワイドに拡がる。2011年より自らの 「THINK GREEN」への着想を表現すべくアート・ プロジェクト「LightTreeProject」 を開始する。
家に帰ると両親に、「将来は魔法使いになる」と宣言しました(笑)。そこから魔法探しがはじまります。例えば街でパントマイムを見ると、魔法使いだと思って見入ってしまうんです。当時の僕にとって不思議なことはすべて魔法でした。触れないもの、心で感じるものに魔法のヒントがあるんじゃないかと、とにかくそれを探してばかりいました。
おもちゃを買ってもらうと、どんな魔法で動いているのかが知りたくて、必ずドライバーを持ち出してひっくり返していました。だから、そのおもちゃでほとんど遊べないんです(笑)。銀座の博品館に「おもちゃ病院」というのがあって、白衣を着たお医者さんがおもちゃを直してくれるのですが、そこに持っていくのもまた楽しかったんですよね。おもちゃを分解してがっかりするよりも、なんで元に戻せないんだろう? という好奇心の方が断然強い子供でした。
映画『トロン』に魅せられ、CGアニメを自作
僕が幼かった頃はおもちゃもゼンマイ仕掛けで、中を開けるとからくりがわかって分解も楽しかったのですが、「基板」が主流になると、中を開けてもチップしか出てこなくなりました。それからはこのチップの中にきっと魔法の仕掛けがあるんだと思うようになり、小学校6年生ぐらいになるとコンピュータに興味をもちはじめました。。小学生の僕にはもちろん情報はなかったのですが、ラッキーなことに家の前にあった喫茶店に理工系の大学のお兄さんたちがたむろしていたので、そこで色々教えてもらっていました。
その頃、ウォルト・ディズニーが『トロン』(1982年)というSF映画を公開しました。全編にわたってCGを多用した初めての映画で、それを観た僕は現実では考えられないカメラワークやスピード感のあるチェイスシーンに、子供ながらに強く惹かれました。それからというものCGに興味が沸き、「自分でトロンのような世界をつくりたい」と思うようになったんです。
当時のコンピュータといえばNECのPC8801や9801なんかがステータスでしたが、30万円以上するので小学生には到底手が出ません。そこで僕が手に入れたのが、『ぴゅう太』というトミー(現タカラトミー)が59,800円で発売していた16bitコンピュータでした。よく見ると、「グラフィックスコンピュータ」と書いてある。「これだ!」と思って(笑)。その『ぴゅう太』を使って初めてつくった作品が、カモメがパタパタとドットで動くCGアニメーションでした。当時の640×480のピクセル数で1ドットだと結構大きかったのですが、それでも6〜7個の点を描けば縮小されて、しかも液晶ではなくブラウン管なので少しぼやけることでちゃんとカモメに見えるんです。ただ、想像していた『トロン』の世界観には程遠かった。『トロン』がつくりたいのにつくれない……。そのジレンマと常に葛藤していたのが中学生くらいまでです。ここが僕の土台で、いまにつながるきっかけになった出来事ですね。
技術を追いかけ腕を磨いた20代
20代の頃は、デザイン業界でも映画の世界でもCGブームでした。僕はというと、クリエイター2人とシェアハウスで生活しながら、モーショングラフィックスを教える講師をしていました。ものを観察しないことにはディテールも追えないし、ものづくりには何より観察が大事だと思っていたので、とにかくいろんなものを観察しました。
映画の『タイタニック』が公開された時は、映画館に4回観に行きました。笑い話ですが、CGのシーンばかりに気を取られて話の内容は最後までわかりませんでした(笑)。あとは道端も大好きでしたね。歩いていてブロック塀に苔が生えているのが気になると、その苔をずっと観察していました。「お前はなんでここに生えたんだ?」からはじまって、そこから想像の世界が広がるんです。

作家としての活動ももちろんしていましたが、一方で食べていくための仕事も必要だったので、請負仕事もしていました。テレビのCGパーツやオープニングタイトルをつくるほか、クラブVJ、ミュージックビデオやプロモーションビデオの監督なんかも。当時は僕のつくったCGアニメーションを実験させてくれる場がクラブだったので、作品発表も兼ねてクラブにはよく通っていました。実はVJマサルという名前で、MTVで司会をしていたこともあります(笑)。海外アーティストが来ると、僕がインタビューアーとして彼らに質問していました。
いま思えば何でもやっていましたね。本来ならクリエイタールームにいるはずで画面に立つ側にいることに違和感も感じましたが、音楽も好きだったのでこれも経験のひとつとして吸収しようと。実際にその時に得たこともたくさんあり、おもしろかったですよ。僕は会社に所属せずフリーランスでずっとやってきたので、師匠がいないんです。だからとにかく現場で覚えて、自分で工夫することを身に付けました。鍛えられましたね。
- 1
- 2
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)











![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)