幸福の解体新書-はじめに(後編)

読者のみなさんはじめまして。コンセプトを軸とした企業やサービスのクリエイティブコーチをしているさわくんです。特に「コンセプト」に主眼をおいて活動しており、法人であろうがサービスであろうが、それそのものが自然と躍動していくような根幹を形成しながら、ブランディング×コーチングをおこなっています。
このコラムでは、巷にあふれている幸福にまつわる言葉と格闘し、その本質を疑っていきます。
前編では、「なぜ、デザイン情報メディアで幸福論などという胡散臭い話を連載するのだろうか。そもそも全然関係ないではないか」という、おそらく読者の中に浮かんでいる疑問に対して、
・コンセプト≒幸福という話
・幸福をクリエイターが学ぶ重要性
という観点から、本コラムを実施する理由に対する解説をおこなっていました。後編では上記の2点に加えて、「幸福を学ぶ手段は、幸福を疑うことによって成せる」という重要な点に関して解説していきます。

「幸福を疑う力」が、「幸福のクオリアを掴む力」となる
前編を読むうちに、次のような疑問が浮かんできたのではないでしょうか。「幸福のクオリアを掴むことの重要性はわかった、それならなぜ、幸福のクオリアをレクチャーするのではなく、幸福のクオリアを解体するなんて嫌味なことをするんだ」と。
この疑問に対して端的に述べるのならば、世の中にある幸福の概念を適切に疑う力を高めることこそが、顧客が本当に望む幸福のクオリアに迫る唯一の方法だからです。
たとえば「挑戦」という言葉は、企業のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)などでよく見かけることはないでしょうか。犬が歩くとよく棒に当たるらしいのですが、それと同じくらい出くわす「挑戦」という文言。しかし、文言上で頻発するからといってすべての「挑戦」が当然ながら同じ意味ではありません。その企業が語っている「挑戦」というクオリア(言葉の質感)を掴む必要があります。
つまり、「その言葉は何を意味しているのか?」を問うわけです。
そしてクオリアを把握したとしても、それを「かしこまりました」と請け負ってクリエイティブをつくるのもよろしくはありません。なぜなら人は「そもそも依頼する時点で何をお願いすればいいかを完全に把握していない」、もっというならば「自分が何を願っているかについて、願いそのものを解像度高く理解している人はいない」からです。
読者のあなたも自分に問いを投げかけてみたらわかると思います。仮に自分が会社をつくるとして、その企業理念をパッと考えてみたとしましょう。そこで軸にした言葉こそ自らが本当に望んだ言葉である、と確信できる人はどれほどいるでしょうか。
つまり、「その言葉に宿るクオリアを本当に望んでいるのか?」を問う必要があるのです。
仮に問いを投げて揺さぶられたとして、揺さぶられた当人は困惑するはずです。「では、どうすればいいのだ」と。そこで考える必要があるのは、「そもそもなぜその言葉に宿るクオリアを”望まされたのか”」ということ。ここで考える必要があるのは2つ、個人の文脈と社会の文脈です。
無意識にする行動、使う言葉には必然性があります。なぜなら「なんとなく」選択する行動や言葉の選択肢は無限にあるからです。無限にある中で、その言葉を使うということは何らかの傾向があります。
では、その傾向はどこから生じるのか。それは、その個人が育ってきた環境による積み重ねに由来します。個人が育ってきた環境は時代の空気感を色濃く反映します。無意識の根源を辿っていくと、自然と周囲の環境に辿り着くのです。言葉だけ、個人の経験だけを辿っても本当の意味でその言葉のクオリアは把握できないのです。

個人の文脈、社会の文脈について、具体例を踏まえて解説していきます。まずは個人の文脈に関して。
今回は「挑戦」をテーマに置いていますが、みなさんの中にもこうした「〇〇って根拠はないけど良いと思っている概念」はたくさんあるはず。それこそ本コラムのテーマである「幸福」などもそうでしょう。そのため、ここからは「挑戦」を自分が「良いと思っている概念」に置き換えてお読みください。
たとえば、その社長が幼少の頃にいじめられ、その反動から「挑戦して見返してやる」という信念が形成されたとします。その人はその瞬間から、「どうしたらもっと挑戦できる?」「どうすれば見返せる実績が手に入る?」と考えるようになるでしょう。その問いに基づき、自分を高め、挑戦に邁進した結果、いまの事業、そして社長という立ち位置があったとします。
クリエイティブで発注をするとき、依頼は当然「どうしたらもっと挑戦できる?」からスタートすることになります。挑戦に対する社長の人生を深堀りして、最もその社長や企業にふさわしい「挑戦」を体現するクリエイティブや組織開発がおこなわれることになるでしょう。
しかし、たとえばこの「挑戦して見返してやる」という信念が形成される前、彼は挑戦に執着してるわけではなく、ただ穏やかに本を読んで知的好奇心を満たしていればよかった人だったとします。
つまり、その人にとっては「穏やかに過ごす」が本来一番気楽で自然な一方、「挑戦する」をやればやるだけ「無理してる」状態を強化することになっているわけです。
過去に遡ると「穏やかに知的好奇心を満たす」を得るために「挑戦」をしていたことになります。そうした手段がいつしか目的となって、企業の在り方ができているとき、果たしてどちらの要望に応えるべきなのか。ここに向き合う必要があるわけです。

続いて社会の文脈に対して。
上記の通り、個人文脈でいうと幼少の頃の体験や生活環境によって「何を良いと思うのか」が決定づけられたりします。しかし、これがすべて個人の経験によるものかというとそうではありません。
たとえば「挑戦」という概念をそもそも欲するためには、社会が「挑戦できる」物理環境でなければなりません。仮に中世の身分社会が根強い時代にいじめられていたとして、「挑戦して見返してやる」という思考を持てたかというとそうではないでしょう。
また、現代でもバブル崩壊以前の時代であれば、「リスクをとって挑戦するよりも安定した就職環境でコツコツ努力をすべきだ」という社会風潮が強かったと思われます。故に「挑戦=ただのリスク」という認識が強く、「見返す」という目的を果たすにあたってはむしろ「安定した地位で地道に努力する」などのイメージを浮かべる可能性が高かったのではないでしょうか。少なくとも、現代における典型的な「挑戦」のクオリアとは異なるイメージを持っていたことでしょう。
現在において「挑戦=見返す」が結びつくのは、安定した雇用が揺さぶられ社会的にも「自分で自分の道を切り開く」ことを国や大企業が推奨しているが故のことなのです。
このように何を理想とするか、何を手段として思い浮かべるかは、社会の前提が大きく影響しています。私たちがゼロベースで欲望しているように見えて、その欲望を抱く最初の時点から社会に縛られていることがほとんどなのです。

長くなりましたが、こうした理由から「その言葉に宿るクオリアを”望まされていた”のはなぜか?」を問う必要があるわけです。
何かをクリエイトする際、必ずそこには「幸福のクオリア≒コンセプト」が存在すること。それらは個人の過去の経験、そしてその経験に符合する社会の要請がハイブリットされる形で個人に「望まされる」こと。以上について説明してきました。
ここまで問えてはじめて、その人の望む本当のコンセプト≒幸福のクオリアを理解し、クリエイティブをすることができるわけです。逆にここまで問えずに何かをつくるというのは土地のない状態で建物を立てるようなもので、すぐに瓦解するものになってしまいます。
また、これらはクライアントの理解を促すことだけにとどまらず、あなた自身のコンセプト≒幸福のクオリアにかかっているバイアスを取っ払う際にも重要です。
たとえば、今回の話を通して「挑戦すると幸せになれる」という幸福のクオリアには、無意識下における前提(思い込み)が多分に含まれており、必ずしもその前提は是ではないことがわかったと思います。
しかし、「挑戦とはこういうものだ」「そしてそれらはいいものだ」と、それを疑うことすら考えられない状態でクライアントのクリエイティブに携わったらどうなるでしょう。当然、あなたはクライアントに問いを投げかけることなく”あなたの挑戦のクオリアの前提”にしたがってクリエイティブをすることになります。そうやってできるクリエイティブはそもそも顧客の想定する質感と異なる上に、顧客の望みの奥底にまで辿りつかないものをつくり上げてしまうでしょう。
世の中の幸福のクオリアの前提を理解し、それを解体する術を持つことは、クリエイターがクリエイティブをする第一段階なのです。顧客に向けてクリエイティブを提供する以前に、あなたの中にある無意識の前提(思い込み)を解体することで初めて、あなたはクリエイティブができるようになるわけです。

これが、本コラムを「幸福の解体新書」と名付けた理由です。幸福のクオリアを掴み、その幸福のクオリアが望まれやすい背景、そもそもその幸福の概念が出現している理由をひたすらにネチネチ解剖する。それを通して世の中にある幸福のクオリアを理解し、クライアントが本当に望むクリエイティブを提供できるようになろう。ひいてはあなた自身が幸福に生きられるように、というのが本コラムで提供するコンテンツの内容となります。
つまり、本コラムにおける幸福のクオリアは「世の中の幸福を解体することで幸福になる」ということになります。このフラットに幸福を斬っているように見えることのコラムさえも、何かの前提に立っているわけですね。
さてさて、前提の話がかなり長くなってしまいました。では早速、次回から世の中に流通する幸福の概念を一つ一つ解体していくことにいたしましょう。
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)


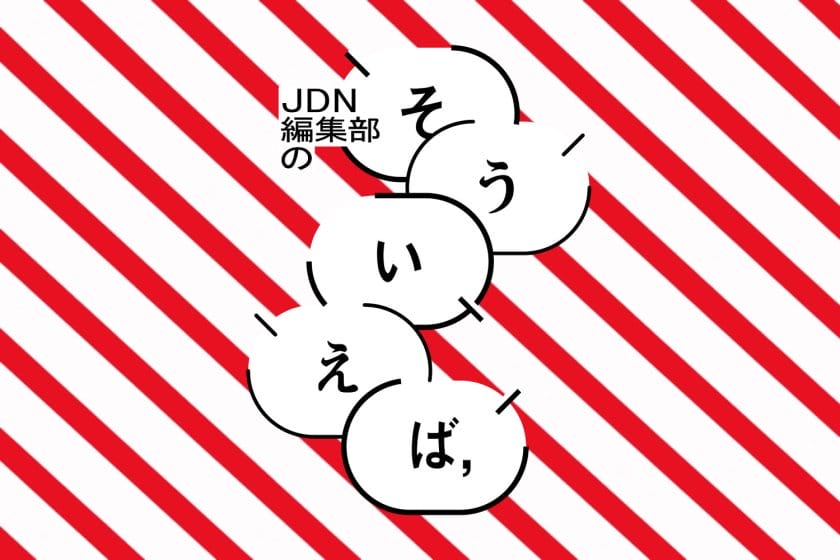

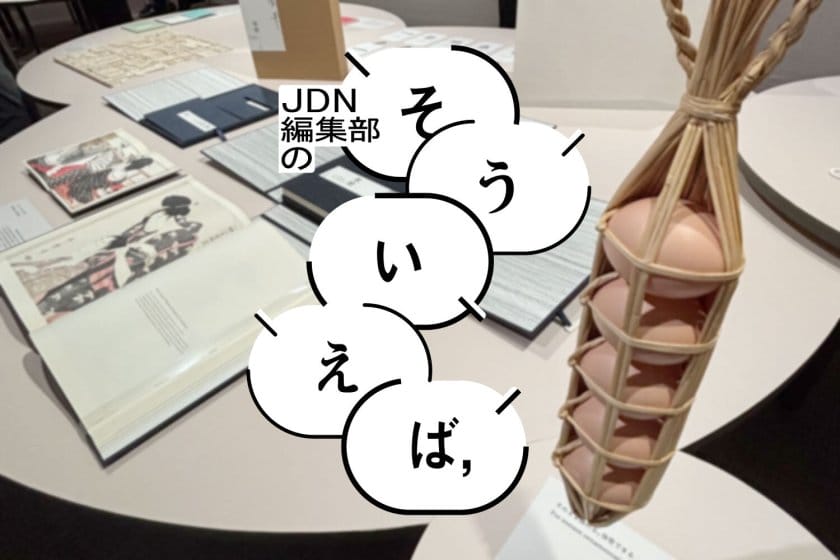
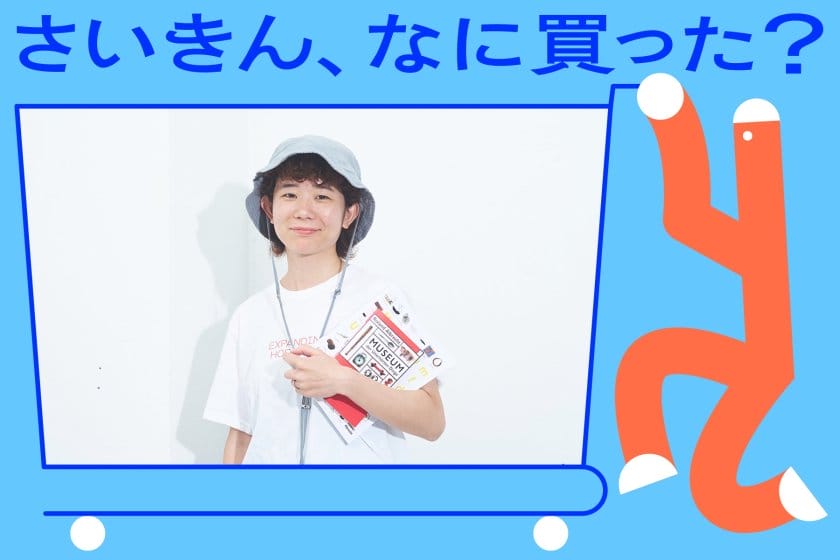
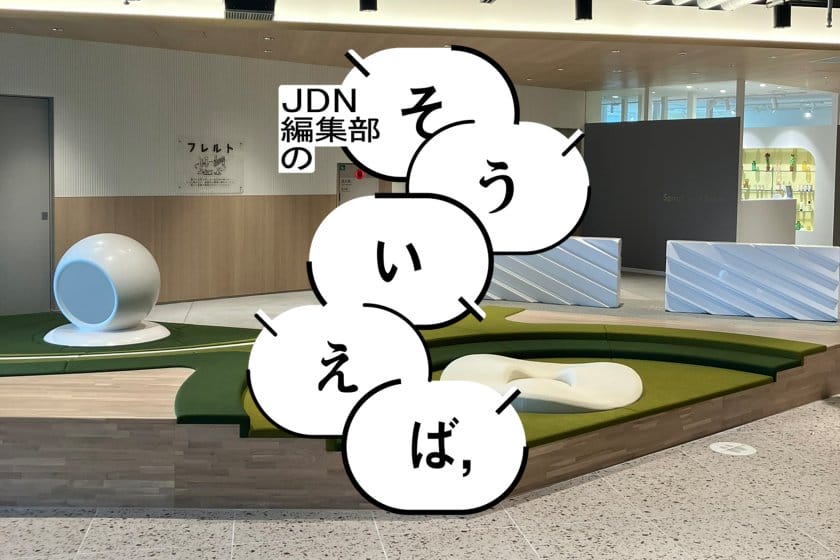
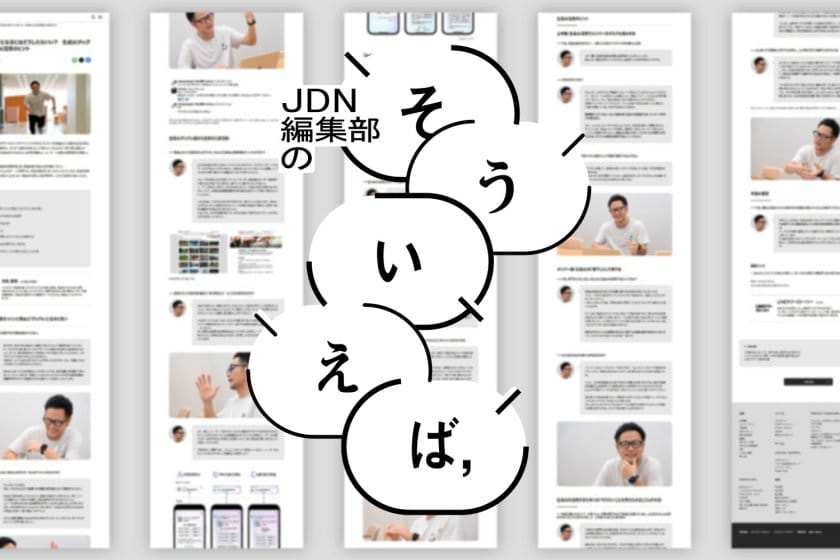




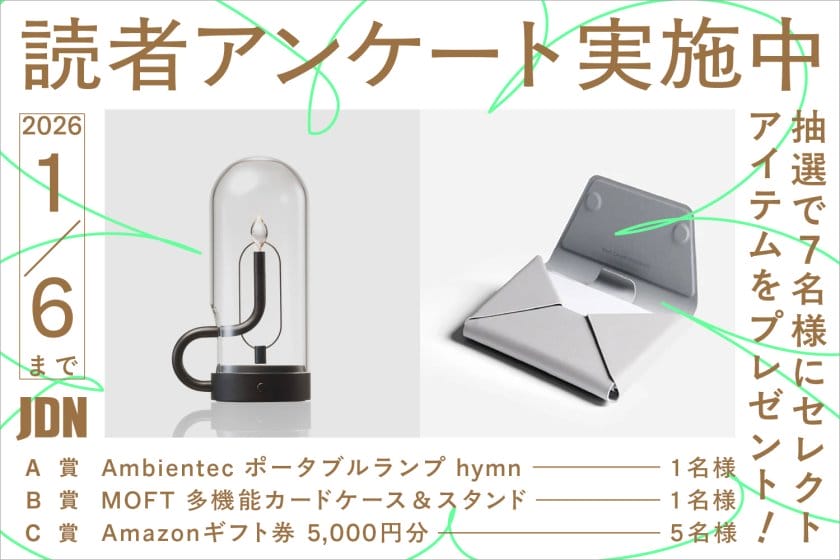
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)




