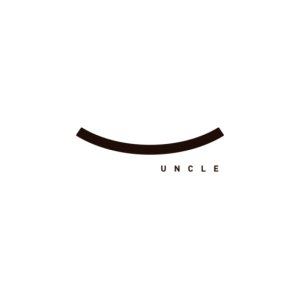“当たり前の日常”だから自分事にできる
――『デザインあneo』という番組が、子どもから大人まで多くの方に愛されているのは、どんな理由からだと思われますか。
そうですね、番組づくりがはじまった当初、関わるスタッフの方々やクリエイターのみなさんが集まってキックオフをおこなったんです。そこで私は「30年後を想像して番組づくりをはじめましょう」とお話ししました。
それだけ続くかどうかはわからないけれど、この番組を見た子どもが、30年後には世の中に自分の意見が通るくらいの立場になっているだろう。その時、世の中がどう変わるのかを楽しみにしてはじめましょうと。なので当初から、30年は番組を続けたいという思いがありました。

実際に番組が続いてるのは、“当たり前の日常”がテーマだからではないでしょうか。デザインはあらゆるところに無数に存在していて、気づいたら目の前にあったり、実は毎日使っていたり。まったく知らないようなものやテーマだと、どこか他人事になってしまいますが、知っていたり手が届くようなものだったりすると、自分事として身近に思えるのかもしれませんね。
私たちが生活する中で、デザインとして意識しているものは本当にほんの一部です。身近で、ごくごく日常の中にあるのに、そのほとんどは無意識の中に存在しています。私たちの当たり前の日常生活は、いろんなデザインが複合的に存在し、組み立てられた中で営まれていますが、当たり前が成り立っているって考えてみたらとてもありがたいことですよね。
そもそも「ありがたい」という言葉の語源は、仏教用語の「有り難し」です。つまり、有ることが難しい、めったにない、珍しい、ありえないことが起きているという意味です。世の中のあらゆるすべてのものにデザインを考えた人たちがいる。そこに気づくことができたなら、きっと「ありがたい」と思えるのではないでしょうか。
それと同時に、例えば本展のように動詞をテーマに世の中を見てみたり、2007年に21_21 DESIGN SIGHTで開催した水をテーマにした「water」展だったり、いろいろなものの見方や考え方、言葉を通して、新たな視点や思考を持つって、とても豊かなことなのではと思います。
デザインについて考えられるのは、幸せであるから
――『デザインあ』がスタートして15年、『にほんごであそぼ』も含めると25年のロングタームになりますが、日本も世界も、激動の時代が続いてきました。
一方で、この数年は特にデジタル空間やAIの進化が著しい中で、今回、動詞をテーマにしたリアルな体験の場をつくられました。ますます、日常の中で、自分の目の前に存在するものや体験、広くさまざまなことへ関心を持ち続けることの重要性が増していくように感じます。
私はつくづく思いますが、デザインについて考えることができる、しかも子どもの頃からというのは、ある意味でものすごく幸せなことなんです。戦争の真っ只中にいて、いつミサイルが飛んでくるかわからない、食べ物も飲む水もないような状況では、それどころではありませんから。しかし日本で暮らしていると、これが当たり前ではないことになかなか気づけませんよね。
実のところ、デザインというものがほんの少しでも、そういったことに目をむける、チャンスやひとつのツールにできないだろうかと思ってはいます。ただ、あんまり説教くさいデザインは嫌いです(笑)。楽しく面白く、でも実はそこに、深い深い本来の意味が込められてる。何事においても、そんな風に組み立てていけたらと、いつも考えているところがあります。

「みんなのあ」にて、「あ」を思い思いに色付けすることができる
――子どもの頃に見ていたものを、大人になったいま改めて見ると、やっぱり見え方や捉え方が変わっていて、そういった深いところに置かれたものに気づくことができるようになっているなと実感します。
情報ってそういうものですよね。そこから読み解く人間の力が変わるから。大人になってふと、子どもの頃に歌っていた童謡や歌を口ずさんだ時に、「あ!そういう意味だったんだ!」と気づくことがありますよね。小説や映画、テレビ番組でも何でもそうですけど、思い返してみたら、そんなに深い意味が込められてたんだって。
だから、“詰め込み教育”って実は重要なんですよ。その時はわからなくても、子どもたちには大切なことや良いものを山のようにどんどん与えて、接する機会をたくさんつくることは、大人の責任だと思います。同時に、良いものを与え続けていると、ひどいものに触れた時、いかに自分が良いものに触れてきたのかにも気づくことができます。

なぜわざわざ、子どもがわからないようなことを教えるのか、子どもには子どもがわかるレベルで、子どもっぽいものがいいのではと疑問に思う親御さんもいますが、私は反対ですね。“子どもっぽい”って大人が勝手に決めたことであって、子どもたちに強制しないことが重要です。この「デザインあ展neo」も、誰ひとり子どもっぽいものをつくろうなんて思っていませんし、大人が本気で遊びながらつくっていますから。
子どもは気づく、小さないたずら
――だからこそ、そうそうたるクリエイターの方々が、Eテレの番組に関わっていらっしゃるのですね。
そうなんです。例えば、『ピタゴラスイッチ』の佐藤雅彦さんも仕事を一緒にしていたことがあるし、よく存じあげているんですけど、この人は天才だなと思いました。『ピタゴラスイッチ』も2002年から続いていますが、いろんなアイデアを形にしていったEテレは、本当に大きな可能性を持つところだなと当時思いました。
Eテレの番組は、アイデアをすぐに形にして放送に向けて動いてくれるので、「え?放送って全国放送ですよね?」ってよく驚きましたからね(笑)。
――常に実験的なことをおこなったり、新しい可能性やアイデアを試したりするには、ある程度、物理的にも精神的にも余裕がないと難しくないでしょうか?
いやいや、みんな余裕なんて持てていないと思いますよ、そこはあまり関係ないんじゃないかな。
私は子どもの頃から、誰かに喜んでもらいたい、笑ってもらいたいって思っていたので、何かしらのいたずらを仕掛けるのも大好きだったんです。いまでも仕事で時々やるんですよ。やってもやらなくても売上に影響しないようなら、ちょっとデザインで遊ばせてくださいって交渉して(笑)。
もちろん、一応大人ですから、売上目標をクリアするとか、やってはいけないような時はやりませんよ。でも、いたずらできるかできないかは常に狙っています。真面目な顔してね(笑)。それを誰かがふいに見つけて喜んでくれれば、私もすごく嬉しいです。
そして、そういう意外なところに子どもって気づくんですよね。些細なところを本当によく見ている。大人が見てほしいところは見ていないのに(笑)。貼ってあるものは剝がそうとするし、穴があれば指を突っ込むし、隙間があれば引き離そうとするし。でも展覧会では、3期目ともなれば想定内です。「だいたい壊されますから、最初から予備をつくっておきましょう」って(笑)。

動詞「たべる」に展示されている「たべられるきもち」
本当に、大人が思いもかけないようなことをするし、本当に最強で面白い。それでいて子どもって、誰もが楽しめるようなとてもユニバーサルな視点の持ち主でもありますしね。『デザインあneo』の番組も展覧会も、そんな感覚がベースとなってつくっている気がします。
まだ出会ったことのない難題に悩みたい
――さて、これからの『デザインあneo』についてうかがっていきたいのですが、今後はどんなテーマや表現に取り組んでみたいですか?
クリエイターのみなさんからは、今後も面白いアイデアがいっぱい出てくるだろうし、そこから新たな方法や表現を見つけていくのかな。
今回の展覧会ではじめて登場したコンテンツが、番組でも放送されはじめましたが、番組と展覧会、そしてグッズのほかに、あるとすればどんなメディアだろうとか。いまは何を思いつくのか想像もつかないけれど、きっといろんな可能性が無限にあって、こんなことをやったらどうだろうと突然、思いつきそうだし、考えていきたいですね。
――ちなみに普段は、どんな時にアイデアを思いつくことが多いのでしょうか?
いろいろですよ。ある時フッとか、電車に乗ってる時にとか。「あれをやってみたら面白いんじゃないかな……」って思いつくけれど、そこでメモを取ることはしないんですね。
面白いアイデアって、脳の中に記憶が残るから、一旦忘れてしまっても必ずまた思い出すんですよ。そういえばこの間も思ったなって時は、つまり自分はそれをやりたいってことなんだなって。逆に思い出せないものは面白くないってことだろうし、その方が気楽じゃない?

あと、さっきのいたずらの話ではないけれど、普段の仕事でも、依頼がないのによく提案しますね。依頼はただの“入口”であって、そこをきっかけに、こんなことをやったらどうでしょうって、思いついたらいっぱいお伝えしちゃうんです。
ダメでもともとで良いんだし、いつも余計なお世話をしています(笑)。でもそれが時々、動きはじめたり、形になりそうってなったり、「これは面白いことになってきたぞ!」ってね。
――普段からとても自然に、さまざまなものごとについて考えている一方で、緩急をつけた思考の仕方そのものもユニークです。意識してそうなさっているのでしょうか?
どうなんでしょうね、自分のことって自分ではわからないですよね……。でも、いろいろなことをさせていただいているので、仕事における自分のスタイルって決めていないんですよ。
いろんなプロジェクトが同時並行で進んでいますから、あるプロジェクトでアイデアが出なければ、別のことに取り組んで、そのうち、「あ!」って、アイデアが出たところで再び取り組んで。締切が迫っている場合は、「この1時間でアイデアを5つ出すぞ!」と集中する時もありますが(笑)。無理にやろうとせず、いまはできるだけ自然体でいますね。

――最後に、佐藤さんご自身がこれからやってみたいことをお聞かせください。
まだ出会ったことがない物事に出会いたいですね。自分がやりたいことって、だいたい自分の想像の範疇でしかないですから。これまでの仕事でも、出会ったことがないものや、やったことのないことを積極的にやらせてもらってきました。だから、出会ったことがないことに出会いたい。そしてそれについて悩みたいですね(笑)。
やっぱり、仕事って難しい方が面白いじゃないですか。だいたいのことはもう「こうすればこうなるだろうな、できるだろうな」と、ある程度の予想がつきますし、もちろん、きっちりと取り組みます。
でも、「どうやったらいいかわからないな、うわぁー……」って悩ませてくれる機会は、私にとってものすごい喜びです。「よくぞこんな難しいことを!」というテーマに出会えると嬉しい。悩みながらも開拓できるから、もうニコニコしていますよ。なんというか、先が見えないぐらい難しい、やったことのないことをやって難しいなって思えることをやってみたいですね。

■デザインあ展neo
https://exhibition-ah-neo.jp/
取材・文:Naomi 撮影:葛西亜里沙 編集:岩渕真理子(JDN)
- 1
- 2
![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

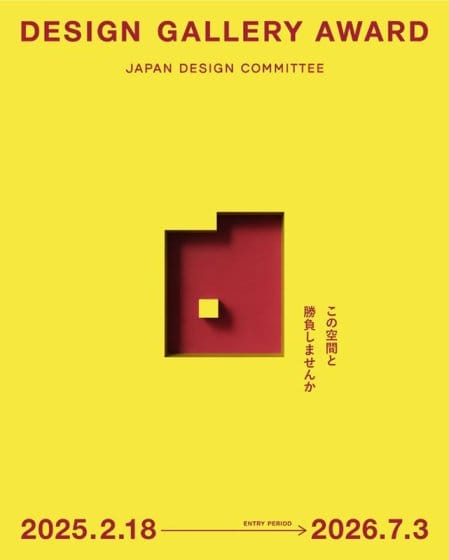



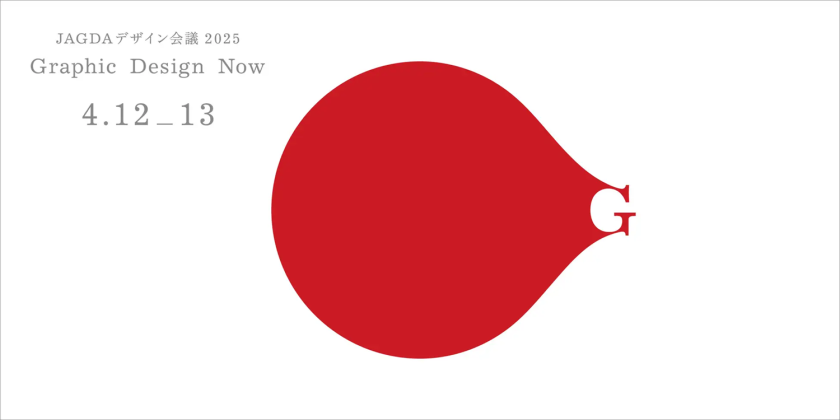
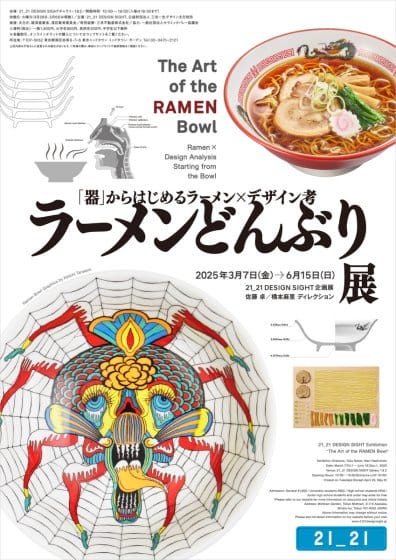








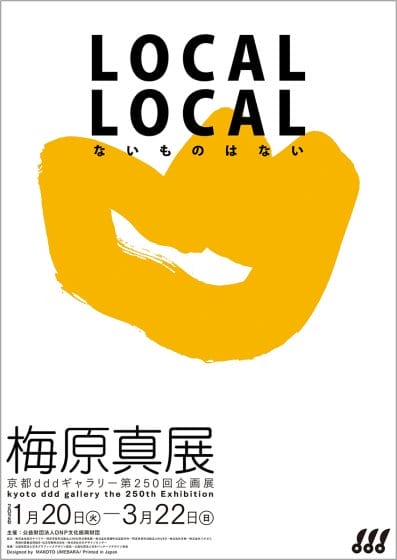
![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)